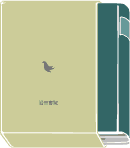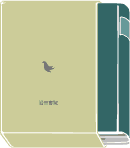|
|
往来物は、手習いの手本や素読・教訓の教材として、中古・中世・近世を経て近代初頭に至るまで、さまざまな展開をしつつ広く行われた書籍の総称である。
本書では、江戸時代の出版文化に関する研究成果と、往来物の研究成果とを合わせて考察する方法を採った。具体的には、対象となる事柄を定めてデータを多く集めて見ていく方法と、一人の作家を扱って、そこから立ち現れる情報を組み立てて、その作家の手になる往来物の個性を浮き彫りにする方法である。
|
| 【主要目次】 |
序 章 (「往来物」に関する先行研究/問題の所在/本論の目的・構成)
|
第1章 「往来物」が採り入れた和歌、及び出版の問題
第1節 「往来物」における七夕の歌-類題集の利用-
(「往来物」の巻頭・巻末・頭書の和歌/「往来物」の「七夕歌」の背景/類題集の利用/近世堂上派和歌と庶民の子どもたち)
第2節 「大坂進状」「同返状」をめぐる出版書肆の問題
(改変に関する従来の指摘と本節で明らかにすること/改変過程の変遷と出版事情/出版統制と伝統の継承)
付 論 『直江状』について
|
第2章 「往来物」の作者と書肆-一九・馬琴の方法と意識及び書肆とのかかわり-
第1節 十返舎一九の文政期往来物の典拠と教訓意識
(一九の「往来物」についての従来の指摘/山口屋藤兵衛版の『和漢三才図会』利用/『和漢三才図会』利用の意義/西宮新六版の道中記型の往来物/一九の「往来物」とのかかわり方と教訓)
第2節 曲亭馬琴著『雅俗要文』の成立と意義
(従来の指摘と問題点/本書の成立事情と馬琴の思い/本書の特色/本書の意義)
付 論 明治初年の文章表現と馬琴-『こがね丸』を中心に-
(こがね丸に関する従来の説の問題点/天明ぶりの黄表紙類とこがね丸の構想/こがね丸の文章表現/こがね丸刊行当時の文体意識/明治初年の人々と馬琴/狐の裁判の利用/こがね丸の価値)
|
資料編
女中用文玉手箱/民間當用 女筆花鳥文素/雅俗要文
|
|
|
|