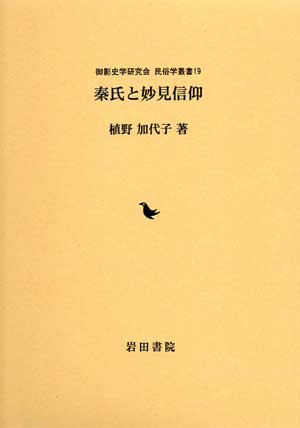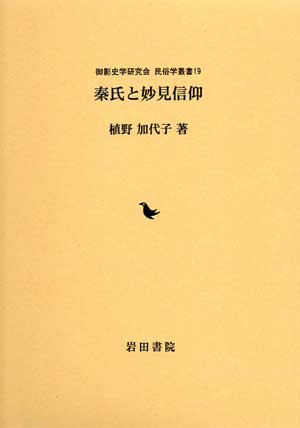本書では、畿内を中心に古代の妙見信仰とそれに関わった氏族である秦氏が、ことに海上河川などの水上の物資運搬のため、ことさら夜の水上交通の航行に妙見を信仰したものであることを明らかにし、併せて平安貴族社会における妙見信仰についても考察した。
第1章では、古代から近世までの舟運を取り上げ、夜に舟出する困難や潮の流れを考察。
第2章では、水上交通を中心とした秦氏の物資運搬経路を検討。
第3章では、兵庫猪名川添いに秦氏の伝承が点在する理由を通し、秦氏の活動の跡を検討。
最後の第4章では、妙見の図像や修法を中心に、貴族社会での妙見信仰について考察。
|
| 【主要目次】* は新稿 |
|
| 第1章 |
海上・河川交通と信仰 |
| 第1節 |
夜に船を出すこと |
| 第2節 |
津田川を考える
−行基の開発と近木川との関わりの中で− |
| 第3節 |
葛城修験の一考察−序品の地をめぐって− |
| 第4節* |
海上交通と犬鳴山燈明ケ嶽と
−尊星王妙見大菩薩との関わりの中で− |
| 第2章 |
妙見信仰と秦氏の水上交通
|
| 第1節 |
妙見信仰と秦氏の水上交通
|
| 第2節 |
木上山海印寺の妙見信仰
−木津川の河川交通をめぐって− |
| 第3節 |
長岡京への物資輸送と運搬経路
−妙見信仰との関わりの中で− |
| 第3章 |
能勢妙見と河川流通
|
| 第1節 |
能勢妙見と秦氏
−猪名川の水上交通との関わりの中で− |
| 第2節 |
秦氏にとっての猪名川の役割
−摂津国能勢郡の山林との関わりの中で− |
| 第3節 |
アヤハ・クレハ伝承と水上交通
−兵庫県西宮市松原町の伝承を中心に− |
| 第4章 |
平安貴族社会と妙見信仰 |
| 第1節 |
妙見菩薩の像容
−平安時代後期から室町時代の図像を中心に− |
| 第2節* |
尊星王法と僧侶たち−11世紀の三井寺を中心に− |
|
|
  |