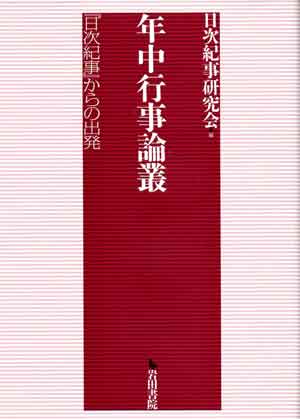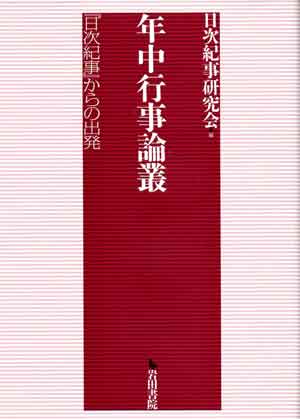黒川道祐『日次紀事』貞享2年(1685)は、実際に洛中洛外を足で歩いて、フィールド調査をした成果が、余計な考察を加えることなしに、正月元日から月日を追って詳細に整理されており、その内容に信が置けるため、その紀事を子細に読み込むことによって、今日の京都の年中行事や習俗の本来の姿を知ることができる。
本書は、民俗・歴史・芸能史などの研究者によって始められた読書会の成果。 |
| 【主要目次】 |
|
| 第1部 行事・儀礼へのまなざし |
|
| 「節季候」考 |
山路 興造 |
| 千本ゑんま堂大念仏狂言考 |
斉藤 利彦 |
鞍馬寺の竹伐り会
−中世蓮華会試論− |
野地 秀俊 |
祇園会山鉾鬮取考
−戦国時代から近世前期にかけて− |
河内 将芳 |
年中行事としての相撲儀礼の展開
−伝承と文献との整合性についての試論− |
橋本 章 |
| 和泉流狂言《瓢の神》成立考 |
長田あかね |
室町幕府の年中行事
−同朋衆の役割を中心に− |
家塚 智子 |
中国の山車
−唐玄宗朝を中心に− |
原田 三壽 |
| |
|
| 第2部 組織・担い手からの広がり |
|
貿易扇−
一時代を担った京都の産業− |
佐野 惠子 |
| 木地屋「根元地」の近代 |
木村 裕樹 |
| 「えびす」にまつわる人々 |
中野 洋平 |
神性を帯びる山鉾
−近世祇園祭山鉾の変化− |
村上 忠喜 |
日光東照宮御神忌祭と田楽法師
−変容する祭礼と芸能者の交渉史− |
吉村 旭輝 |
| 中世の楽琵琶の宗家・西園寺家と妙音天信仰 |
大森 惠子 |
| 中世北野社御供所八嶋屋と西京 |
高橋 大樹 |
松梅院禅予と宮寺領の回復
−所領注文作成を例にして− |
貝 英幸 |
|
|
|
|
  |