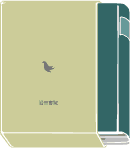 |
国民国家形成期の地域社会 −近代茨城地域史の諸相− 佐々木 寛司編 (茨城大学教授/1949年生まれ) 2004年4月刊 ISBN4-87294-308-2 A5判・264頁・上製本・函入 5900円 品切れ |
 | |
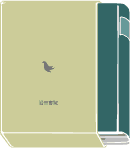 |
国民国家形成期の地域社会 −近代茨城地域史の諸相− 佐々木 寛司編 (茨城大学教授/1949年生まれ) 2004年4月刊 ISBN4-87294-308-2 A5判・264頁・上製本・函入 5900円 品切れ |
 | |
| 「…19世紀後半に起こった明治維新という変革期に、日本もこの国民国家体制の下に強制的に編入されるなかで、「万国対峙」の基底的方向として国民国家の枠組みを積極的に導入 することを企図した。地域社会も、この国民国家形成の下で、さまざまな対応と変容を経験することになる。本書は、かかる地域社会の動向を茨城県域を対象として分析したものである。」(佐々木「本書の概要」より) 第1編は、後期水戸学を代表する著作『新論』にスポットをあて、それが幕末志士の心情をいかに捉え、その志士的言動(ナショナリズム)の源泉となったのかを2本の論攷によって検証した。第2編は、19世紀後半から20世紀初頭の当該過程における「地域」の動向を追跡した3稿からなる。そして第3編は、当該期の地域経済の変容過程を、舟運と地主肥料商に焦点をあてた2本の論文からなっている。 |
||
| 【主要目次】 | ||
| 第1編 | 国民国家形成のイデオロギー | |
| 第1章 | 『新論』における国体論の位相─────────菅谷 務
−転換期の言説− |
|
| 第2章 | 『新論』受容の一形態─────────桐原 健真 −吉田松陰を中心に− |
|
| 第2編 | 国民国家形成期における地域秩序の動揺と再編 | |
| 第3章 | 地租改正期の地域社会─────────佐々木寛司
−動揺する地域社会の実相− |
|
| 第4章 | 作成されていた大暴風雨記録の全容─────────松澤 克昭 −明治後期茨城大暴風雨記録『被害一斑』とその意義について− |
|
| 第5章 | 帝国在郷軍人会成立の社会的基盤─────────宮本 和明
−大正期茨城県の農村を素材として− |
|
| 第3編 | 資本主義確立期における地域経済の変容 | |
| 第6章 | 利根川水系舟運の推移と地域社会─────────桐原 邦夫
−鉾田河岸・小川河岸を事例として− |
|
| 第7章 | 新興養蚕地域における地主肥料商の経営展開─────────市川 大祐 −茨城県結城郡廣江嘉平家の事例− |
|
 |