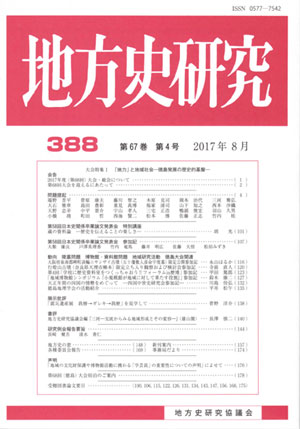 |
地方史研究 地方史研究協議会刊(会長:久保田昌希) http://wwwsoc.nii.ac.jp/chihoshi/ ※335号以前は、名著出版 (http://www.meicho.co.jp/)発売 *381号以前と392~402,411号は取扱終了 |
| 第437号(75-5)(2025.10) | ||
| A5/144p 1143円(税別) | ||
| <大会特集Ⅱ 福島の歴史像―交錯・衝突・交流からみる狭間の地域―> | ||
| 問題提起 | ||
| 13 考古学からみた福島県域の歴史的特性 | 菊地 芳朗 | |
| 14 中近世移行期南奥の統合と文書の年代比定 | 佐藤耕太郎 | |
| 15 福島県域における旗本知行所の成立 ―陸奥国岩瀬郡三枝家と溝口家を例に― |
野本 禎司 | |
| 16 近世白河の陸奥国における認識 | 内野 豊大 | |
| 17 出稼ぎ・奉公・入百姓 ―近世越後から南奥州への人口移動― |
原 直史 | |
| 18 職人の出稼ぎと地域間交流 ─会津茅手と越後大工─ |
内山 大介 | |
| 19 いわき地方の民俗芸能の伝播と展開について | 田仲 桂 | |
| 20 東北の自由民権運動における福島の位置 | 友田 昌宏 | |
| 21 福島県の境 | 徳竹 剛 | |
| 22 東蒲原郡の新潟・福島両属論を見直す ―赤城源三郎・『東蒲原郡史』・藤木久志の提起― |
竹田 和夫 | |
| 23 三木宗策《阿部茂兵衛翁銅像》 ―福島県における近代モニュメント彫刻の一考察― |
髙橋 翔 | |
| 24 福島県における史料ネット運動と新たな歴史像の可能性 | 阿部 浩一 | |
| 25 昭和・平成・令和の双葉郡内町村史編纂にむけて | 門馬 健 | |
| 26 原発事故被災地の歴史資料救出と大字誌 | 西村慎太郎 | |
| 明治三年六月民部省布告と国絵図調進 ―武蔵国を事例として― |
阿部 俊夫 | |
| 動向(大会関連) | ||
| 須賀川市の歴史資料の保全と活用について | 宮澤 里奈 | |
| 福島県における民権運動の顕彰活動報告 | 渡辺 実 | |
| 展示批評 | ||
| 館山市立博物館 没後100年記念企画展「資生堂創業者 福原有信と館山」 | 長友美恵子 | |
| 茨城県立歴史館 開館50周年記念特別展「雪村 常陸に生まれし遊歴の画僧」 | 川延 安直 | |
| 書評 | ||
| 地方史研究協議会第73回(館林)大会成果論集 『“川合”と「里沼」―利根川・渡良瀬川合流域の歴史像―』 |
澤村 怜薫 | |
| 研究例会報告要旨 | ||
| 西摂の一隅からみた「ひょうご五国」 | 橋本 久 | |
| 土岐氏の内訌と足利義満 ―土岐満貞の動向を中心に― |
格和 賢 | |
| 近世中期、阿武隈高地の金融資本 ―北方村佐藤勘之丞家を中心に― |
小松 賢司 | |
| 大正期における福島県の物産発信 ―三越での東北名産品陳列会を例に― |
荒川 瑛楠 | |
| 地方史の窓/新刊案内/受贈図書論文要目 | ||
| 第436号(75-4)(2025.08) | ||
| A5/148p 1143円(税別) | ||
| <大会特集1 福島の歴史像 ―交錯・衝突・交流からみる狭間の地域―> | ||
| 問題提起 | ||
| 1 福島県前田遺跡出土のアスファルト資料の産地推定について | 三浦 武司 | |
| 2 古墳出現期における福島県の地域性 | 神林幸太朗 | |
| 3 西久保遺跡からみた古代信夫郡 | 上田 優喜 | |
| 4 古代陸奥国南部における奥羽山脈の東と西 | 垣内 和孝 | |
| 5 中世考古学からみた北東日本海域との交流 | 佐藤 俊 | |
| 6 戦国期の福島 ―僧侶や商人の動向から― | 高橋 充 | |
| 7 奥会津における近世運輸機構 ―狭間の地域に生きた百姓仲附駑者― |
板倉 正哉 | |
| 8 伝説の「狭間」としての福島 | 小田倉仁志 | |
| 9 信達地方における近世民衆思想の再考 ―菅野八郎研究を事例として― |
青野 誠 | |
| 10 明治前半期伊達郡の養蚕伝習所と伝習生 | 阿部 俊夫 | |
| 11 会津若松と若松連隊 | 栗原 祐斗 | |
| 12 昭和戦前期における相馬地方の報徳運動 ―小学校長・飯野次郎が経験したこと― |
須田 将司 | |
| 第66回日本史関係卒業論文発表会 | ||
| 特別講座 史料との邂逅 | 永井 博 | |
| 参加記 | 志村奏恵 外舘涼真 加藤菜穂子 鹿山結 本多雄登 田代恵悟 村花有覇 |
|
| 動向 | ||
| 狐井塚古墳(陵西陵墓参考地)飛地ろ号ほか外構柵改修工事に伴う立会調査見学参加記 | 鬼塚 知典 | |
| 大山古墳(仁徳天皇百舌鳥耳原中陵)立入り観察参加記 | 小林 孝秀 | |
| 日本アーカイブズ学会2025年度大会参加記 | 林 かおる | |
| 展示批評 | ||
| 郡山市歴史情報博物館の開館と第1回企画展「過去と未来をつなぐ新たな博物館の挑戦」 | 石澤 夏巳 | |
| 上田市の仏教美術展実行委員会「ハッケン!上田の仏像」 | 原田 和彦 | |
| 千代田区立日比谷図書文化館特別展「実録 桜田門外の変」 | 山本 遥大 | |
| 書評 | ||
| 『“出入り”の地域史―求心・醸成・発信からみる三重―』 | 厚地 淳司 | |
| 研究例会報告要旨 | ||
| 五国の多様性と交流 | 藤本 史子 | |
| 兵庫大会の成果と課題 ―新しい兵庫地域史研究にむけて― |
山﨑 久登 | |
| 近代深大寺文書と天台宗の動向について | 生駒 哲郎 | |
| 元三大師像の修理報告 | 菱沼 沙織 | |
| 地方史の窓/新刊案内/受贈図書論文要目 | ||
| 声明 日本学術会議第194回総会決定を支持し、「日本学術会議法案」の廃案を求める声明 | ||
| 第435号(75-3)(2025.06) | ||
| A5/150p 1143円(税別) | ||
| <特集 地方史研究と歴史教育> | ||
| 1 地域資料から組み立てる観光教育 ―東京都立新島高等学校での授業を事例に― |
山﨑 久登 | |
| 2 地域博物館と博学連携、歴史教育について ―春日部市郷土資料館を事例として― |
実松 幸男 | |
| 3 大学における歴史系教員養成と地方史研究 | 野本 禎司 | |
| 4 大学における教員養成と地域資料の活用 | 千葉真由美 | |
| 5 受け継ぎ、教科をつなぎ、地域とつながる史資料の活用 | 竹田 和夫 | |
| 6 学校教育における歴史学習と地域 -教育課程を踏まえた社会教育との連携・展望- |
藤野 敦 | |
| 7「地方史研究と歴史教育」参加記 | 百濟 正人 | |
| 8 シンポジウム「地方史研究と歴史教育」に参加して | 富田三紗子 | |
| 境目相論における近隣交渉と用達 -近世中期の熊本藩・幕府領日田関係を事例に- |
川端 駆 | |
| 幕末期地域社会における民衆教化と学問 ―早田伝之助と信達地方を中心として― |
青野 誠 | |
| 丹波国桑田郡における中世の材木輸送について -京都府立京都学・歴彩館所蔵の中世文書から- |
荒田 雄市 | |
| 第66回 日本史関係卒業論文発表会要旨 | 瀧澤胡桃 磯部美咲 鈴木夢乃 秋場真澄 上山裕太 瀬尾智優 武田侑大 若島 壮 田代健留 宮井知優 森田和航 小林江梨花 池滝駿介 小畑勇樹 角田 舞 山田真也 萩本大翔 吉川 葵 小川幸介 中村祥吾 寺谷嘉泰 長嶋 優 小林亮太 矢島康地 |
|
| 動向 | ||
| 神奈川における地域資料掘り起こしと教材化の取り組み ―高校歴史分科会日本史研究推進委員会の活動― |
矢野 慎一 | |
| 「第19回歴史教科書シンポジウム ―中学歴史教科書問題と高校歴史教育の問題―」参加記 |
風間 洋 | |
| 「神武天皇陵御休所建仁寺垣改修工事見学会」に参加して | 菅野 洋介 | |
| 東山本町陵墓参考地ブロック塀改修工事・誉田御廟山古墳(応神天皇陵)外構柵改修工事立会調査見学参加記 | 小林 孝秀 | |
| 令和6年度藤沢市史講座(主催:藤沢市 後援:地方史研究協議会) 『藤沢市文書館 開館50周年を記念して』参加記 |
平田 恵美 | |
| 研究例会報告要旨 | ||
| 新井浩文『文書館のしごと』から考える | 新井 浩文 | |
| 国文学研究資料館アーカイブズ学研究分野の廃絶の危機に警鐘を鳴らし、 機能充実・強化を訴える声明 | ||
| 森安彦先生の訃報 | 髙木 俊輔 | |
| 地方史の窓/新刊案内/受贈図書論文要目 | ||
| 第434号(75-2)(2025.04) | ||
| A5/126p 1143円(税別) | ||
| 陸奥八幡氏の基礎的考察 | 高橋 和孝 | |
| 近世中期姫路藩領における魚問屋の存在形態 -播州加古郡東本庄村を事例に- |
近都 兼司 | |
| 明治初期の府県庁における意思決定 -千葉県庁を事例に- |
柏原 洋太 | |
| 動向 | ||
| 地方史研究協議会・交通史学会合同例会「東海道研究の最前線」に参加して | 宮川 充史 | |
| 大山古墳外堤整備工事に伴う限定公開参加記 | 森 正太郎 | |
| 「高輪築堤跡現地見学会―確認調査の成果を公開―」参加記 | 伊藤 宏之 | |
| 展示批評 | ||
| 幸手市郷土資料館 令和六年度特別展 「幸手小学校の歴史―資料が受け継ぐ明治・大正・昭和の姿―」 |
山田 篤史 | |
| 兵庫県立兵庫津ミュージアム 秋季企画展 「イワシとニシンと兵庫津の商人」 |
宮坂 新 | |
| 研究例会報告要旨 | ||
| 交代寄合芦野家の知行所支配 -下ノ庄八ヶ村「取締」家の分析を中心に- |
中谷 正克 | |
| 那須の文籍 狂歌師玄仲那言匕盛 | 小林 義朗 | |
| 関東大震災における金丸原演習場での朝鮮人の収容 | 作間 亮哉 | |
| 参勤交代制と大名家臣団 -東海道通行の大名家を事例に- |
仲泉 剛 | |
| 駿府在勤の武士と東海道 -八戸藩南部家の駿府加番を事例に- |
岡村 龍男 | |
| 東海道二川宿における伝馬役負担の実態 | 久住祐一郎 | |
| 地方史の窓/新刊案内/受贈図書論文要目 | ||
| 声明 日本学術会議の解体・変質を招く「法人化」に反対し、法案撤回を求める声明 | ||
| 第433号(75-1)(2025.02) | ||
| A5/160p 1143円(税別) | ||
| 戦国期今川領国における寺院アジールの機能 ―佐藤孝之氏の「山林」論を中心に― |
夏目 琢史 | |
| 植民地台湾における漁場秩序の再編について ―植民地期初期基隆庁下のテングサ漁場を事例として― |
新垣 夢乃 | |
| 2024年度 第74回(兵庫)大会参加記 | 長谷川明則 大沼大晟 山西康之 林晃之介 赤井誠 近都兼司 三浦加帆 松本充弘 横井蒼大 |
|
| 動向 | ||
| 日本歴史学協会報告 | 桑原 功一 | |
| 歴史シンポジウム「水無瀬離宮の黎明と終焉―水無瀬という場を考える―」参加記 | 山本 雅和 | |
| 地方史研究協議会2023年度 第7回研究例会(伊予史談会との合同例会) 「足立重信没後400年記念シンポジウム」参加記 |
大上 幹広 | |
| 研究例会報告要旨 | ||
| 考古学研究から見た兵庫県の特性および展望 | 森岡 秀人 | |
| 幕末期の「摂海」警衛と兵庫 | 後藤 敦史 | |
| 足立重信文書と加藤嘉明の時代― 一次史料にみる重信像― |
山内 治朋 | |
| 道後平野における地理的環境の復元 ―埋蔵文化財調査成果を中心として― |
三好 裕之 | |
| 歴史地理学からみた石手川・重信川旧流路 | 柚山 俊夫 | |
| 地方書と地方巧者の変容 | 工藤 航平 | |
| 地方史の窓/新刊案内/受贈図書論文要目 | ||
| 第432号(74-6)(2024.12) | ||
| A5/86p 1143円(税別) | ||
| 大坂城落城時の落人狩りと捕縛された落人の処遇について | 長屋 隆幸 | |
| 摂河国役普請制度における役の免除について | 飯沼 雅行 | |
| <小特集 被災文化財の保存と活用―熊本から考える―> | ||
| 熊本地震で被災した古墳の復旧 ―その現状と課題― |
杉井 健 | |
| 被災史料が語る井寺古墳 ―未指定文化財と国指定史跡との間― |
三澤 純 | |
| 細川家歴代当主甲冑の「発見」 ―被災文化財研究の可能性― |
今村 直樹 | |
| 研究例会参加記 何によって文化財を次世代へ「つなぐ」のか | 小粥 祐子 | |
| 日本歴史学協会第29回史料保存利用問題シンポジウム 「裁判記録の現状と課題―保存と公開体制の確立を―」に参加して | 淺井 良亮 | |
| 書評 | ||
| シリーズ 地方史は面白い06 地方史研究協議会編『徳島から探究する日本の歴史』 |
湯浅利彦 宮本和宏 |
|
| 地方史、私の履歴書 草莽の志士、そして農民日記 |
髙木 俊輔 | |
| 地方史の窓/新刊案内/受贈図書論文要目 | ||
| 声明 民具(有形民俗文化財)の廃棄問題に対する声明 | ||
| 第431号(74-5)(2024.10) | ||
| A5/122p 1143円(税別) | ||
| 大会特集Ⅱ 五国の多様性と交流 ―兵庫地域史研究の新たな試み― | ||
| 問題提起 | ||
| 17 地域の遺跡を図化する、遺跡立体図 | 永惠 裕和 | |
| 18 但馬の画家・齋藤畸庵 | 山口奈々絵 | |
| 19 民芸運動によって抹殺された瀬戸内の木食たち | 西海 賢二 | |
| 20 山間部からみる兵庫県の近現代 | 長谷川達朗 | |
| 21 兵庫県における観光地選定イベント | 吉田 隼人 | |
| 22 伊丹市における修史事業 | 新宮 由真 | 23 但馬地域における歴史文化の継承 | 石松 崇 |
| 24 稲岡工業株式会社文書保存モデル | 増田 行雄 | |
| 25 財産区の設置する地域史料館の運営について | 道谷 卓 | |
| 26 地域住民と協働した資料保全活動の成果と課題 | 井上 舞 | |
| 27 歴史資料ネットワークの現状と課題 | 跡部 史浩 | |
| 28 資料のデジタルアーカイブ化 | 中谷真悠香 | |
| 近世後期仙台藩領気仙郡における御普請の郡受制の展開 | 大銧地駿佑 | |
| 動向 | ||
| 歴史シンポジウム | ||
| 「後鳥羽上皇が造った都市 水無瀬離宮を考える」に参加して | 渡邊 浩貴 | |
| 日本アーカイブズ学会大会企画研究会を聞いて | 小谷 啓人 | |
| 「博物館のまち・北九州市」の創造 | 日比野利信 | |
| 地方史、私の履歴書 都市史研究と自治体史の編纂・執筆 | 今井 修平 | |
| 地方史の窓/新刊案内/受贈図書論文要目 | ||
| 第430号(74-4)(2024.08) | ||
| A5/150p 1143円(税別) | ||
| 大会特集Ⅰ 五国の多様性と交流 ―兵庫地域史研究の新たな試み― | ||
| 問題提起 | ||
| 1 淡路島の青銅祭器の動向について | 定松 佳重 | |
| 2 但馬 横穴式石室の導入と展開からみた地域性と交流 | 仲田 周平 | |
| 3 『播磨国風土記』研究の新潮流 | 坂江 渉 | |
| 4 丹波焼生産開始の再評価 | 松岡 千寿 | |
| 5 五国の神人 | 大村 拓生 | 6 中世五国の一宮と地域 | 田村 正孝 |
| 7 近世史研究における西摂・播磨 | 今井 修平 | |
| 8 近世西宮えびす信仰の展開と兵庫 | 戸田 靖久 | |
| 9 播磨の近世たたら製鉄をめぐる諸問題 | 土佐 雅彦 | |
| 10 篠山藩における皮多村の役負担について | 今井 進 | |
| 11 丹波の村人にとっての大坂城加番 | 山内 順子 | |
| 12 解明すすむ幕末の姫路藩 | 藤原 龍雄 | |
| 13 庚午事変と淡路島の兵庫県編入 | 金田 匡史 | |
| 14 近代における姫路と姫路城 | 竹内 信 | |
| 15 明治前期における兵庫県の議会と政党 | 出水清之助 | |
| 16 明治四〇年代・神戸市近郊における地域開発から見る「多様性」 | 戸部 愛菜 | |
| 第65回日本史関係卒業論文発表会 特別講座 地方史研究の歴史をたどる |
山田 邦明 | |
| 第65回日本史関係卒業論文発表会 参加記 | 吉田勝弥 末武宏太 小幡哲央 草山菜摘 佐藤友美 山内裕太 佐藤夢来 |
|
| 動向 | ||
| 「全国史料ネット研究交流集会in首都圏」に参加して | 伴野 文亮 | |
| 「鹿児島県霧島市溝辺町高屋山上陵 立会調査見学」参加記 | 近沢 恒典 | |
| 展示批評 | ||
| 石川町立歴史民俗資料館(イシニクル)の移転リニューアルオープン |
山田 英明 | |
| 研究例会報告要旨 | ||
| 地方史研究協議会第73回(館林)大会の成果と課題 | 鬼塚 知典 | |
| “川合”と「里沼」の地域像 -館林大会を振り返って- | 近藤 聖弥 | |
| 福山藩における『諸国風俗問状』回答事業 | 堀内 誠司 | |
| 地方史の窓/新刊案内/受贈図書論文要目 | ||
| 能登からのおたより | ||
| 声明 内閣府特命担当大臣決定「日本学術会議の法人化に向けて」(2023.12.22)の撤回を求め、日本学術会議の法人化に強く反対する声明 | ||
| 第429号(74-3)(2024.06) | ||
| A5/126p 1143円(税別) | ||
| 軍事的視点から見る近世前期の蝦夷地の「国外」性 -寛文蝦夷蜂起を素材として- |
久保田正志 | |
| 日露戦後期の町村請願運動 -「戦捷紀念」市町村基本金下付請願運動の展開過程- |
石坂 桜 | |
| 文久三年における加藤有隣の政治的位置 -長州藩の国事周旋運動との関連性に着目して- |
赤井 誠 | |
| 第65回日本史関係卒業論文発表会要旨 | ||
| 1 律令上京力役制度の成立 | 赤松龍之介 | |
| 2 平安期における宋商人の対日交易と東アジア海域 | 北村 友唯 | |
| 3 鎌倉街道上道と熊野修験 | 志村 奏恵 | |
| 4 古河公方官途授与の基礎的考察 | 三栗谷凜大 | |
| 5 永正年間における阿蘇大宮司家の社領支配 | 岩﨑 大知 | 6 足利的秩序の崩壊と三好氏の位置付け | 舩嵜 勇人 |
| 7 中世商人の展開と装束 | 泉 知里 | |
| 8 戦国期肥前国における勧進聖の存在形態 | 青木 英輔 | |
| 9 戦国期における江戸の発展 | 町田 敦秀 | |
| 10 徳川秀忠発給文書の基礎的研究 | 竹村 拓磨 | |
| 11 茶人古田織部の死生観について | 横井 蒼大 | |
| 12 徳川綱吉時代における「側用人」と将軍専制権力について | 伊藤菜月子 | |
| 13 近世における将軍正妻の政治的影響力 | 加藤菜穂子 | |
| 14 禁裏外部での活動からみる近世非蔵人 | 山本 遥大 | |
| 15 象洞の活用から見た享保期の疫病政策 | 田中 裕太 | |
| 16 福岡藩における燃料政策の展開 | 大庭 夕佳 | |
| 17 近世領知宛行制度の研究 | 関 恵正 | 18 近世後期における江戸町火消の怪我と補償 | 澤田 陸斗 |
| 19 群馬と埼玉の民権結社の比較検討 | 田中 翔也 | |
| 20 明治期における菓子業界の形成 | 鳥羽 菜月 | |
| 21 農村地域における小規模経営鉄道の展開 | 戸倉 希実 | |
| 22 富士裾野演習場における地元住民と陸軍の関係 | 山崎 紫音 | |
| 23 一九一〇年代における福岡市政と上水道布設事業 | 田代 恵悟 | |
| 24 大正期のアジア主義に関する考察 | 小谷 啓人 | |
| 25 なぜ「移民」を送り出したのか | 城山菜々子 | |
| 26 婦人雑誌に見る生活改善の実態 | 秋本萌乃加 | |
| 27 資生堂と戦時下の女性像 | 細島 瑠花 | |
| 28 身体からみた終戦前後の音楽実践 | 宮城 幸太 | |
| 動向 | ||
| 能登半島地震の被災状況と資料レスキュー活動 | 寺口 学 | |
| 「令和五年度 東日本大震災アーカイブシンポジウム -震災遺産と地域文化の継承を目指して-」に参加して | 川上 真理 | |
| 群馬県文化財防災ネットワーク連携協議会設立記念講演会参加記 | 須藤 聡 | |
| 全史料協全国(東京)大会に参加して | 山田 之恵 | |
| 「塚穴古墳(来目皇子墓)事前調査に伴う見学会」参加記 | 片山 正彦 | |
| 展示批評 | ||
| 郡山市歴史資料館 令和五年度企画展 「『廻米』-守山藩・二本松藩の事例-」 |
小松 賢司 | |
| 研究例会報告要旨 | ||
| 菅江真澄の旅 -<自然と人間の生活誌>としての- | 佐々木隼相 | |
| 鹽竈神社の知のネットワーク | 城所 喬男 | |
| 地方史の窓/新刊案内/受贈図書論文要目 | ||
| 第428号(74-2)(2024.04) | ||
| A5/174p 1143円(税別) | ||
| 近代初頭における河川流通秩序の変容 ―新河岸川流域を事例に― |
西口 正隆 | |
| 特集 変わる、歴史教育の現場 ―地域資料への向き合い方― | ||
| 1 身近な地域の歴史学習を通して、地域の未来を構想する力(持続可能な社会を形成する力)を育てる研究 | 川名 洋右 | |
| 2 身近な地域史を活用した「歴史総合」の授業 ―埼玉県東部地域の鉄道事業を題材に― |
山田 篤史 | |
| 3 資料と対話し、時代を再考する歴史学習 | 岩本 和恵 | |
| 4 日本史授業及び部活動における郷土史資料の活用 ―岐阜県立関高等学校の実践事例― |
林 直樹 岩田拓弥 |
|
| 5 「探究」を軸とした「地域から世界史へ」の授業実践 | 内山 博貴 | 6 カリキュラム・マネジメントの視点に立った「総合的な探究の時間」の効果的学習方法について ─近代地方新聞を用いた学習を通して─ |
熊谷 隆次 |
| 7 長崎県立壱岐高等学校東アジア歴史・中国語コースにおける地方の歴史との関わり方 | 長岡 康孝 | |
| 8 地域資料を活かした学校現場での取り組み ―休館中の学校向け教育・普及事業を通して― |
村上 聡 | |
| 9 やっぱり博物館が好き ―学校は地域資料とどう向き合ってきたか― |
神山 知徳 | |
| 10 徳島県立鳥居龍蔵記念博物館における中学生、高校生の研究支援活動について ―二つのフォーラムをめぐって― |
小林 篤正 | |
| 11 沖縄で「歴史学と歴史教育の両立」を問う | 武井 弘一 | |
| 12 地方史研究協議会と歴史教育 ―会誌『地方史研究』のあゆみと共に― |
風間 洋 | |
| 動向 | ||
| 第43回群馬学連続シンポジウム 「関東徳川史観と『天正十八年問題』」に参加して |
山田あづさ | |
| 第71回全国博物館大会参加記 | 佐藤 有 | |
| 展示批評 | ||
| こおりやま文学の森資料館 特別企画展 没後80年「石井研堂」 | 荒川 瑛楠 | |
| 松戸市立博物館 企画展 「あの日の〝まつど〟―写真でふりかえる一五〇年―」 |
大沼 大晟 | |
| 書評 | ||
| 地方史研究協議会編 シリーズ地方史はおもしろい05 『日本の歴史を突き詰める―おおさかの歴史』 | 林 晃之介 | |
| 研究例会報告要旨 | ||
| 足立区における地域美術史の展開 ―江戸東郊地域の美術文化の一例として― |
小林 優 | |
| 地方史の窓/新刊案内/受贈図書論文要目 | ||
| 第427号(74-1)(2024.02) | ||
| A5/182p 1143円(税別) | ||
| 近世大嘗祭と村落社会 -斎田抜穂の儀の再検討を通じて- |
各務 諒 | |
| 丹比連と丹比公 -丹比地域の氏族と王権との関係- |
上遠野浩一 | |
| <小特集 地域資料の保存と活用-大分から考える> | 三野 行徳 | |
| 大分県記録史料調査事業とデジタルアーカイブの活用 | 松尾 大輝 | |
| 学校資料の散逸を防ぐために -「アーカイブズ教育」と学校資料保存の道筋- | 平井 義人 | |
| 地域における資料の保存と活用 -近年の地方史研究協議会の活動に沿って- |
保垣 孝幸 | |
| 「地域資料の保存と活用-大分から考える-」に参加して | 松原 勝也 | |
| 2023年度(第73回)地方史研究協議会館林大会・総会報告 | 2023年度(第73回)地方史研究協議会館林大会 参加記 | 大貫茂紀/ 大野秀彰/ 升川繁敏/ 矢嶋翔/ 渡邉歩/ 鈴木萌花/ 森正太郎 |
| 動向 | ||
| 日本歴史学協会報告 | 桑原 功一 | |
| 存廃の危機に瀕する豊後日出藩木下氏の御茶屋襟江亭の今 | 平井 義人 | |
| 日本歴史学協会第28回資料保存利用問題シンポジウム 「コロナ感染症をめぐる記録と記憶―何を、誰が、どう残すか―」に参加して | 三野 行徳 | |
| 第18回シンポジウム 歴史教科書・いままでとこれから 新科目「歴史総合」「日本史探究」「世界史探究」と歴史教育の課題PART2参加記 | 野本 禎司 | |
| 念仏寺山古墳(開化天皇陵)外構柵整備工事に伴う立会調査見学参加記 | 太田 宏明 | |
| 展示批評 | ||
| 日出町歴史資料館・日出町帆足萬里記念館 特集展「ひじの少年少女、まちの近代-学校日誌にみえてくる時代-」 |
須永 敬 | |
| 三井記念美術館・岡崎市美術博物館・静岡市美術館 NHK大河ドラマ特別展「どうする家康」を観覧して | 杉本 竜 | |
| 書評 | ||
| 地方史研究協議会編 『「非常時」の記録保存と記憶化―戦争・災害・感染症と地域社会』 | 堀野 周平 | |
| 研究例会報告要旨 | ||
| 中近世移行期における婚姻ネットワークと由緒 -両毛地域を中心に- |
青木 裕美 | |
| 地方史の窓/新刊案内/受贈図書論文要目 | ||
| 第426号(73-6)(2023.12) | ||
| A5/176p 1143円(税別) | ||
| 松平忠直豊後配流の影響 -寛永元年の忠直領往来禁止令から- |
入江 康太 | |
| 表背墨書から辿る仏画の保存継承 -醍醐寺座主高演の事績を中心として- |
田中 直子 | |
| 特集 コロナ禍の地方史研究を振り返る -日常と挑戦から見えてきたもの- |
||
| コロナ禍の日々と疫病史研究 | 菊池 勇夫 | |
| コロナ禍における地方大学での研究教育活動 | 小松 賢司 | |
| コロナ禍の常陸大宮市文書館の業務運営 | 高村 恵美 | |
| コロナ禍における自治体史の編集と執筆 -東京都立川市史と長野県栄村誌を事例として- |
高野 宏峰 | |
| コロナ禍の研究活動を振り返って -コロナ後へ向けて今私ができること- |
村上 博美 | |
| コロナ禍における研究活動 -学生の立場から- |
堀内 誠司 | コロナ禍の学生生活と研究 | 岸野 達也 |
| コロナ禍と高校教育 -オンライン対応の実情を中心に- |
北村 拓 | |
| コロナ禍の中学・高校歴史教育 | 近藤 剛 | |
| コロナ禍における社会科系部活動 | 中西 崇 | |
| コロナ禍での三重大会と写真資料の可能性 | 藤谷 彰 | |
| コロナ禍における歴史博物館の教育普及活動 -島根県立古代出雲歴史博物館の事例より- |
伊藤 大貴 | |
| コロナ禍発生後の愛媛県における資料保全活動について | 胡 光 | |
| コロナ禍の地域史料の公開と保存 -都城島津邸所蔵史料デジタル化の取り組み- |
山下 真一 | |
| コロナ禍の地方史研究協議会の活動を振返って(3) -Withコロナ時代の地方史活動- |
鎮目 良文 | |
| 動向 | ||
| 第10回四国地域史研究連絡協議会大会参加記 | 芝野 有純 | |
| 展示批評 | ||
| 兵庫県立歴史博物館の常設展示紹介 -「ひょうご五国のあゆみ」を中心に- |
新宮 由真 | |
| 「河野広中没後一〇〇年記念展」(福島県三春町、石川町)を拝観して | 飯塚 彬 | |
| 研究例会報告要旨 | ||
| 須賀川町の教育 ー郷学舎「敷教第二舎」と須賀川医学校についてー | 宮澤 里奈 | |
| 学校給食の歴史的経緯と特色 -山形県置賜地方の小学校に着目して- |
中川 恵 | |
| 戦後の地方における短期大学の教員養成の意義 -米沢女子短期大学の卒業生を対象として- |
村瀬 桃子 | |
| 江戸・東京東郊農村の寺社と地域 | 大関 直人 | |
| 地方史の窓/新刊案内/受贈図書論文要目 | ||
| 第425号(73-5)(2023.10) | ||
| A5/152p 1143円(税別) | ||
| <大会特集Ⅱ 〝川合〟と「里沼」―利根川・渡良瀬川合流域の歴史像> | ||
| 問題提起(続) | ||
| 18 利根川・渡良瀬川合流域の中世荘園に関する一考察 ―在地武士・地方寺院からみる― | 野口 華世 | |
| 19 近世後期、渡良瀬川流域の鷹捉飼塲 ―野廻り役「御鷹御用日記」を読む― |
巻島 隆 | |
| 20 近代における〝川合〟の物流 | 渡辺 嘉之 | |
| 21 近現代の館林織物業の展開にみる研究課題 | 鈴木 理彦 | |
| 22 近代以降の文芸作品にみえる〝川合〟・「里沼」 | 井坂 優斗 | 23 館林・邑楽郡における弁財天信仰と道祖神信仰について | 鈴木耕太郎 |
| 24 日本遺産「里沼」の認定と館林の地域特色 | 岡屋 紀子 | |
| 第一次企業勃興期における田口卯吉の経済思想 -両毛鉄道会社創立事業をめぐって- |
山本 祐麻 | |
| 長州戦争における物資調達 -長州領内兵粮米を中心に- |
柳澤 京子 | |
| 動向 | ||
| 群馬県地域文化研究協議会研究大会 参加記 | 深澤 敦仁 | |
| 高崎経済大学図書館 地方史研究協議会受贈図書の活用 | 長谷川明則 | |
| 長楽寺永禄日記勉強会と「瀬端」の景観 | 簗瀬 大輔 | |
| 「門徒久敷断絶す―三河一向一揆後の三河本願寺教団と家康・秀吉―」 基調報告に参加して |
角 衣利奈 | |
| 展示批評 | ||
| 館林市立資料館収蔵資料展「いくさと備え」 | 長谷川幸一 | |
| 京都市歴史資料館「文化庁移転記念特別展 八瀬の歴史をまもり、伝える」 | 宮田 直樹 | |
| 施設紹介 | ||
| NPO法人 足尾鉱毒事件田中正造記念館 活動紹介 | 針ヶ谷照夫 | |
| 地域共創の拠点としての「カルピス」みらいのミュージアム | 西村 衛 | |
| 正田醤油「正田記念館」とその時代 | 斎藤 隆 | |
| 日清製粉グループにおける「館林」と「製粉ミュージアム」について | 町田 英樹 | |
| 書評 | ||
| 地方史研究協議会第71回(茨城)大会成果論集 『海洋・内海・河川の地域史―茨城の史的空間』 |
阿部 裕樹 | |
| 研究例会報告要旨 | ||
| 参勤交代制度と大名家臣団-鳥取藩を事例に- | 仲泉 剛 | |
| 地方史の窓/新刊案内/受贈図書論文要目 | ||
| 第424号(73-4)(2023.08) | ||
| A5/148p 1143円(税別) | ||
| <大会特集Ⅰ 〝川合〟と「里沼」―利根川・渡良瀬川合流域の歴史像> | ||
| 問題提起 | ||
| 1 関東平野の中の〝川合〟と「里沼」 | 澤口 宏 | |
| 2 縄文時代の遺跡分布と〝川合〟 | 宮田 圭祐 | |
| 3 赤岩堂山古墳と光恩寺の意義について | 足立 佳代 | |
| 4 館林市陣谷遺跡から読み解く古代の土地利用と景観 | 関口 博幸 | |
| 5 多々良沼とたたら製鉄跡 | 市橋 一郎 | 6 「鶏足寺世代血脈」の地域史料としての可能性 | 近藤 聖弥 |
| 7 戦国期における沼の機能 | 新井 浩文 | |
| 8 〝川合〟地域の沼城の特性 | 飯森 康広 | |
| 9 〝川合〟地域と古河公方 | 藤田 慧 | |
| 10 〝川合〟の関所と通船改 | 竹内 励 | |
| 11 日光脇往還館林宿の機能と周辺助郷村 | 秋山 寛行 | |
| 12 〝川合〟地域における政治領域の形成とその地域性 | 川名 禎 | |
| 13 〝川合〟における水害と館林藩の対応 | 宮坂 新 | |
| 14 利根川・渡良瀬川合流域における自然環境と土地利用 | 関戸 明子 | |
| 15 群馬県東部、邑楽・館林地域における米と麦の食文化 | 横田 雅博 | |
| 16 川魚食は残った | 内田 幸彦 | |
| 17 渡良瀬川の大水と水塚・揚げ舟 | 板橋 春夫 | |
| 第64回 日本史関係卒業論文発表会 | ||
| 特別講座 共同研究の醍醐味 | 浅倉 有子 | |
| 参加記 | 川田大 金井遥 篠原杏奈 小松和史 鈴木紀輝 土田宏成 森高恵史 |
|
| 動向 | ||
| ぐんま地域文化遺産フォーラム2022 | ||
| 「みぢかな歴史のつむぎかた―自治体史編纂へ向けた大字誌の可能性―」に参加して | 作間 亮哉 | |
| 京都府高倉天皇陵斜面地崩落復旧工事に伴う立会調査見学参加記 | 斉藤 進 | |
| 日本博物館協会主催フォーラム | ||
| 「改正博物館法施行間近!~現場の視点で改正法のポイントを考える~」参加記 | 尾崎 泰弘 | |
| 改正博物館法アンケートの実施について | 地方史研究協議会博物館・ 資料館問題検討委員会 |
|
| 展示批評 | ||
| 展示キャプションは「どうする?」べきか | ||
| 桑名市博物館特別企画展「こうなる徳川将軍家 家康と千姫」を観覧して | 湯谷 翔悟 | |
| 神奈川県立歴史博物館特別陳列 | ||
| 「松平造酒助江戸在勤日記―武士の絵日記―」 | 仲泉 剛 | |
| 栃木県立美術館開館50周年記念 令和4年度企画展 | ||
| 「「二つの栃木」の架け橋 小口一郎展 足尾鉱毒事件を描く」 | 井坂 優斗 | |
| 研究例会報告要旨 | ||
| 三重大会を振り返って | 谷戸 佑紀 | |
| 三重大会の成果と課題 | 荒木 仁朗 | |
| 三重大会総括例会に参加して | 川端 蒼海 | |
| 地方史の窓/新刊案内/受贈図書論文要目 | ||
| 第423号(73-3)(2023.06) | ||
| A5/120p 1143円(税別) | ||
| 昭和期長野県下における地域の防空組織と在郷軍人 -上伊那郡南向村を事例に- |
安 裕太郎 | |
| 明治後期から大正前期の東葛飾郡における機械排水 -明治農法に依拠しない土地生産性の向上- |
太田 知宏 | |
| 第64回日本史関係卒業論文発表会要旨 | ||
| 1 日本古代儀礼・祭祀の諸相と変遷 -古代「神道」における神仏隔離の意義- |
青山 大悟 | |
| 2 九世紀から一二世紀における采女と諸国 -国単位の貢進・出身地による資養を通じて- |
薄 麻里奈 | |
| 3 狩倉再考 | 石井 伸明 | |
| 4「豊前宇都宮氏」の政治的動向 -都鄙の連関に着目して- |
進 竜一郎 | |
| 5 鎌倉後期幕府訴訟における「召文違背の咎」 | 小松原瑞基 | |
| 6 南北朝期石見国の合戦と地域 | 金子 初音 | |
| 7 陸奥国高野郡の交通と白河結城氏・山伏 | 末武 宏太 | |
| 8 戦国・近世初期における軍事編成と兵糧調達 | 平田 真司 | |
| 9 江戸時代中期における浅草寺での行き倒れの実態とその医療・福祉支援について | 樋口 葵 | |
| 10 鳥取藩「家老日記」から見る初期藩政の確立について -藩主権力との関係に着目して- |
窪田 絢乃 | |
| 11 近世大名の「死」と家中 -津山藩松平家の葬送- |
小幡 哲央 | |
| 12 大名勤役と江戸幕府制度 -大名門番役を中心として- |
山田 瑛斗 | |
| 13 近世後期武家社会における小笠原平兵衛家 -溶姫婚礼を素材として- |
山田 拓実 | |
| 14 近世後期における村掟と若者議定のかかわりについて -相模国大住郡を事例として- |
草山 菜摘 | |
| 15 レザノフ来航からみる日魯交渉における一考察 -「魯西亜滞船中日記」を中心に- |
前田 公平 | |
| 16 明治初年における徳大寺実則の政治的位置 | 大内 駿人 | |
| 17 機密漏洩問題における新聞統制方針の変化 -明治一〇年代での移行と結末- |
那波 宏哉 | |
| 18 明治期町村制下の「公民」にみられる民権と大衆の相剋 -東京府南多摩郡稲城村の青年の動向を中心に- |
前島 奉行 | |
| 19 原胤昭の東京出獄人保護所から見る近代日本の更生保護事業 | 佐藤 愛華 | |
| 20 明治末期から大正初期にかけての北洋漁業 | 山本 駿太 | |
| 21 有田外交期における日中交渉と対中政策の転換 -川越茂・張群会談の分析を通して- |
市岡 広大 | |
| 22 終戦期の重要地点防衛 | 井川 蓮音 | |
| 23 沖縄戦におけるアメリカ軍対日宣伝ビラ -沖縄研究の反映とその影響- |
海野 貴之 | |
| 24 傷痍軍人の妻が生きた二〇世紀の日本社会 | 村上 詩歩 | |
| 25「精神薄弱者福祉法」の成立過程 | 佐藤 夢来 | |
| 26 戦友会史料の調査と分析 -巡洋艦「阿賀野」戦友会を例として- |
宮島 凜 | |
| 27 継承と変革のNHK戦争ドキュメンタリー -『映像の世紀』シリーズを中心に- |
安藤 優衣 | |
| 動向 | ||
| 誉田御廟山古墳立入観察参加記 | 小林 丈広 | |
| 「市庭古墳(平城天皇・楊梅陵)コンクリートブロック塀改修その他工事に伴う立会調査見学」参加記 | 鬼塚 知典 | |
| 展示批評 | ||
| 松田町生涯学習センター特別展示 「松田城-古文書・出土遺物から迫る-」の展示と資料整理事業 |
草山 菜摘 | |
| 水戸市立博物館 特別展「那珂川ヒストリー-水と共に生きた人々-」 | 菅野 洋介 | |
| 行田市郷土博物館開館35周年記念 第35回企画展 「天正十八年~関東の戦国から近世~」 |
簗瀬 大輔 | |
| 地方史、私の履歴書 私の香川地域史研究 | 木原 溥幸 | |
| 地方史の窓/新刊案内/受贈図書論文要目 | ||
| 第422号(73-2)(2023.04) | ||
| A5/122p 1143円(税別) | ||
| 戦国期における佐竹氏の一字授与について | 安達 和人 | |
| 細川氏同族連合体制と阿波光勝院 -頼之の光勝院移転を中心として- |
福家 清司 | |
| 百姓一揆後の村と費用負担 -文化六年信州飯田紙問屋騒動を事例に- |
林 進一郎 | |
| 動向 | ||
| 歴史教育シンポジウム: 歴史総合をめぐって(6)「「歴史総合」の教科書と授業を検討する」参加記 |
山田 篤史 | |
| シンポジウム「軍事・戦争遺跡を未来に生かす道」に参加して | 栗原 健一 | |
| 「畝傍陵墓監区事務所建替工事予定区域限定公開」参加記 | 鬼塚 知典 | |
| 小豆島石のシンポジウム2023 「日本遺産の石の島、新たな発見と保存をめざして!」に参加して |
堀之内照幸 | |
| 展示批評 | ||
| 鶴岡市郷土資料館「酒井家入部400年記念企画展 庄内藩江戸市中取締展~庄内藩士松平造酒助がみた幕末の江戸~」 |
原 淳一郎 | |
| 千葉市立郷土博物館令和四年度企画展示 「甘藷先生の置き土産~青木昆陽と千葉のさつまいも~」 |
猪野映里子 | |
| 研究例会報告要旨 | ||
| 書評 小田原近世史研究会編『近世地域史研究の模索』 | 松本 和明 | |
| 地域史研究への構え -「つながり」論を企画するうえで考えたこと- |
早田 旅人 | |
| 論集『近世地域史研究の模索』書評会参加記 | 三宅 真人 | |
| 地方史、私の履歴書 地域史料を渉猟して |
丑木 幸男 | |
| 地方史の窓/新刊案内/受贈図書論文要目 | ||
| 要望書 国立国会図書館デジタルコレクションの著作権処理の改善による知識情報基盤の拡充を求めます | ||
| 第421号(73-1)(2023.02) | ||
| A5/144p 1143円(税別) | ||
| 足利義教政権と石見守護山名氏 | 伊藤 大貴 | |
| 織田信長家臣堀秀政の実像 | 田嶋 悠佑 | |
| 小特集 第62回庄内大会から10年 ―その後の成果と課題― | ||
| 日本憲法史としてのワッパ騒動 ―庄内から東京へ、そして未来へ― |
長沼 秀明 | |
| 庄内藩の財政難 | 本間 勝喜 | |
| 第62回(庄内)大会から10年後の庄内地域の郷土史の動向 | 今野 章 | |
| 致道博物館の酒井家庄内入部四〇〇年記念事業 | 菅原 義勝 | 地方史はおもしろい№3『日本の歴史を問いかける ―山形県〈庄内〉からの挑戦』 出版までの経緯について |
大嶌 聖子 |
| 参加記 長沼報告と鶴岡への思い | 野口 周一 | |
| 参加記 「第62回庄内大会から10年 ―その後の成果と課題―」に参加して |
林 幸太郎 | |
| 第72回(三重)大会参加記 | 大澤誠 手倉森結南 長谷川明則 小嶋圭 井坂優斗 春名紘彰 |
|
| 動向 | ||
| 日本歴史学協会報告 | 桑原 功一 | |
| 第17回シンポジウム 歴史教科書・いままでとこれから 新科目「歴史総合」「日本史探究」「世界史探究」と歴史教育の課題 参加記 |
風間 洋 | |
| 全史料協滋賀大会に参加して | 佐藤 明俊 | |
| 展示批評 | ||
| 春日部市郷土資料館×宮内庁宮内公文書館 企画展示「明治天皇と春日部~巡幸・御猟場・梅田ごぼう~」 |
牛米 努 | |
| 熊本県博物館ネットワークセンター企画展「昔のお金と今のお金」 | 森 正太郎 | |
| さいたま市岩槻人形博物館 特集展示「郷土玩具―おまもり・えんぎもの」 | 荒川 瑛楠 | |
| 横山昭男先生の訃報 | ||
| 地方史の窓/新刊案内/受贈図書論文要目 | ||
| 第420号(72-6)(2022.12) | ||
| A5/130p 1143円(税別) | ||
| 武田氏と西上野小幡氏の出張軍役 -永禄11年~天正3年の小幡氏宗家を事例に- |
恩田 登 | |
| <小特集 展示批評> | ||
| 佐藤孝之氏インタビュー | ||
| 展示批評掲載号一覧 | ||
| 展示批評 | ||
| 石巻市博物館 常設展 「大河と海に育まれた石巻」 |
渋谷 洋祐 | |
| 葛飾区郷土と天文の博物館 リニューアルされたかつしかの郷土史 |
栁沼由可子 | |
| 厚木市立あつぎ郷土博物館 「基本展示」「融合展示」を見学して |
山下 春菜 | 十日町市博物館 常設展示を見学して | 小酒井大悟 |
| 徳島県立博物館 リニューアルによせて | 胡 光 | |
| 延岡城・内藤記念博物館 平常展示室の展示について |
中嶋 愛 | |
| 高岡の森弘前藩歴史館 自館紹介:施設概要と常設展示 |
澁谷 悠子 | |
| 尼崎市立歴史博物館 自館紹介:常設展示について |
楞野 一裕 | |
| 研究例会報告要旨 | ||
| 幕末会津藩の蝦夷地政策について | 佐藤 愛未 | |
| 明治19年の福島県東蒲原郡の新潟県移管について | 山田 英明 | |
| 地方史、私の履歴書 わたしの歩み | 門前 博之 | |
| 地方史の窓/新刊案内/受贈図書論文要目 | ||
| 第419号(72-5)(2022.10) | ||
| A5/150p 1143円(税別) | ||
| <大会特集Ⅱ 〝出入り〟の地域史 ―求心・醸成・発信からみる三重―> | ||
| 問題提起 | ||
| 20 戦国期伊勢国の「徳政」とその研究視角 ―地域社会論的観点からの展望― |
水林 純 | |
| 21 紀州藩の狩猟と伊勢国鷹場 | 飯場 大輔 | |
| 22 近世後期における俳人たちの交流 ―人名録・番付に見る伊賀俳人― |
伊藤 善隆 | |
| 23 飯高郡柳瀬家と茶業の関わり ―「柳瀬家文書」について― |
雨宮 智花 | |
| 24 伊勢桑名の刀工・村正に関する〝出入り〟 ―地域博物館の求心・醸成・発信― |
杉本 竜 | 25 近代における芸能者と移動 | 黛 友明 |
| 26 富士山信仰と「伊勢」 ―富士山行者、食行身禄・禄行三志との関連を中心に― |
吉田 政博 | |
| 動向 | ||
| 三重郷土会 創立七五周年を迎えて | 浅生 悦生 | |
| 三重県の地方史関連雑誌素描 | 太田 光俊 | |
| 山形県地域史研究協議会参加記 | 鈴木 駿兵 | |
| 第27回史料保存利用問題シンポジウム 「アーカイブズ専門職問題の新潮流」参加記 |
藤 隆宏 | |
| 展示批評 | ||
| 石巻市博物館テーマ展「奥羽仕置と石巻」 | 江田 郁夫 | |
| 土浦市立博物館 第43回特別展 「八田知家と名門常陸小田氏 鎌倉殿御家人に始まる武家の歴史」 |
森田 忠治 | |
| 稲敷市立歴史民俗資料館特別展 「常州江戸崎不動院 天海、ここに顕現す!」を見学して |
西口 正隆 | |
| 研究例会報告要旨 | ||
| 江戸東京の里神楽の実態解明を目指して | 亀川 泰照 | |
| 三井越後屋の太々神楽講と伊勢参宮 -一八-一九世紀御神楽執行記録の分析を中心に- |
五味 玲子 | |
| 地方史、私の履歴書 わたしの地方史研究遍歴 | 北崎 豊二 | |
| 地方史の窓/新刊案内/受贈図書論文要目 | ||
| 「改正博物館法に関するアンケート調査」の実施について | ||
| 第418号(72-4)(2022.08) | ||
| A5/150p 1143円(税別) | ||
| <大会特集Ⅰ 〝出入り〟の地域史 ―求心・醸成・発信からみる三重―> | ||
| 問題提起 | ||
| 1.伊勢と三重 | 遠藤 慶太 | |
| 2.斎宮と伊勢神宮をめぐる人とモノ | 榎村 寛之 | |
| 3.伊勢御師の淵源をめぐって | 岡野 友彦 | |
| 4.中近世移行期の石塔に見る受容・醸成・変容・発信 | 伊藤 裕偉 | |
| 5.慶長期における東海道七里の渡しとその周辺 | 伊藤 信吉 | 6.江戸時代初頭における奉行制の問題点 | 梅田 優歩 |
| 7.山田奉行の代参 | 谷戸 佑紀 | |
| 8.津藩の城下町研究と史料 | 齋藤 隼人 | |
| 9.文政六年桑名藩の転封と町方の動向 | 藤谷 彰 | |
| 10.伊勢書肆藤原長兵衛と三都出版界との交流 | 速水 香織 | |
| 11.伊勢商人による蒐書とその意義 | 桐田 貴史 | |
| 12.長谷川次郎兵衛家と裏千家 | 扇野 耕多 | |
| 13.幕末期神宮史研究について | 安部 玄将 | |
| 14.明治維新期の伊勢参宮 | 谷口 裕信 | |
| 15.郵便資料から見る伊勢型紙の近代 | 代田 美里 | |
| 16.海女の移動と出稼ぎ | 縣 拓也 | |
| 17.四日市公害の歴史と教訓 | 小池真理子 | |
| 18.三重県域の自治体史誌編さん事業史をめぐる〝出入り〟 | 鴨頭 俊宏 | |
| 19.御頭神事への研究視座に関する一提起 | 味噌井拓志 | |
| 第63回日本史関係卒業論文発表会特別講座 | ||
| 職業としての学芸員 | 寺門 雄一 | |
| 第63回日本史関係卒業論文発表会参加記 | 田中皓大/ 宮野純光/ 中村昂希/ 森田香司/ 武田真幸/ 伊藤静香/ 小杉勇人/ 鈴木葵/ 髙山慶子/ 芦田寿子/ 矢嶋毅之 |
|
| 動向 | ||
| 「高輪築堤」の保存と今後の動向 -「シンポジウム~高輪築堤を考える~」に寄せて- |
学術体制小委員会 | |
| シンポジウム「歴史が導く災害科学の新展開Ⅴ ―文理融合による1611年慶長奥州地震津波の 研究―」参加記 |
岡崎 佑也 | |
| 日本アーカイブズ学会大会参加記 | 北浦 康孝 | |
| 展示批評 | ||
| 致道博物館「酒井家庄内入部400年記念特別展【第一部】徳川四天王筆頭 酒井忠次」 | 山下 葵 | |
| 研究例会報告要旨 | ||
| 山中共古の武蔵野研究 | 波田 尚大 | |
| 近世在方市の風景 -飯能縄市を中心に- | 尾崎 泰弘 | |
| 茨城大会をふりかえって -近世・近代を中心に- | 永井 博 | |
| 茨城大会の成果と課題 | 長谷川幸一 | |
| 地方史の窓/新刊案内/受贈図書論文要目 | ||
| 第417号(72-3)(2022.06) | ||
| A5/134p 1143円(税別) | ||
| 播磨国鵤荘における名体制 ―点定名に注目して― | 竹内 惇人 | |
| <小特集 コロナ禍の地方史研究―研究会の日常と挑戦―> | ||
| コロナ禍と研究会活動 ―模索と進化― | 永島 政彦 | |
| コロナ禍における首都圏形成史研究会の活動 | 西村健 松本洋幸 |
|
| コロナ禍における関東近世史研究会 | 武田 真幸 | |
| コロナ禍における小田原地方史研究会の活動 | 井上 弘 | |
| コロナ禍における静岡県地域史研究会の活動状況 | 厚地 淳司 | |
| コロナ禍と加能地域史研究 | 石田 文一 | コロナ禍の地域の歴史サークル | 長谷川澄夫 |
| コロナ禍の地方史研究 ―徳島地方史研究会の二年間― |
徳野 隆 | |
| 新型コロナに立ち向かう姿勢を常に持ち続けたい | 橋詰 茂 | |
| <第63回 日本史関係卒業論文発表会 要旨> | ||
| 正倉院文書に見える考課関係文書の検討 ―唐代文書との比較を中心に― |
陳 泓 錚 | |
| 律令国家による僧尼統制の特質と展開 | 市村 悠大 | |
| 流刑からみた中世国家 | 重村 つき | |
| 南北朝期安芸国における国人と守護武田氏 | 羽田 友生 | |
| 遠江国原田・村櫛荘の半済と半済給人 | 佐藤 公彦 | |
| 寺社統制から見る河野氏の地域支配 | 小泉 柚乃 | |
| 古河公方足利義氏の下総国小金への移座について ―その背景事情と政治史上の意義に関する一試論― |
吉田 勝弥 | |
| 中近世移行期の関東足利氏 -足利氏姫を中心に- | 岸野 達也 | |
| 近世初期の武家における男色の評価 | 松本 亮 | |
| 明和九年目黒行人坂大火の実態と幕府による罹災後の対処 | 東海林さくら | |
| 江戸時代後期における正月行事からみた庶民信仰 ―『諸国風俗問状答』を中心に― |
堀内 誠司 | |
| 近世後期の手習塾にみられる地域性 ―遠江国有玉下村の事例から― |
河野 七海 | |
| 近世後期信濃国高瀬川の川除普請 | 宮坂 和弥 | |
| 近世鎌倉仏師の活動に関する一考察 -相模国鎌倉郡扇ヶ谷村居住仏師を例に挙げて- |
鈴木 萌花 | |
| 幕府国産改所と関東八ヶ国絞油仲間の結成 | 石原 千尋 | |
| 宇都宮藩士の名字から見た家臣団構成の分析 ―幕末期の分限帳を中心に― |
冨金原拓馬 | |
| 新選組伊東甲子太郎の動向と国家構想 | 佐藤 友美 | |
| 旧会津藩における戊辰戦争戦死者慰霊・顕彰の変遷 ―旧藩士の変化と問題意識に注目して― | 尾崎紗耶香 | |
| 私擬憲法草案における民衆の通俗道徳思想に関する研究 ―五日市憲法草案の分析を基に― | 田中 雄大 | |
| 房総の自由民権運動 ―民権結社を中心に― | 佐藤 海斗 | |
| 明治期・陵墓治定過程における「旧藩士」と「旧藩意識」 ―旧対馬藩士による陵墓運動の事例を中心に― |
首藤 佳祐 | |
| 下野紡績所とその職工 | 見目 智菜 | |
| 日本陸軍における組織の研究 ―満洲事変時の対応を例として― |
進藤悠佳理 | |
| 戦後における天覧相撲に関する研究 | 石塚 皓生 | |
| 継承と変革の戦後少年誌 ―黎明期の『週刊少年マガジン』を中心に― |
李 天 雅 | |
| 動向 | ||
| 「第八回全国史料ネット研究交流集会」に参加して | 小嶋 圭 | |
| シンポジウム「大名華族家と地域社会」に参加して | 大沼 大晟 | |
| コロナ禍の地方史研究協議会の活動を振返って(2) ―感染状況長期化への覚悟― |
桑原 功一 | |
| 書評 | ||
| 地方史研究協議会編 シリーズ地方史はおもしろい04 『日本の歴史を描き直す―信越地域の歴史像』 | 藤野 敦 | |
| 研究例会報告要旨 | ||
| 熊本県博物館ネットワークセンターの取り組みとそこから見えた課題 | 堤 将太 | |
| 地方史の窓/新刊案内/受贈図書論文要目 | ||
| 第416号(72-2)(2022.04) | ||
| A5/134p 1143円(税別) | ||
| 東寺領摂津国垂水荘における「興行」について | 土山 祐之 | |
| 相良氏の天文14年 -天文前半期の肥後情勢と勅使下向- |
窪田 頌 | |
| 『ひたち帯』に見る元禄期常陸国の名所 | 猪岡 萌菜 | |
| 動向 | ||
| 三重県総合博物館(MieMu)における地域連携の取組 -市民活動・資料保全活動を中心に- |
山本 梨加 | |
| 「大山古墳(仁徳天皇百舌鳥耳原中陵)限定公開」参加記 | 鬼塚 知典 | |
| 日本学術会議公開シンポジウム:歴史教育シンポジウム 「「歴史総合」をめぐって-「歴史総合」の教科書をどう作ったか-」参加記 |
神田 基成 | |
| 第47回全史料協全国(高知)大会 「資料保存ネットワークの拡充とアーカイブズ-連携と支援、高知の挑戦-」参加記 |
村中 大樹 | |
| コロナ禍の地方史研究協議会の活動を振返って(1) -感染拡大への対応のはじまり- |
桑原 功一 | |
| 展示批評 | ||
| 郡山市歴史資料館 企画展「旧二本松藩士族と大槻原開墾~桑野村ものがたり~」 | 髙橋 直道 | |
| 神奈川県立歴史博物館?特別展 「開基五〇〇年記念 早雲寺-戦国大名北条氏の遺産と系譜-」 |
誉田航平 木本和志 |
|
| 宮崎県立西都原考古博物館 令和三年度国際交流展 「イノシシと人間~身近な“野生”との交渉史~」 |
鈴木 良幸 | |
| 書評 地方史研究協議会編?シリーズ地方史はおもしろい03 『日本の歴史を問いかける―山形県〈庄内〉からの挑戦』 |
伊藤 暢直 | |
| 研究例会報告要旨「近世における結城本郷の成立と在地興造」 | 川名 禎 | |
| 地方史の窓/新刊案内/受贈図書論文要目 | ||
| 第415号(72-1)(2022.02) | ||
| A5/152p 1143円(税別) | ||
| 内藤宗勝の丹後・若狭侵攻と逸見昌経の乱 | 馬部 隆弘 | |
| <小特集 シンポジウム:非常時の記録保存と記憶化を考える -コロナ禍の<いま>、地域社会をどう伝えるか-> |
||
| 福島県双葉町における震災資料の保全について | 吉野 高光 | |
| 地域に残された戦後社会事業史関係資料の価値 | 西村 健 | |
| 新型コロナウイルス感染症関係資料の収集について | 小畑 茂雄 | |
| 非常時に作成された公文書の移管 -千葉県文書館の場合- |
飯島 渉 | |
| 図書館は非常時の記録をどう生かせるか -「令和元年房総半島台風」に関する取組から- |
飯田 朋子 | |
| 参加記 | 武田 剛朗 | |
| 2021年度第71回(茨城)地方史研究協議会大会・総会報告 | ||
| 2021年度第71回(茨城)地方史研究協議会大会 参加記 |
小酒井大悟/ 西沢淳男/ 森田真一/ 小堤捺貴/ 出野雄也/ 磯本宏紀/ 道迫真吾/ 谷戸佑紀/ 関周一 |
|
| 動向 | ||
| 日本歴史学協会報告 | 新井 浩文 | |
| 向日市文化資料館 国際シンポジウム 「20世紀の和紙-寿岳文章 人と仕事」の参加記 |
家塚 智子 | |
| シンポジウム「公文書管理法後の自治体と文書管理」に参加して | 佐藤 愛未 | |
| 高校生が取り組む地域史研究 -歴史研究同好会の試み- |
桐生 海正 | |
| 第16回シンポジウム 歴史教科書・いままでとこれから 「新科目「歴史総合」と近現代史学習の課題」参加記 |
風間 洋 | |
| 展示批評 刈谷市歴史博物館 令和三年度 秋季企画展 「豊臣秀次-刈谷に新時代をもたらした関白殿下-」 |
水野 智之 | |
| 地方史の窓/新刊案内/受贈図書論文要目 | ||
| 第414号(71-6)(2021.12) | ||
| A5/146p 1143円(税別) | ||
| 白鳥健の思想と運動 -千葉県における初期社会主義と対外硬- |
跡部 史浩 | |
| 慣行専用漁業権下における反慣行の実践 -新潟県佐渡市柳沢のタコ漁場の事例から- |
新垣 夢乃 | |
| <小特集 東日本大震災これまでの10年、これからの10年-現場からの発信-> | ||
| 東日本大震災10周年雑感 -青森県から- | 中野渡一耕 | |
| 遠野から見た東日本大震災 -支援と被災の間で史料を守る- |
前川さおり | |
| 石巻文化センターにおける文化財レスキューのその後 | 泉田 邦彦 | |
| 宮城資料ネット 東日本大震災からの10年とこれから | 斎藤 善之 | |
| 「<敗北>の地域史」を越えて | 山田 英明 | |
| 3・11から10年のふくしまとこれから | 阿部 浩一 | |
| 被災地で考える地方史・地域史研究 -茨城での経験から- |
白井 哲哉 | |
| 地方自治体における文化財の災害復旧 -千葉県香取市の事例- |
川口 康 | |
| 動向 那須資料ネットの設立と博物館・行政 | 作間 亮哉 | |
| 展示批評 | ||
| 都城島津邸令和三年度特別展「神話にみえる都城」 | 籾木 郁朗 | |
| 埼玉県立歴史と民俗の博物館 NHK大河ドラマ特別展「青天を衝け~渋沢栄一のまなざし~」 |
浦木 賢治 | |
| 研究例会報告要旨 | ||
| 地域社会と<戦没者慰霊> -長野県南佐久郡の事例から- |
小池祐賀子 | |
| 地方史の窓/新刊案内/受贈図書論文要目 | ||
| 第413号(71-5)(2021.10) | ||
| A5/150p 1143円(税別) | ||
| <大会特集Ⅲ 海洋・内海・河川の地域史―茨城の史的空間―> | ||
| 内海世界の将門と貞盛 | 高橋 修 | |
| 下野国の百姓による常総内陸水運網拡充構想 -文化・文政年間における小貫万右衛門の奔走- | 平野 哲也 | |
| 水戸城の調査成果と歴史景観整備の現状 | 関口 慶久 | |
| 古霞ヶ浦の内海世界 古墳時代における水上交通の展開と地域社会の形成 | 塩谷 修 | |
| 施設紹介 | ||
| 複合施設の中の地域資料館 -真壁伝承館歴史資料館- |
寺崎 大貴 | |
| 常陸大宮市文書館の資料保全活動 | 髙橋 拓也 | |
| 水辺のムラの歴史と自然を伝える -東海村歴史と未来の交流館- |
林 恵子 | |
| 書評 | ||
| 地方史研究協議会編 『京都という地域文化:地方史研究協議会第70回(京都)大会成果論集』 |
杉森 哲也 | |
| 地方史研究協議会編 シリーズ 地方史はおもしろい01・02 『日本の歴史を解きほぐす―地域資料からの探求』 『日本の歴史を原点から探る―地域資料との出会い』 |
湯浅 隆 | |
| 研究例会報告要旨 | ||
| コロナ前後のデジタルミュージアム -大網白里市デジタル博物館の事例より- |
武田 剛朗 | |
| 今川氏と東三河の在地領主の関係 | 藤原 大志 | |
| 渋沢家における敬三の栄一観 -「祖父の後ろ姿」から見る- |
胡桃沢勘司 | |
| 地方史の窓/新刊案内/受贈図書論文要目 | ||
| 第412号(71-4)(2021.08) | ||
| A5/146p 1143円(税別) | ||
| 特集 コロナ禍の地方史研究、地方史研究者の日常と挑戦 | ||
| 八戸地方えんぶり調査事業と高校教育 -コロナ禍への対応- |
小林 力 熊谷隆次 |
|
| これからの古文書サークル活動 -コロナ禍の経験を踏まえて- |
高橋 陽一 | |
| コロナ期におけるとちぎ歴史資料ネットワークの設立 | 髙山 慶子 | |
| コロナ禍の博物館活動 -博物館の休館と展覧会- |
中村 陽平 | |
| コロナ禍における地方史・林政研究者によるオンライン授業の模索 | 芳賀 和樹 | |
| コロナ禍における東京都公文書館の取り組み | 工藤 航平 | |
| 「ウィズ・コロナ」社会の歴史資料保全と歴史研究 | 西村慎太郎 | |
| コロナ禍の日々-2020年8月頃までを振り返って- | 小林 丈広 | |
| 一歩前進、二歩後退 -コロナ禍に書き下ろし著書をつくってみて- |
小田 康徳 | |
| 新型コロナ禍における祭りと民俗芸能 | 須永 敬 | |
| 新型コロナウイルス感染症による影響と挑戦 -熊本県博物館ネットワークセンターの取り組みから- |
堤 将太 | |
| 近江鉄道架橋工事にみる公権力の役割 -「滋賀県特定歴史公文書」を通して- |
松岡 隆史 | |
| 第62回日本史関係卒業論文発表会参加記 | 藤木 海 田部井涼生 誉田航平 川田大晶 堀井美里 山中さゆり 古林直基 伊藤寛崇 森正太郎 |
|
| 第61回日本史関係卒業論文発表会参加記 | 鎌田直樹 和田 学 吉田大槻 須田華那 石澤夏巳 出口颯涼 |
|
| 動向 | ||
| 東日本大震災10年目に資料保全を考える -第7回全国史料ネット研究交流集会参加記- |
青野 誠 | |
| 展示批評 |
||
| 館山市立博物館令和2年度企画展「武士たちの明治」 |
山下 真一 |
|
| 山梨県立博物館開館15周年記念特別展「生誕500年 武田信玄の生涯」 | 小笠原春香 | |
| 地方史の窓/新刊案内/受贈図書論文要目 | ||
| 第411号(71-3)(2021.06) 品切れ | ||
| A5/112p 1143円(税別) | ||
| 関ヶ原合戦の布陣地に関する考察 | 小池絵千花 | |
| 神君伊賀越え後の伊勢湾渡海の実態について ―由緒書の検討を通して― |
山本 直孝 | |
| 彦根築城普請の着工年代について ―「年未詳木俣守勝宛て榊原康政書状」の年代比定を通して― |
永井 哲夫 | |
| 第62回日本史関係卒業論文発表会要旨 | ||
| 軒先瓦の出土傾向からみる下野国分二寺の造営過程 ―町谷瓦窯産軒先瓦の検討から― | 宇高美友子 | |
| 摂関期における地方裁判制度 | 河内 春樹 | |
| 足利義教の専制政治と守護家の内部要因からみた嘉吉の変 | 齋藤 莉瑚 | |
| 戦国期守護論の再検討 ―大内氏を例に― | 栗原 隼人 | |
| 戦国期京都における商人集団の展開 ―粟津供御人を中心に― |
谷本 隆之 | |
| 一五世紀の土倉と公方御倉 | 林 悠吾 | |
| 豊臣秀長文書の基礎的研究 | 鎌田 直樹 | |
| 近世武州秩父郡三峯山における生と死 ―近世の三峯神社運営組織と神領・修験の在り方― | 角田くるみ | |
| 江戸における名所の社会=空間とその受容 ―芝神明社を例として― |
須田 華那 | |
| 江戸周辺農村にみる水車稼ぎ ―三田用水流域の精米水車を事例に― |
小松 和史 | |
| 近世後期水運・陸運をめぐる地域社会 ―甲州三河岸を事例に― |
小泉 詩織 | |
| 近世後期伊豆国東浦地域における硫黄公害訴訟 | 藤田 勇祐 | |
| 幕末中央政局における徳川慶喜の政治構想 | 大澤 穂高 | |
| 埼玉県域における神仏分離とその影響 ―『新編武蔵風土記稿』と『武蔵国郡村誌』の比較と考察― |
小見 和也 | |
| 大衆とメディアが作り上げた西郷隆盛の英雄像 ―西南戦争錦絵を中心に― |
金澤 朋香 | |
| 明治前期のコレラ流行と防疫行政について ―神奈川県を事例として― |
瀬戸 優香 | |
| 田口卯吉の思想 ―「経済」論における「自治」と「貿易」― |
山本 祐麻 | |
| 農村「青年」の〈実像〉 ―大正デモクラシー期、信濃地域における普選運動及び自由大学運動を中心に― |
佐々木七美 | |
| 第一回普通選挙と仏教界 -伝統仏教と既成政党の動向を中心に- | 出口 颯涼 | |
| 市町村義務教育費国庫負担法から見る立憲政友会の義務教育政策 |
西田 幸平 | |
| 国策研究会の行政改革案と「近衛新体制」確立前後の動向 ―「官界新体制」をめぐる諸構想― |
山藤 舞香 | |
| 戦時下の大相撲力士たち | 津久井美花子 | |
| 占領下の各務原と鉄道輸送 | 岡安 琉伊 | |
| 動向 | ||
| 御廟野古墳(天智天皇陵)外構柵修繕工事に伴う立会調査見学会参加記 | 山本 雅和 | |
| 岡崎市美術博物館のコロナ禍対応 ―収蔵品展「贅沢な対話」の開催について― |
湯谷 翔悟 | |
| 安城市歴史博物館主催の第10回松平シンポジウムに参加して | 中島 学 | |
| 展示批評 | ||
| 千葉県立関宿城博物館企画展「関東のへそ ~地勢とくらしのヒストリー~」 |
新井 浩文 | |
| 野田市郷土博物館特別展「まちの記憶―写真でたどる野田・関宿の30→40年代―」 | 浪江 健雄 | |
| 地方史の窓/新刊案内/受贈図書論文要目 | ||
| 第410号(71-2)(2021.04) | ||
| A5/100p 1143円(税別) | ||
| 『風土記』における国譲り・天孫降臨神話について | 舟久保大輔 | |
| 中世前期の高野山膝下地域における在地領主の存在形態 -貴志氏を事例に- | 伊藤 哲平 | |
| 動向 | ||
| 日本歴史学協会報告 | 新井 浩文 | |
| 歴史教育シンポジウム「大学入試改革と歴史系科目の課題」参加記 |
風間 洋 | |
| 史料保存利用問題シンポジウム 「続発する大災害から史料を守る―現状と課題―」に参加して |
佐藤 麻里 |
|
| ウワナベ古墳(宇和奈辺陵墓参考地)限定公開参加記 | 鬼塚 知典 | |
| 要望書 『高輪築堤』遺構の保存・公開の要望/『高輪築堤』の保存を求める要望書 | ||
| 地方史の窓/受贈図書論文要目 | ||
| 第409号(71-1)(2021.02) | ||
| A5/118p 1143円(税別) | ||
| 豊臣政権期における南部信直の蔵入地支配について | 熊谷 隆次 | |
| 中世における前期赤松氏の軍事関係文書に関する基礎的考察 | 濱田浩一郎 | |
| 2020年度(第71回)地方史研究協議会大会の延期・総会(書面方式)報告 | ||
| 展示批評 | ||
| 流山市立博物館企画展「流山の災害史~史料は語る~」 | 小酒井大悟 | |
| 松戸市立博物館企画展「松戸と徳川将軍の御鹿狩」 | 山﨑 久登 | |
| 追想 竹内誠氏を偲んで | 久保田昌希 太田尚宏 保垣孝幸 北村行遠 奥田晴樹 松尾美惠子 廣瀬良弘 佐藤孝之 上野秀治 上條宏之 |
|
| 研究例会報告要旨(京都大会総括例会) | ||
| 『京都という地域文化』をどうとらえるか | 山田 徹 | |
| 京都大会の成果と課題(古代・中世) |
兼平 賢治 | |
| 京都大会の成果と課題(近世・近代) | 宮間 純一 | |
| 地方史の窓 新刊案内 受贈図書論文要目 | ||
| 第408号(70-6)(2020.12) | ||
| A5/83p 1143円(税別) | ||
| 永禄五年における能登・越中情勢の再検討 -『諸家文書纂』所収「温井景隆書状」をめぐって- |
石田 文一 | |
| 新潟大学附属図書館所蔵「保坂家文書」にみえる近世初期の越後根知城領支配 | 田嶋 悠佑 | |
| 動向 | ||
| 『旧真田山陸軍墓地、墓標との対話』出版記念シンポジウム 「死者と向き合ってみよう」参加記 |
実松 幸男 | |
| 全国歴史民俗系博物館協議会の令和元年度 関東ブロック集会(第八回)参加記 |
河野彩里 四戸菜穂 |
|
| コロナ禍における研究会の実施 -茨城地方史公開セミナーの事例- |
武子 裕美 | |
| 訃報 竹内誠 元会長の訃報 | 大石 学 | |
| 地方史の窓 新刊案内 受贈図書論文要目 | ||
| 第407号(70-5)(2020.10) | ||
| A5/122p 1143円(税別) | ||
| <大会特集Ⅱ 海洋・内海・河川の地域史―茨城の史的空間―> | ||
| 問題提起 | ||
| 列島の国家形成期における水上交通志向の社会と常総の内海世界 | 田中 裕 | |
| 河川の流域と新善光寺 -中世の常総国境地域を事例として- |
牛山 佳幸 | |
| 境目地域の平地城館と「用水管理」 | 藍原 怜 | |
| 下総型板碑の製作をめぐる一視点 | 伊藤 宏之 | |
| 寛永大日如来の祭祀から見る飯沼周辺地域の史的環境 | 山澤 学 | |
| 徳川光圀と法華宗 -本土寺と小西檀林- | 生駒 哲郎 | |
| 忘れられた常陸木食上人 -木食観海上人の宗教活動によせて- |
西海 賢二 | |
| 「尊皇」の背景 -水戸藩の地理的位置から- | 永井 博 | |
| 河川流域と河岸問屋の近代 | 飯塚 彬 | |
| 近代の土浦 -水辺の城下町から「空都」へ- |
野田 礼子 | |
| 中世における和市の復元研究 -播磨国矢野荘を事例として- |
小早川裕悟 | |
| 仙台藩廻米体制と穀宿 | 井上 拓巳 | |
| 動向 | ||
| デジタルミュージアムと地方史研究の関係性 -大網白里市デジタル博物館の事例より- |
武田 剛朗 | |
| 「歴史資料を活用した減災・気候変動適応に向けた新たな研究分野の創成」参加記 | 武子 裕美 | |
| 三〇周年を迎える徳島県立文書館 | 金原 祐樹 | |
| 茨城県下の地域資料の保存をめぐる現状と課題 | 添田 仁 | |
| 澤登寛聡先生の訃報 |
中山 学 | |
| 地方史の窓/新刊案内/受贈図書論文要目 | ||
| 第406号(70-4)(2020.08) | ||
| A5/132p 1143円(税別) | ||
| 第71回大会「海洋・内海・河川の地域史-茨城の史的空間-」問題提起 | ||
| 霞ヶ浦沿岸における縄文時代土器製塩研究の動向 | 亀井 翼 | |
| 太平洋沿岸の装飾古墳と横穴墓 -虎塚古墳と十五郎穴横穴墓群- |
稲田 健一 | |
| 日立市長者山遺跡と駅家推定遺跡尾に係る諸課題 | 猪狩 俊哉 | |
| 古代から中世へ-久慈郡・多珂郡の港- | 笹岡 明 | |
| 中世仏教と内海世界 -浄土真宗と真言律宗研究の展望- |
金子 千秋 | |
| 涸沼沿岸の城郭群と水運の拠点 | 五十嵐雄大 | |
| 中世「村松」の水辺景観 | 林 恵子 | |
| 古河公方足利成氏の動向と常総の内海・水系 | 石橋 一展 | |
| 戦国期佐竹氏と水運 | 山縣 創明 | |
| 戦国期佐竹氏権力と流通 -過所と荷留の事例から- |
泉田 邦彦 | |
| 近世水郷遊覧における旅人たちの舟運利用 | 長谷川良子 | |
| 水戸藩沿岸地域における海防強化態勢下の民衆の動向と地域意識 -会瀬村の事例から- | 千葉 椎奈 | |
| 明治期、茨城県産花崗岩の輸送と利用 -鉄道・水運、東京との関連- |
川俣 正英 | |
| 霞ヶ浦における定期航路の展開と「水郷めぐり」-土浦を中心に- | 西口 正隆 | |
| 「水」にまつわる茨城の民俗文化と地域性-研究のこれまでと課題- | 林 圭史 | |
| 直轄県における統治と「公論」 -柏崎県郡中議事者制の形成過程を事例として- |
荒川 将 | |
| 動向 | ||
| 茨城県内の中世史に関する研究会と調査事業 | 高橋 修 | |
| 台風一九号災害における長野市立博物館の活動 -民間所在の未指定文化財に対して- |
原田 和彦 | |
| 「奈良市・佐紀石塚山古墳(成務天皇陵)鳥居改修工事に伴う立ち合い調査見学」参加記 |
風間 洋 | |
| 安楽寿院南陵及び深草十二帝陵、陵墓立入り観察参加記 | 山本 雅和 | |
| 書評 | ||
| 地方史研究協議会編『拠点にみる相武の地域史―鎌倉・小田原・横浜―』 | 井上 攻 | |
| 地方史の窓/新刊案内/受贈図書論文要目 | ||
| 第405号(70-3)(2020.06) | ||
| A5/120p 1143円(税別) | ||
| 蘆名盛氏の対上杉氏外交 -新出「山内殿」宛書状の検討を通じて- |
丸島 和洋 | |
| 室町期越前国における時衆道場の展開と中央権力 | 黄 霄龍 | |
| 官位昇進運動に見る内願と「御家」 -近世後期の萩毛利家を事例に- |
根本みなみ | |
| 第61回日本史関係卒業論文発表会要旨(副題省略) | ||
| 治承・寿永の内乱と在地社会 | 小堤 捺貴 | |
| 源頼朝と甲斐武田氏 | 渡邊 紗希 | |
| 梶原景時の乱の再検討 | 時田 栄子 | |
| 戦国期の今川領国における境目領主の実態 | 藤原 大志 | |
| 豊臣政権の東国惣無事における石田三成 | 江田万結子 | |
| 近世前期大名家における政治的意思決定の構造 | 宮脇 啓 | |
| 代官頭伊奈忠治の地方支配に関する一考察 | 神田 裕樹 | |
| 近世伊豆国淡島での石切 | 増田 琴子 | |
| 天保期における武蔵豪農吉田市右衛門の社会活動 | 伊藤 由佳 | |
| 幕末期薩摩藩における琉球観 | 親富祖顕吾 | |
| 幕末対外問題と公家社会 | 岸本 萌里 | |
| 幕長戦争下における広島藩領の民衆 | 大沼 大晟 | |
| 明治前期における小学校制度 | 村上 博美 | |
| 前橋市における製糸業の発展 | 女屋 瑠乃 | |
| 愛知県対外硬派組織の動向 | 野々山 舜 | |
| シベリア出兵・撤兵政策と原敬 | 田中 那樹 | |
| 「死の知らせ」のうわさ話にみる戦死者の記憶と表象 | 田部井隼人 | |
| 戦後日本における被爆者意識の形成 | 吉村 知華 | |
| 動向 | ||
| 文理融合によって切り拓く歴史地震研究の現在 -一八三〇年文政京都地震を事例にして- |
岩橋清美 大邑潤三 加納靖之 |
|
| 「陵墓限定公開」四〇周年記念シンポジウム 「文化財としての『陵墓』と世界遺産」参加記 |
鬼塚 知典 | |
| 三重県亀山市能褒野古墳群の立会見学会参加記 | 菅野 洋介 | |
| 「高知県の学校資料を考える会」の発足と活動 |
目良裕昭 楠瀬慶太 |
|
| 「請戸の歴史と文化を知る会」に参加して | 三瓶 秀文 | |
| 茨城地方史研究会の紹介 -地方史編さんとともに歩んだ七〇年- |
永井 博 | |
| 地方史の窓/新刊案内/受贈図書論文要目 | ||
| 第404号(70-2)(2020.04) | ||
| A5/130p 1143円(税別) | ||
| 鏡板と本尊を共鋳とする懸仏の伝播について -静岡県川根本町・上長尾八幡神社の懸仏を端緒として- |
大塚 幹也 | |
| 武田信玄の永禄一二年軍事作戦と西上野衆 | 恩田 登 | |
| 第二次世界大戦期の里山林における木炭増産 -岡山県御津郡の事例- | 大塚 利昭 | |
| 動向 | ||
| 第45回全史料協全国(安曇野)大会 参加記 | 松野 准子 | |
| 同上 参加記 | 市川 包雄 | |
| 全史料協 公文書館機能普及セミナーin山形 参加記 | 佐々木結恵 | |
| 日本歴史学協会主催 歴史教育シンポジウム | ||
| 「歴史総合」をめぐって(4) ―「歴史総合」の背景― 参加記 |
風間 洋 山﨑久登 |
|
| 第12回四国地域史研究連絡協議会大会・高知県立歴史民俗資料館シンポジウム | ||
| 「豊臣政権下の四国」参加記 | 大上 幹広 | |
| 同上 参加記 | 土居喜一郎 | |
| 展示批評 | ||
| 文京ふるさと歴史館特別展「ぶんきょう写真帖-時を感じる-」 | 佐藤 貴浩 | |
| 書評 | ||
| 地方史研究協議会編『学校資料の未来-地域資料としての保存と活用-』 | 宇山 孝人 | |
| 研究例会報告要旨 | ||
| 佐賀の旧藩秩序と民権運動 | 山下 春菜 | |
| 1830年文政京都地震・1854年伊賀上野地震における比叡山周辺の被害状況 | 岩橋清美 大邑潤三 加納靖之 |
|
| 地方史の窓/新刊案内/受贈図書論文要目 | ||
| 第403号(70-1)(2020.02) | ||
| A5/122p 1143円(税別) | ||
| 鼠山感應寺の成立と江戸講中 | 國分 眞史 | |
| 府県分合方針と第三次香川県の設置過程について | 石井 裕晶 | |
| 2019年度(第70回)地方史研究協議会大会・総会報告 | ||
| 第70回(京都)大会参加記 | 澤村怜薫 麦居和真 山田恭大 小田龍哉 永井博 吉岡孝 |
|
| 動向 | ||
| 日本歴史学協会報告 | 新井 浩文 | |
| 文化財防災ネットワーク推進事業 「地域の文化財防災体制の確立に向けたブロック研究会」参加記 |
芝﨑由利子 | |
| 金原明善研究と金原家文書を守るということ |
杉山 容一 | |
| 研究例会報告要旨 | ||
| 伊達時宗丸入嗣計画と小泉庄侵攻 -年代比定の再検討を中心に- |
中沢 将吾 | |
| 中世山間荘園の特質と変容 -丹波国山国荘を素材に- |
熱田 順 | |
| 深井甚三先生の訃 | 鈴木 景二 | |
| 地方史の窓/新刊案内/受贈図書論文要目 | ||
| 第402号(69-6)(2019.12) | ||
| A5/114p 1143円(税別) | ||
| 鎌倉幕府御家人制と「御家人領」の成立 -若狭国太良荘を事例として- |
野木 雄大 | |
| 伊勢神宮の荘園支配と村落の再編 | 朝比奈 新 | |
| 戦国期能登畠山氏と本願寺・一向一揆 | 川名 俊 | |
| 動向 | ||
| 史料保存利用問題シンポジウム | ||
| 「史料保存利用運動の再検証とアーカイブズの未来」参加記 | 髙木 謙一 | |
| 「ICOM(国際博物館会議)京都大会2019」参加記 | 青木 然 | |
| 全国歴史民俗系博物館協議会北海道総会参加報告 |
伊達 元成 | |
| 最寄りの図書館で閲覧できる地方史関連のデジタル化資料 | 辰巳 公一 | |
| 首都圏形成史研究会シンポジウム「自治体史編纂の現状と課題」を聞いて | 半戸 文 | |
| 「平安京・京都研究集会」参加記 | 島田 雄介 | |
| 展示批評 春日部市郷土資料館企画展示 「元祖!成金 鈴木久五郎」 -人物を通じて社会を描く展示- |
佐藤 美弥 | |
| 研究例会報告要旨 | ||
| 三治制期における東京公用人 | 堀野 周平 | |
| 伊勢大神楽と「遊芸稼人」の時代 | 黛 友明 | |
| 地方史の窓/新刊案内/受贈図書論文要目 | ||
| 第401号(69-5)(2019.10) | ||
| A5/138p 1143円(税別) | ||
| <大会特集Ⅱ 京都という地域文化> | ||
| 問題提起 |
||
| 15 平安京以前の京都盆地とその周辺 | 高橋 明裕 | |
| 16 室町期京都と武士 | 山田 徹 | |
| 17 中世京都における職能民 | 西山 剛 | |
| 18 東本願寺の創立と寺内町の形成 | 平野 寿則 | |
| 19 淀川舟運と徳川家茂 -将軍に献上された餅- |
片山 正彦 | |
| 20 「京都旧記録」類にみる近世京都の歴史叙述 | 牧 知宏 | |
| 21 京都西郊農村の近代 -ビール麦栽培への転換を中心に- |
松中 博 | |
| 22 「伝統文化都市」京都の創出 -福沢諭吉の京都観を事例に- |
吉岡 拓 | |
| 23 八瀬と八瀬童子 | 宇野日出生 | |
| 24 京都の伝統行事からみた地域振興と地方史研究 | 福持 昌之 | |
| 25 誓願寺研究の進展と京都・地方の文化交流の再検討 | 中島 敬 | |
| 26 大学における「京都学」研究・教育の現状 | 田中 聡 | |
| 27 地域史を目指して | 小林 丈広 | |
| 第60回日本史関係卒業論文発表会 特別講座 史料編纂と地域史と-歴史研究を日常に- |
石田 文一 | |
| 第60回日本史関係卒業論文発表会 参加記 | 森岡 麗 行田健晃 福田博晃 佐藤成浩 寺島宏貴 松本武之 林幸太郎 |
|
| 動向 | ||
| 「旧真田山陸軍墓地見学会」参加記 | 桜井 昭男 | |
| 「文化資源学フォーラム:コレクションを手放す -譲渡・売却・廃棄-」参加記 |
後藤 知美 | |
| 番組小学校創設150周年シンポジウム参加記「学校資料の活用を考える」 | 風間 洋 | |
| シンポジウム「新学習指導要領下の小・中・高歴史教育と教科書」参加記 |
山﨑 久登 | |
| 京都歴史研究会について | 佐野 方郁 | |
| 勝林院研究会 | 上田 寿一 | |
| 〈共に生きる地域研究の可能性〉と今村家文書 | 秋元 せき | |
| 書評 | ||
| 地方史研究協議会編『徳島発展の歴史的基盤-「地力」と地域社会』 | 桑原 恵 衣川 仁 端野晋平 髙橋晋一 |
|
| 地方史の窓/新刊案内/受贈図書論文要目 | ||
| 第400号(69-4)(2019.08) | ||
| A5/190p 1143円(税別) | ||
| <大会特集Ⅰ 京都という地域文化> | ||
| 2019年度第70回(京都)大会 問題提起 | 常任委員会 | |
| 01 埋蔵文化財行政と考古学的都市研究 -京都の多様性を視点に- |
新田 和央 | |
| 02 権門間紛争処理再考 -平安京の貴族医社会の一様相- |
告井 幸男 | |
| 03 鎌倉期東山における宋式寺院という「場」 -泉涌寺の宋文化受容の視点から- |
西谷 功 | |
| 04 室町文化と京都 | 家塚 智子 | |
| 05 京都の寺社の勧進を請け負う戦国期の聖・山伏 | 工藤 克洋 | |
| 06 戦国期~織田・豊臣政権期の都市京都における「城」の立地と大路・小路 |
河内 将芳 | |
| 07 尼門跡寺院の調査・研究 -近世公家社会における比丘尼御所の資料- |
岸本 香織 | |
| 08 近世京都における都市と信仰 | 村上 紀夫 | |
| 09 地域史資料としての「長谷川軍記日記」 | 伊東 宗裕 | |
| 10 近代で道はどのように変わってくるか -京都府の道- |
高久嶺之介 | |
| 11 学校史からみた「京都という地域文化」の展開 | 竹村 佳子 | |
| 12 京唐紙という生活文化の継承と伝播 -唐長『千田家文書』の研究を通して- |
小粥 祐子 | |
| 13 京都文化の創造力に解明の目を | 小田 直寿 | |
| 14「京都学」は成立するのか? -民俗考古学の立場から- |
木立 雅朗 | |
| 動向 京都大会関連 | ||
| 乙訓の文化遺産を守る会(古文書部会)のあゆみと井ヶ田良治先生 | 長谷川澄夫 | |
| 平安京・京都研究集会の紹介 | 山田邦和 仁木 宏 |
|
| 柳原銀行記念資料館とその時代 | 山内 政夫 | |
| <400号記念特集> | ||
| 座談会 地方史研究協議会の大会と運営 |
(司会) 伊藤暢直 保垣孝幸/ 松尾美恵子 松尾正人 廣瀬良弘 湯浅 隆 吉田 優 |
|
| 地方史研究の現在 | ||
| 千葉県の地方史研究の現状と課題 (2010年・成田大会) |
矢嶋 毅之 | |
| 山形県における地域史研究の現状 (2011年・庄内大会) |
今野 章 | |
| 逆風の中で、その先へ進むには… (2012年・東京大会) |
寺門 雄一 | |
| 石川県における地方史研究の現状 (2013年・金沢大会) |
袖吉 正樹 | |
| 埼玉県の地方史研究とその周辺 (2014年・埼玉大会) |
榎本 博 | |
| 三河地域における自治体史編纂の軌跡 (2015年・三河大会) |
山田 邦明 | |
| 信越地域における地方史研究の現在 (2016年・妙高大会) |
佐藤 慎 | |
| 徳島県における「ネオ郷土史」と地方史研究 (2017年・徳島大会) |
福家 清司 | |
| 地域持続と地方史研究 | ||
| つぶれた村、再興される村 -江戸時代史研究から- |
菊池 勇夫 | |
| 館林市史編纂と“地域持続”への課題 | 佐藤 孝之 | |
| 歴史教育における地域、持続可能な社会への展望 -新学習指導要領を中心に- | 藤野 敦 | |
| 次世代の地方史研究のために -東北芸術工科大学歴史遺産学科の資料保存活動- |
竹原 万雄 | |
| 地域の戦争の〈記憶〉を未来へつなぐ | 佐藤 宏之 | |
| 地域学としての「地域持続史」の構想 -「古墳地域学」を例に- |
簗瀬 大輔 | |
| 文化財保護法等の改正とこれからの地方史研究をめぐる課題について | 吉田 政博 | |
| 研究例会報告要旨 | ||
| 地方史研究協議会第69回(神奈川)大会 「拠点にみる相武の地域史-鎌倉・小田原・横浜-」を振り返って |
早田 旅人 | |
| 神奈川大会を終えて -共通論題討論を中心に- |
松本 洋幸 | |
| 近世後期武州三峰山の寺院組織と「門前三十六戸」に関する考察 | 川田 大晶 | |
| 地方史の窓/新刊案内/受贈図書論文要目 | ||
| 第399号(69-3)(2019.06) | ||
| A5/136p 1143円(税別) | ||
| 戦国末期の能島村上氏と河野氏 -天正一二年を中心に- |
大上 幹広 | |
| 「満洲国」期の鉱工業と満鉄の貨物輸送 | 三木 理史 | |
| 第60回日本史関係卒業論文発表会要旨 | ||
| 動向 | ||
| 大倉幕府跡地の保存・活用を考える会連続フォーラム第3回 「原点としての大倉幕府跡~鎌倉のまちづくりのために~」参加記 | 実松 幸男 | |
| 大山(大仙・大仙陵)古墳(仁徳天皇百舌鳥耳原中陵)発掘調査見学会に参加して | 佐藤 慎 | |
| 「市庭古墳(平城天皇・楊梅陵)鳥居整備工事の立会調査」参加記 | 鬼塚 知典 | |
| 高屋築山古墳立会見学会(限定公開)参加記 |
菅野 洋介 | |
| 「指定管理者制度による公立博物館の運営~財団法人指定管理館の現状と課題~」に参加して | 鈴木紀三雄 | |
| 研究集会「地域持続におけるアーカイブズやアーキビスト等の果たす役割」参加記 | 五十嵐和也 | |
| 「地域歴史資料救出の先へⅡ」参加記 | 四家 久央 | |
| 「第11回四国地域史研究連絡協議会大会・第40回徳島地方史研究会公開研究大会」参加記 | 甲斐未希子 | |
| 「松代藩・真田家の歴史とアーカイブズⅢ」参加記 | 小泉 詩織 | |
| 素人集団による古文書保存活動 | 向坂 正美 | |
| 地方史の窓/新刊案内/各種委員会報告/事務局だより/受贈図書論文要目 |
||
| 第398号(69-2)(2019.04) | ||
| A5/110p 1143円(税別) | ||
| 播磨国矢野荘における水害と損免要求 -「荘家の一揆」形成の社会的論理- |
赤松 秀亮 | |
| 佐竹天文の乱と常陸国衆 | 泉田 邦彦 | |
| 「小山評定」再々論 -家康の宇都宮在陣説を中心に- |
本多 隆成 | |
| 動向 | ||
| 「学び舎の記録遺産-学校資料の保存・活用を考える-」参加記 | 平尾 直樹 | |
| 全国歴史資料保存利用機関連絡協議会全国(沖縄)大会参加記 | 佐藤 崇範 | |
| アーキビストの覚悟に触れて -大会参加記- | 重久 幸子 | |
| 旧陸軍墓地を今に生かす道 -財務省の予算措置決定をうけて- |
小田 康徳 | |
| 展示批評 | ||
| すみだ北斎美術館「北斎の橋 すみだの橋」を見学して | 馬場 宏恵 | |
| 豊橋市二川宿本陣資料館企画展「とよはしの旗本たち」によせて | 澤村 怜薫 | |
| 研究例会報告要旨 | ||
| 昇進運動から見る「御家」意識 -近世後期の萩毛利家を事例に- |
根本みなみ | |
| 地方史の窓/新刊案内/受贈図書論文要目 | ||
| 第397号(69-1)(2019.02) | ||
| A5/155p 1143円(税別) | ||
| 鎌倉期東国における地頭支配と郷村の動向 -常陸国真壁郡竹来・亀熊・長岡郷を中心に- |
高橋 裕文 | |
| 応永30年の室町幕府と鎌倉府 -ふたつの争乱の分析から- |
亀ヶ谷憲史 | |
| 昭和10年の北海道開発構想と二大政党の北海道支部 -住民重視型総合開発- | 井上 敬介 | |
| 2018年度(第69回)地方史研究協議会大会・総会報告 | ||
| 大会参加記 | 関根玲奈 茶園紘己 久保田昌子 茂木大樹 山本雅和 山田英明 |
|
| 動向 | ||
| 日本歴史学協会報告 | 中野 達哉 | |
| 全国歴史民俗系博物館協議会 第七回年次集会に参加して |
実松 幸男 | |
| 妙高大会のその後 -新たな研究会の発足と妙高山麓の地域文化の掘り起こし― |
佐藤 慎 | |
| シンポジウム「ふくしまの未来へつなぐ、伝えるⅡ-地元から立ち上がる資料保全と歴史叙述-」から考える歴史・文化の保存と継承 | 川上 真理 | |
| リアルタイムの歴史講座!連続フォーラム第一回『大倉幕府を知っていますか?』に参加して | 西川 修一 | |
| 文化財防災ネットワーク推進事業の現況 -関東甲信越地方での活動状況について- |
黄川田 翔 | |
| 地方史の窓/新刊案内 「百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産推薦に関する見解」に対するユネスコ世界遺産センターからの回答 |
||
| 第396号(68-6)(2018.12) | ||
| A5/95p 1143円(税別) | ||
| 在地領主の拠点開発と展開 -成田氏を事例として- |
大井 教寛 | |
| 高野山子院と地方檀家の関係 -本覚院と豊後臼杵藩の伽藍再建支援をめぐる交渉に注目して- |
村上 博秋 | |
| 地租改正事務局の活動 | 滝島 功 | |
| 動向 | ||
| 日本歴史学協会・日本学術会議史学委員会 第23回史料保存利用問題シンポジウム 「自治体アーカイブズの現状と公文書管理制度」参加記 | 上田 良知 | |
| 木更津市郷土博物館 金のすずのあゆみ -10周年を迎えて- |
多田あゆ美 | |
| 「福島の震災遺産と震災アーカイブズの構築」参加記 | 水本 有香 | |
| 「福島の震災遺産と震災アーカイブズの構築」参加記 |
橋本 唯子 | |
| 研究例会報告要旨 | ||
| 東照宮三百年祭の基礎的考察 | 岩立 将史 | |
| 近世寺社日鑑の書誌的検討 -藤沢山日鑑を中心に- |
酒井 麻子 | |
| 地方史の窓/新刊案内/受贈図書論文要目 | ||
| 声明文 「百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産推薦に関する見解」の表明について | ||
| 第395号(68-5)(2018.10) | ||
| A5/121p 1143円(税別) | ||
| <大会特集Ⅱ 拠点にみる相武の地域史―鎌倉・小田原・横浜―> | ||
| 問題提起 | ||
| 拠点としての郡(評)家とその成立について -武蔵国橘樹郡を事例に- |
望月 一樹 | |
| 相武における鎌倉期善光寺信仰の二つの拠点 -松田郷西明寺と鎌倉名越新善光寺- |
牛山 佳幸 | |
| 戦国時代の鎌倉観 | 阿部 能久 | |
| 一六世紀末から一七世紀における相武の地域性について | 斉藤 司 | |
| 水上交通の拠点・神奈川湊 | 吉﨑 雅規 | |
| 無尽講から見る金融拠点としての小田原 | 荒木 仁朗 | |
| 神奈川県産石材「白丁場石」から見た近代石材産業史 | 丹治 雄一 | |
| 高度成長期の湘南地域 -商勢の推移と公団団地の建設から考える- |
本宮 一男 | |
| 応仁・文明の乱後における石見山名氏の動向 | 伊藤 大貴 | |
| 近世後期の寺の温泉運営帳簿にみる災害と復興 -越後国妙高山雲上寺宝蔵院を事例として- |
冨樫 明美 | |
| 動向 | ||
| 横須賀開国史研究会 | 山本 詔一 | |
| 京浜歴史科学研究会の活動紹介 | 大湖 賢一 | |
| 神奈川地域資料保全ネットワークについて | 多和田雅保 | |
| 理論・実務の交差点から政策提言の主体へ -日本アーカイブズ学会2018年度大会参加記- |
西村 芳将 | |
| 四条塚山古墳(現・綏靖天皇陵)<奈良県橿原市>立入り観察参加記 |
風間 洋 | |
| 研究例会報告要旨 | ||
| 伊勢神宮の荘園支配と村落の再編 | 朝比奈 新 | |
| 地方史の窓/新刊案内/受贈図書論文要目 | ||
| 要望書「鎌倉円覚寺西側結界遺構の保存推進に関わる要望書」について | ||
| 第394号(68-4)(2018.08) | ||
| A5/129p 1143円(税別) | ||
| <大会特集Ⅰ 拠点にみる相武の地域史-鎌倉・小田原・横浜-> | ||
| 問題提起 | ||
| 律令制以前の相模と海上交流 | 永井 肇 | |
| 神奈川県における在地首長と地域拠点 -考古学の立場から- |
田尾 誠敏 | |
| 中世鎌倉人に思いを馳せよう -鎌倉の中世文書教材化の試み- |
風間 洋 | |
| 考古学から見る中世の鎌倉 | 古田土俊一 | |
| 本光院殿衆編成について | 梯 弘人 | |
| 近世相武の町場について | 多和田雅保 | |
| 拠点としての藤沢宿 -宿駅制度による地域形成- |
富田三紗子 | |
| 相模国の物流・金融拠点としての須賀湊 |
早田 旅人 | |
| 横浜市域の幕府代官編成農兵隊と開港場 | 小林 紀子 | |
| 小田原藩領民にとっての国恩を考える | 下重 清 | |
| 関東大震災復興と観光政策 -横浜復興博と箱根観光博- |
馬場 弘臣 | |
| 昭和初期の地域における観光振興組織 -箱根振興会の活動を事例として- |
高橋 秀和 | |
| 戦後神奈川における社会事業の復興過程 | 西村 健 | |
| 中華街を育む街、横浜 | 伊藤 泉美 | |
| 銭湯からみる都市横浜を支えた「同郷者」と「同業者」 | 羽毛田智幸 | |
| 軍都の形成から衛星都市へ -相模原の政治過程から見えてくるもの- |
沖川 伸夫 | |
| 革新の拠点・戦後横浜の市政 | 大西比呂志 | |
| 第59回日本史関係卒業論文発表会 特別講座 | ||
| 地方史研究と税 | 牛米 努 | |
| 第59回日本史関係卒業論文発表会 参加記 | 高尾亮伍 千葉篤志 黒田千尋 田口拓海 冨 恵美 萱場真仁 |
|
| 動向 | ||
| 神奈川県高等学校文化連盟社会科専門部の紹介 | 高階 淳子 | |
| 国立公文書館「アーキビストの職務基準書」の意義と課題 | 熊本 史雄 | |
| 展示批評 | ||
| 埼玉県立歴史と民俗の博物館「明治天皇と氷川神社 -行幸の軌跡-」を見て | 井上 拓巳 | |
| 葛飾区郷土と天文の博物館 「かつしか絵図風土記-描かれた東京低地-」 |
川名 禎 | |
| 書評 | ||
| 地方史研究協議会編 『信越国境の歴史像-「間」と「境」の地方史-』 |
矢田 俊文 | |
| 研究例会報告要旨 | ||
| 町の記録と講の再編 | 石本 敏也 | |
| 「地力」と地域社会 | 町田 哲 | |
| 徳島大会を終えて | 中山 学 | |
| 地方史の窓 新刊案内 受贈図書論文要目 | ||
| 第393号(68-3)(2018.06) | ||
| A5/104p 1143円(税別) | ||
| 天正年間の洛中における法華宗檀那の分布状況 | 長崎 健吾 | |
| 織豊大名領国と大身家臣 -越後堀領国を事例として- |
田嶋 悠佑 | |
| 第59回日本史関係卒業論文発表会要旨 | ||
| 動向 | ||
| 全国歴史資料保存利用機関連絡協議会全国大会(神奈川県相模原)参加記 | 平尾 直樹 | |
| 四国地域史研究連絡協議会香川大会「四国の中世城館」参加記 | 梶原 慎司 | |
| 四国地域史研究連絡協議会10年の歩み | 唐木 裕志 | |
| 第四回全国史料ネット研究交流集会に参加して | 土居 祐綺 | |
| 佐紀陵山古墳(「日葉酢媛命陵」)限定公開参加記 | 菅野 洋介 | |
| 研究例会報告要旨「秋田藩政における一門の政治的役割 | 清水翔太郎 | |
| 地方史の窓/新刊案内/受贈図書論文要目 | ||
| 第392号(第68巻2号)(2018.04) | ||
| A5/104p 1143円(税別) | ||
| 丁字頭勾玉の展開過程と地域性 | 瀧音 大 | |
| 筒井順慶の「日和見」と大和国衆 | 片山 正彦 | |
| <小特集 地域と歩む史料保存活動> | ||
| 地域と歩む史料保存活動 -越佐歴史資料調査会の20年とこれから- |
地方史研究協議会研究小委員会 | |
| 地域と歩む史料保存活動 -越佐歴史資料調査会の20年を振り返る- |
長谷川 伸 | |
| 越佐歴史資料調査会と自治体の連携 -新発田市蔵光・滝谷調査の事例を通して- |
鈴木 秋彦 | |
| 地域歴史資料保存の課題 -越佐歴史資料調査会に学んだこと、できなかったこと- |
西村慎太郎 | |
| 地方史研究と地域史料調査会 | 新井 浩文 | |
| 合同研究例会「地域と歩む史料保存活動」に参加して | 吉成香澄 近藤浩二 |
|
| 動向 | ||
| 越佐地方史談話会第10回記念大会参加記 | 山上 卓夫 | |
| 静岡県地域史研究会シンポジウム「近世の駿豆地域と韮山代官江川氏」参加記 | 森 昌俊 桐生海正 |
|
| 公文書館機能普及セミナーin茨城県市町村公文書管理担当者研修会 「失われゆく地域アーカイブズの保全のために」参加記 |
戸張 真 | |
| 資料保存シンポジウム「原資料保存とデジタルアーカイブ その未来―さまざまな取り組みの中から」参加記 |
井上さやか | |
| 大磯町郷土資料館リニューアルオープン一周年を迎えて | 富田三紗子 | |
| 展示批評 長野市立博物館企画展「信濃の民衆と川中島の戦い」を見学して | 野村 駿介 | |
| 地方史の窓/新刊案内/受贈図書論文要目 | ||
| 要望書「文化財保護法改定に対する要望書」について | ||
| 第391号(68-1)(2018.02) | ||
| A5/156p 1143円(税別) | ||
| 戦国大名島津氏の交通統制策と地頭衆中制 | 大山 智美 | |
| 戦国期における根来寺の日根荘進出と荘園制 | 熱田 順 | |
| 2017年度(第68回)地方史研究協議会大会・総会報告 | ||
| 第68回(徳島)大会参加記 | 竹内竜馬 岡本佑弥 田畑きよみ 米澤英昭 冨善一敏 立井佑佳 西 聡子 |
|
| <小特集 学校資料シンポジウム「学校資料の未来~地域資料としての保存と活用~」> | ||
| 公文書管理・公文書館と学校アーカイブズ | 嶋田 典人 | |
| 学校文化財がつなぐ学校・地域・博物館 | 羽毛田智幸 | |
| 台湾に残る日本統治時代の学校資料 -もし現代日本の地歴科教員が戦前台湾の国史科教員の足跡を追ったら- |
神田 基成 | |
| 「学校資料の未来~地域資料としての保存と活用~」参加記 | 太田弥保 三村宜敬 深田富佐夫 |
|
| 動向 |
||
| 日本歴史学協会報告 | 中野 達哉 | |
| 全国歴史民俗系博物館協議会 第六回年次集会参加記 | 湯浅 淑子 | |
| シンポジウム『地域歴史資料救出の先へ』参加記 | 本木 成美 | |
| 「人命環境アーカイブズの過去・現在・未来に関する双方向的研究」シンポジウム 「地域歴史資料救出の先へ」参加記 |
菅井 優士 | |
| 研究例会報告要旨 | ||
| 村の祭りと聖なる記録 -近世初期オビシャ文書と関東の村- |
水谷 類 | |
| 地方史の窓/新刊案内/受贈図書論文要目 | ||
| 第390号(67-6)(2017.12) | ||
| A5/101p 1143円(税別) | ||
| 近世前期における土豪の土地特権 | 鈴木 直樹 | |
| 1879年コレラ流行と公立病院 -長野県松本地方の医療環境- |
塩原 佳典 | |
| <小特集 第62回(庄内)大会から5年-その後の成果と課題-> | ||
| 黒川能の資料調査と研究動向 | 桜井 昭男 | |
| 第62回(庄内)大会後の庄内地域の郷土史の動向 | 今野 章 | |
| 庄内最上氏権力の成立過程 -最上氏が他領を意識したとき- |
菅原 義勝 | |
| 近代における旧上山藩士 金子清邦像の形成 -旧庄内藩郷士 清河八郎顕彰との関わりを通じて- |
長南 伸治 | |
| 地方史研究協議会合同研究例会に参加して | 三原 容子 | |
| 地方史研究協議会・鶴岡市郷土資料館合同研究例会参加記 | 星川 礼応 | |
| 動向 |
||
| 地域史料とどう向き合うか-日本歴史学協会史料保存利用問題シンポジウム 「地域史料の保存利用と公文書管理の在り方」に参加して考えたこと- | 伴野 文亮 | |
| 大仙市アーカイブズの開館について | 照井沙耶加 | |
| 和歌山地方史研究会 第137回例会(公開シンポジウム)「#(ハッシュタグ)学芸員のおしごと」参加記 |
坂本 亮太 | |
| 展示批評 | ||
| 行田市郷土博物館企画展「江戸湾沿岸警備と忍藩」を見学して | 清水 詩織 | |
| 研究例会報告要旨 | ||
| 金原明善の林業経営と経済思想 | 伴野 文亮 | |
| 戦国期幕府と在国大名の通交体制 |
浜口 誠至 | |
| 地方史の窓/新刊案内/受贈図書論文要目 | ||
| 声明 | ||
| 地方史研究協議会「文化財保護法改定に向けた動きに対する声明」 | ||
| 日本歴史学協会他「文化財保護法の改定に対し、より慎重な議論を求める声明」 | ||
| 第389号(67-5)(2017.10) | ||
| A5/163p 1143円(税別) | ||
| <大会特集Ⅱ 「地力」と地域社会―徳島発展の歴史的基盤―> | ||
| 問題提起(2) | ||
| 戦国期阿波国西部の一領主の熊野信仰とその周辺 | 長谷川賢二 | |
| 豊岡新田の開発と有付百姓の生活 | 菅野 将史 | |
| 裁判資料としての天正検地帳 | 石尾 和仁 | |
| 四国遍路の成立と発展-四国と阿波の求心力- | 胡 光 | |
| 古文書が語る厄除けの寺・日和佐薬王寺 -四国八十八ヶ所霊場研究の一視点- |
須藤 茂樹 | |
| 近世後期阿波の地域文化と遍路の旅 -半田商人を例に- |
西 聡子 | |
| 近世阿波の興行と民衆文化 -子供浄瑠璃を中心に- |
徳野 隆 | |
| 近世近代の人形浄瑠璃お全国流行について -中央の発信と、地域化する過程- |
神津 武男 | |
| 幕末期徳島の「知」と教養 |
桑原 恵 | |
| 明治初年の阿波国地誌 | 立岡 裕士 | |
| 喜田貞吉と「反差別」の歴史学 -起源論から系譜学へ- |
関口 寛 | |
| 伊島の潜水器漁業 | 宮本 和宏 | |
| 幕末期讃岐高松藩の砂糖生産統制 | 木原 溥幸 | |
| 近世安房国誕生寺における海石寺領について | 松本 和明 | |
| 明治初期大川御厩河岸渡しの架橋事業 | 斉藤 照徳 | |
| 動向(地域研究活動 文書館・資料館問題 資料保存問題 徳島大会関連) 加能地域史研究会・群馬歴史民俗研究会 |
||
| 共同研究会を終えて | 石田 文一 | |
| 共同研究会について |
伊藤 克枝 | |
| 共同研究会(石川ラウンド)「加賀・能登と上州の交流」参加記 | 久住祐一郎 | |
| 共同研究会(群馬ラウンド)に参加して | 武田 真幸 | |
| 日本アーカイブズ学2017年度大会参加記 | 加藤絵里子 | |
| 天白・元屋敷遺跡第3回シンポジウムの記録 | 犬塚 康博 | |
| 徳島地域文化研究会の活動について | 磯本 宏紀 | |
| 考古フォーラム蔵本の活動について | 中村 豊 | |
| 徳島地方史研究会第39回公開研究大会参加記 | 岡本 治代 | |
| 「徳島県戦没者記念館-あしたへ-」見学の勧め | 松下 師一 | |
| 地方史の窓/新刊案内 | ||
| 第388号(67-4)(2017.08) | ||
| A5/180p 1143円(税別) | ||
| <大会特集Ⅰ「地力」と地域社会―徳島発展の歴史的基盤―> | ||
| 問題提起 | ||
| 墓制からみた弥生時代の始まり -徳島地域をケースとして- |
端野 晋平 | |
| 竪穴式石郭の成立過程 | 菅原 康夫 | |
| 考古学からみた古代阿波国の成立 | 藤川 智之 | |
| 古代阿波国の官道整備と条里施行 | 木原 克司 | |
| 阿波国分寺創建期の造瓦組織 | 岡本 治代 | |
| 阿波国名方郡東大寺領と「図券」 | 三河 雅弘 | |
| 阿波民部大夫重能と九躰の丈六仏 | 大石 雅章 | |
| 土器・陶磁器から見た中世阿波の流通と水運 | 島田 豊彰 | |
| 出土陶磁器から見る守護所勝瑞の成立 |
重見 髙博 | |
| 中世阿波における藍業の発展と紺屋 | 福家 清司 | |
| 阿波守護家細川氏と禅院西山寺蔵院 | 山下 知之 | |
| 阿波型板碑-その信仰と流通- | 西本 沙織 | |
| 阿波三好家の出兵 | 天野 忠幸 | |
| 阿波内乱における山間地域 | 中平 景介 | |
| 二つの「一国一城令」と阿波九城の終焉について | 宇山 孝人 | |
| 寛永飢饉と徳島藩 | 三宅 正浩 | |
| 「鎖国」期異国船対応を通して見る徳島藩領の地力 |
鴨頭 俊宏 | |
| 知行絵図と村落空間-絵図資料と村落の空間・社会構造の解明- | 羽山 久男 | |
| 江戸期と明治期の「塩田面積」の差異をめぐって | 小橋 靖 | |
| 近世後期の山方の産物と請負-「水井村正石灰」を中心に- | 町田 哲 | |
| 四国遍路から木食行者へ-阿波の木食観正と道標から- | 西海 賢二 | |
| 「神代復古誓願」運動について-自由民権期における「世直し」運動の研究- | 松本 博 | |
| 近代徳島の農業-藍の衰退と農産物供給地への転換- | 佐藤 正志 | |
| 徳島県の翼賛選挙とその影響 | 竹内 桂 | |
| 第58回日本史関係卒業論文発表会 特別講座 | ||
| 蔵の資料論-歴史を伝えることの楽しさ- | 胡 光 | |
| 第58回日本史関係卒業論文発表会 参加記 | 大類優汰 戸澤英理香 竹内竜馬 藤井明広 佐藤大悟 松田みずき |
|
| 動向 | ||
| 大阪府泉南郡岬町淡輪ニサンザイ古墳(五十瓊敷入彦命宇度墓)限定公開参加記 | 永山はるか | |
| 行燈山古墳(奈良県天理市柳本)限定立ち入り観察および検討会参加記 | 寺前 直人 | |
| 第4回「学校に歴史資料室をつくっちゃおう!!フォーラムin歴博」参加記 | 甲田 篤郎 | |
| 地域博物館シンポジウム「小規模館が地域に対して果たす役割」参加記 | 鈴木 康二 | |
| 天正年間の四国の情勢をめぐって-四国中世史研究会参加記- | 川島 佳弘 | |
| 徳島地理学会の活動紹介 | 平井 松午 | |
| 展示批評「震災遺産展 我暦→ガレキ→我歴」を見学して |
菅野 洋介 | |
| 書評 地方史研究協議会編『三河-交流からみる地域形成とその変容-』 | 長澤 慎二 | |
| 研究例会報告要旨 |
||
| 天正期京都における日蓮宗寺院と檀那 | 長﨑 健吾 | |
| 公害資料をめぐる現状と課題 | 清水 善仁 | |
| 地方史の窓 新刊案内 | ||
| 声明「地域の文化財保護や博物館活動に携わる「学芸員」の重要性についての声明」 | ||
| 第387号(67-3)(2017.06) | ||
| A5/127p 1143円(税別) | ||
| 中世後期東北北部の通貨事情に関する一考察 | 小早川裕悟 | |
| 中世後期の雪下殿と鑁阿寺 | 中田 愛 | |
| 第58回日本史関係卒業論文発表会要旨 | ||
| 動向 | ||
| 資料保全活動の現状とこれから -第3回全国史料ネット研究交流集会参加記- |
永野 弘明 | |
| 第3回全国史料ネット研究交流集会に参加して | 安田 容子 | |
| 第14回日本の地域博物館シンポジウム 「博物館展示の理論と実際-これまでの体験を中心に-」参加記 |
金井 安子 | |
| 「宮崎県延岡市北川陵墓参考地立会調査見学」参加記 | 近沢 恒典 | |
| 京都府伏見城跡(桃山陵墓地)立会調査見学会(限定公開)参加記 | 桑原 功一 | |
| 四国中世史研究会の現状 | 長谷川賢二 | |
| 鳴門史学会の活動について |
町田 哲 | |
| 研究例会報告要旨 | 佐藤正三郎 小関悠一郎 友田昌宏 青木昭博 荒木仁朗 風間洋 花岡公貴 |
|
| 地方史の窓 新刊案内 | ||
| 回答書 千葉県文書館収蔵公文書に係る要望書について | ||
| 第386号(67-2)(2017.04) | ||
| A5/118p 1143円(税別) | ||
| 小山評定の歴史的意義 | 水野 伍貴 | |
| 天文期山城国をめぐる三好宗三の動向 -山城守護代的立場の木沢長政と比較して- |
山下真理子 | |
| 東寺領山城国上久世荘における山林資源利用 -「鎮守の森」と「篠村山」- | 高木 純一 | |
| 動向 | ||
| 第10回資料保存シンポジウム参加記 | 植田 真平 | |
| 全国歴史資料保存利用機関連絡協議会全国(三重)大会参加記 | 照井沙耶加 | |
| 全国歴史資料保存利用機関連絡協議会全国(三重)大会参加記 | 飯島 章仁 | |
| 創立60周年を迎えた「群馬文化」 | 宮﨑 俊弥 | |
| 群馬県地域文化研究協議会 |
||
| 「歴史文化遺産の保存と活用を考えるシンポジウム」参加記 | 竹内 励 | |
| 30周年を迎えた栃木県立文書館 | 山本 訓志 | |
| 第9回四国地域史研究連絡協議会大会・第1218回伊予史談会例会 |
||
| 「四国の城を考える」参加記 | 岡本 佑弥 | |
| 徳島地方史研究会50年の歩み | 松下 師一 | |
| 展示批評 | ||
| 岐阜市歴史博物館特別展「葵の時代―徳川将軍家と美濃―」 | 中尾喜代美 | |
| 埼玉県立歴史と民俗の博物館特別展 |
||
| 「徳川家康―語り継がれる天下人―」を見て | 大橋 毅顕 | |
| 研究例会報告要旨「宅地化と祭礼行事」 | 佐藤 智敬 | |
| 千葉県文書館収蔵公文書の不適切な大量廃棄・移動の停止を求める要望書 | ||
| 地方史の窓/新刊案内/受贈図書論文要目 | ||
| 第385号(67-1)(2017.02) | ||
| A5/106p 1143円(税別) | ||
| 近世後期における直上納制と地主的土地所有 -信州松代藩を事例として- |
菅原 一 | |
| 明治二〇年代後半における新潟県の赤痢流行 | 竹原 万雄 | |
| 2016年度(第67回)地方史研究協議会大会・総会報告 | ||
| 第67回(妙高)大会参加記 | 簗瀬大輔 本田雄二 宮川展夫 角 明浩 青木裕美 徳野 隆 |
|
| 動向 | ||
| 日本歴史学協会報告 | 中野 達哉 | |
| 首都圏形成史研究会第一〇〇回記念例会 |
||
| 「博物館は高度成長をどう伝えるか?」参加記 | 武田周一郎 | |
| 「陵墓公開をめぐる成果と未来シンポジウム」参加記 | 菅野 洋介 | |
| 地方史の窓/新刊案内 | ||
| 第384号(66-6)(2016.12) | ||
| A5/126p 1143円(税別) | ||
| 集思社と土浦 -海老原穆・吉島高尚・鳥居正功を中心にして- |
西腰周一郎 | |
| 岡山藩池田家における改易について | 浪江 健雄 | |
| <小特集 東日本大震災関連シンポジウム「大震災からの復興と歴史・文化の継承」> | ||
| 旧警戒区域からの文化財保全への取り組み | 三瓶 秀文 | |
| いわき市における無形民俗文化財の 継承の取り組み -「三匹獅子舞」の事例より- |
田仲 桂 | |
| 歴史・文化の継承とこれからの復興活動 -東日本大震災関連シンポジウム参加記- |
阿部 祐也 | |
| 東日本大震災関連シンポジウムに参加して | 泉田 邦彦 | |
| 書評 阿部浩一編 『ふくしま再生と歴史・文化遺産』 |
新井 浩文 | |
| 動向 | ||
| 史料保存利用問題シンポジウム | ||
| 「被災史料・震災資料の保存利用と公文書管理」 に参加して |
添田 仁 | |
| 史料保存利用問題シンポジウム 参加記 | 久保田昌子 | |
| 鎌倉円覚寺結界開削反対運動と要望書提出の 経緯について |
馬淵 和雄 | |
| 展示批評 新潟県立歴史博物館 平成二八年度春季企画展 | ||
| 「おふだにねがいを-呪符-」 | 土田 拓 | |
| 研究例会報告要旨 | 石田文一 門松秀樹 前田桂子 大貫茂紀 喜多祐子 |
|
| 第383号(2016.10) | ||
| A5/146p 1143円(税別) | ||
| <大会特集Ⅱ 「境(さかい)」と「間(あわい)」の地方史-信越国境の歴史像-> | ||
| 問題提起 | ||
| 信越国境周辺におけるむらの消滅と生活圏 | 土田 拓 | |
| 信越(北信)五岳の山岳信仰 | 小栁 義男 | |
| 廻国行者から木食行者へ -妙高から戸隠への足跡を中心にして- |
西海 賢二 | |
| 考古学からみた古代の信越関係 | 坂井 秀弥 | |
| 中世の信越国境をまたぐ人・モノ・道 | 高橋 一樹 | |
| 川中島合戦と信越国境 | 海老沼真治 | |
| 近世信越間の商品流通をめぐって | 原 直史 | |
| 女手形の発行と高田藩 | 浅倉 有子 | |
| 信越国境の間道と盗賊 | 鈴木栄太郎 | |
| 県境を超える北信越自由民権運動の世界 | 河西 英通 | |
| 戦争末期の無格社整理政策と上越地方 | 畔上 直樹 | |
| 日豊国境の歴史像 -延岡藩領六箇組と佐伯藩領蒲江浦組の争論を題材として- |
増田 豪 | |
| 中世土佐国幡多地域における金剛福寺の存在形態 | 大利 恵子 | |
| 明治期における城址公園の性格変化 -萩公園を例として- |
平井 誠 | |
| 動向 | ||
| 日本アーカイブズ学会2016年度大会に参加して | 渡辺 彩香 | |
| 高知戦争資料保存ネットワークの設立について | 楠瀬 慶太 | |
| 新潟県妙高市における地方史活動 | 佐藤 慎 | |
| 展示批評 大田区立郷土博物館特別展 「まちがやって来た-大正・昭和 大田区のまちづくり-」展をみて |
実松 幸男 | |
| 書評 | ||
| 地方史研究協議会編『北武蔵の地域形成-水と地形が織りなす歴史像-』 | 小山 貴子 | |
| 研究例会報告要旨 | 若山浩章 渡辺嘉之 大浪和弥 丸山翔太 竹村茂紀 山澤 学 和田 実 |
|
| 地方史の窓・新刊案内 | ||
| 要望書・声明 鎌倉円覚寺西側結界遺構の保存に関する要望書/同遺構の保存を求める声明 |
||
| 訃報 川村優先生逝く | 渡邉 晨 | |
| 第382号(66-4)(2016.08) | ||
| A5/147p 1143円(税別) | ||
| <大会特集Ⅰ 「境(さかい)」と「間(あわい)」の地方史―信越国境の歴史像―> | ||
| 問題提起 | ||
| 信越を結ぶ街道と峠道 | 花岡 公貴 | |
| 長野県と上越の合併論 | 新井 雄太 | |
| 『宝蔵院日記』に見える信越の人々 | 清沢 聰 | |
| 関山権現夏季祭礼における信州からの山伏 | 由谷 裕哉 | |
| 弥生・古墳時代の土器の移動 -上越と北信の状況- |
滝沢 規朗 | |
| 考古学からみた古墳時代の信越 | 佐藤 慎 | |
| 越後国域の変遷と信濃 | 小林 昌二 | |
| 古代・中世の信濃国と日本海沿岸地域 | 傳田 伊史 | |
| 信越国境の戦国時代 | 村石 正行 | |
| 文明一八年七、八月の堯恵と道興 | 牛山 佳幸 | |
| 中世後期信越の諸相 -頸城の人びとの意識を中心に- |
木村 康裕 | |
| 信越国境の山論 | 丑山 直美 | |
| 国界と山論 -近世信越の巣鷹山争論から- | 白水 智 | |
| 信越幕領の存在形態 | 西沢 淳男 | |
| 慶応二年凶作時の信越国境における米の動き | 山崎 圭 | |
| 信越地域における近代都市形成の一側面 -北信各市聯合協議会について- |
中村 元 | |
| 北信地域の住民運動-長野警廃事件を中心に- | 望月 誠 | |
| 瞽女の旅路 | 板橋 春夫 | |
| 巨大藩領のなかの「境」と「間」 | 木越 隆三 | |
| 第57回日本史関係卒業論文発表会 特別講座 | ||
| 県史編さんから文書館の世界へ -地域史料の保存に携わって- |
岡田 昭二 | |
| 参加記 | 永井瑞枝 茶園紘己 竹内励 栗原正東 半戸文 三浦直人 |
|
| 動向 | ||
| シンポ「津波被災文化財再生への挑戦 -東日本大震災から五年-」参加記 |
佐藤 大樹 | |
| 徳島地方史研究会公開研究大会参加記 | 菅野 将史 | |
| 長野県北信地域における地方史活動 | 村石 正行 | |
| 博物館を核とする市民参加と地域連携の試み -新潟県を事例に- |
井上 信 | |
| 展示批評 | ||
| 葛飾区郷土と天文の博物館 平成27年度特別展 「平成かつしか風土記-地域の継承と文化財-」 |
杉山 哲司 | |
| 桑名市博物館開館30周年記念 白河市合併10周年記念 桑名市・白河市合同特別企画展「大定信展-松平定信の軌跡-」 |
望月 良親 | |
| 研究例会報告要旨 嘉永小田原地震の震災対応 -小田原城下を事例に- |
岡崎 佑也 | |
| 明治初期における小田原藩生産方と「御用取扱役」の動向 | 桐生 海正 | |
| 地方史の窓/新刊案内 | ||
| 第381号(66-3)(2016.06) | ||
| A5/108p 1143円(税別) | ||
| 三河の国人連歌から天下の柳営連歌へ | 鶴崎 裕雄 | |
| 幕末琉球における異国人応接「官職」制度 -フォルカード逗留期を事例に- |
小林 伸成 | |
| 第57回日本史関係卒業論文発表会要旨 | ||
| 動向 | ||
| 2015年度陵墓限定公開「渋谷向山古墳(景行天皇陵)」参加記 | 永井 瑞枝 | |
| 情報保存研究会第9回シンポジウム 「後世に伝えるための資料保存とデジタルアーカイブ」に参加して |
佐藤 麻里 | |
| 追想 所理喜夫氏を偲んで | 松尾正人 竹内誠 高木俊輔 佐藤孝之 久保田昌希 中野達哉 太田尚宏 宮島敬一 橋詰茂 |
|
| 研究例会報告要旨 | ||
| 天正後期北関東の政治情勢における「惣無事」 | 宮川 展夫 | |
| 第380号(66-2)(2016.04) | ||
| A5/97p 1143円(税別) | ||
| 古代河内の石津 ―倭王権による河内進出の一端― |
溝口 優樹 | |
| 十五世紀の那須氏 ―上・下那須氏分裂の再検討を中心として― |
那須 義定 | |
| 近世民衆の船旅と廻船業 | 中安 恵一 | |
| 動向 | ||
| 地域史料の保全にむけて | 井上 知明 | |
| 第41回全史料協全国(秋田)大会に参加して | 漆畑真紀子 | |
| 東京都三多摩公立博物館協議会・三多摩地域資料研究会合同研修会 「戦後70年を考える―戦争体験を次の世代に伝えるために―」参加記 |
青海 伸一 | |
| 四国地域史連絡協議会第八回高知大会「四国と戦争」参加記 | 岩村 麻里 | |
| 展示批評 安城市歴史博物館 特別展「台地を拓く 都築弥厚の夢」を見て | 塚本弥寿人 | |
| 研究例会報告要旨 | 湯谷 翔梧 | |
| 訃報 所理喜夫先生を偲んで | 廣瀬 良弘 | |
| 第379号(第66巻1号)(2016.02) | ||
| A5/117p 1143円(税別) | ||
| 野木宮の合戦再考 ―内乱における「合力」― | 菱沼 一憲 | |
| 在地修験寺院と「除病祈祷」 ―文久期の秋田藩を事例に― |
松野 聡子 | |
| 2015年度(第66回)大会・総会報告 | ||
| 第66回(三河)大会参加記 | 高橋菜月 石田泰弘 佐伯郁乃 岩月あすか 山下智也 村瀬貴則 |
|
| 日本歴史学協会報告 | 中野 達哉 | |
| 戦後70年関連展示批評 | ||
| 戦後70年関連の展示批評によせて | 博物館・資料館問題検討委員会 | |
| 八潮市立資料館 戦後70年平和祈念事業企画展「戦火に生きる」を見学して | 井上かおり | |
| 空襲死者の「名前」が伝えるもの すみだ郷土文化資料館「東京大空襲と失われた命の記録」展を見る |
山本 唯人 | |
| 横浜市史資料室2015年度展示会 「戦後70年 戦争を知る、伝える―横浜の戦争と戦後―」 |
早田 旅人 | |
| 地方史の窓 新刊案内 | ||
| 第378号(第65巻6号)(2015.12) | ||
| A5/110p 1143円(税別) | ||
| 木曽川の水力開発をめぐる地域紛争 | 浅野 伸一 | |
| 倉敷紡績の初期経営と大原孝四郎 -地方企業の経営史的分析からの視座- |
伊藤 末高 | |
| 「郷士帯刀」と「郷士株」 -山城国壬生村郷士と郷士前川家の創出- | 尾脇 秀和 | |
| 動向 | ||
| 史料保存利用問題シンポジウム「地域史料に未来はあるか? -史料の保存利用と地域のアイデンティティ-」参加記 |
長瀨光仁 西向宏介 |
|
| 全国歴史民俗系博物館協議会第四回年次集会参加記 | 武藤 真 | |
| 首都圏形成史研究会創立二〇周年シンポジウム「首都と首都圏」参加記 | 中野 良 | |
| 「公文書管理法5年見直しについての合同研究集会」参加記 | 栗原 健一 | |
| 研究例会報告要旨 | ||
| 三重県鳥羽市答志の漁業と信仰 -漁業信仰と講の関連を視野に- |
髙木 大祐 | |
| 地方史の窓/新刊案内/受贈図書論文要目 | ||
| 第377号(65-5)(2015.10) | ||
| A5/142p 1143円(税別) | ||
| <大会特集Ⅱ 三河-交流からみる地域形成とその変容> | ||
| 問題提起 | ||
| 三河の東と西 -豊川流域と矢作川流域- | 藤田 佳久 | |
| 考古学上の東西三河 | 荒井 信貴 | |
| 中世三河の特質 | 山田 邦明 | |
| 中・近世移行期における普門寺の「復古」と三遠国境地域 | 服部 光真 | |
| 近世譜代大名田原藩の年中行事 | 鈴木 利昌 | |
| 豊川と矢作川の分一番所をめぐって | 堀江登志実 | |
| 西三河の醸造業と奥立船 | 曲田 浩和 | |
| 地芝居にみる三河地域 | 神谷 朋衣 | |
| 慶応四年戊辰戦争期における三河諸領主の動向 | 神谷 智 | |
| 三河と遠江における在地神職の組織化と神葬祭 | 鈴木 雅晴 | |
| 向陽学舎の研究 -明治・大正期宮崎県における私立教員養成機関- |
竹村 茂紀 | |
| 十八世紀における家史編纂 -鳥取藩家老鵜殿長春と『鵜殿家史』- |
平野 仁也 | |
| 動向 | ||
| 三河民俗談話会 | 伊藤 正英 | |
| 西三河地方史連絡協議会の歩み | 荒井 信貴 | |
| 愛知大学綜合郷土研究所 | 神谷 智 | |
| 日本アーカイブズ学会大会企画研究会「アーカイブズを学びに活かす」参加記 | 浪江 健雄 | |
| 「文化遺産と災害に強い地域社会」東京シンポジウム参加記 | 根ヶ山泰史 | |
| ふくしま震災遺産保全プロジェクトの活動 | 高橋 満 | |
| 山形県内における史料保存関連の動向 | 佐藤正三郎 | |
| 展示批評 | ||
| 長野市立博物館特別展示 「信仰のみち 善光寺・戸隠・飯縄・小菅・斑尾・妙高」「狐にまつわる神々」 |
前嶋 敏 |
|
| 研究例会報告要旨 | ||
| 北昤吉と昭和初期佐渡政界 | 大庭 大輝 | |
| 第376号(65-4)(2015.08) | ||
| A5/134p 1143円(税別) | ||
| 大会特集Ⅰ 三河 ―交流からみる地域形成とその変容― | ||
| 問題提起 | ||
| 考古学からみた古代三河国成立期の東西交流 | 前田 清彦 | |
| 持統太上天皇の行幸からみる三河国 | 廣瀬 憲雄 | |
| 中世後期三河における吉良氏の政治的地位 -その序論として- |
小林輝久彦 | |
| 三河湾を跨ぐ戦国期戸田氏の動向 | 村岡 幹生 | |
| 西三河の大名家墓地 | 松井 直樹 | |
| 三河国における河川水運の利用 | 村瀬 典章 | |
| 近世文書に稀出語彙「東三河」「西三河」を見る | 桒原 将人 | |
| お札降り発生地と津島天王社・参宮船 | 橘 敏夫 | |
| 三河における歌壇について | 塚本弥寿人 | |
| 三河地域における書物交流 -羽田野と竹尾を中心に- |
上田 早織 | |
| 三河万歳と関東の檀家について | 岡田 昭二 | |
| 西三河の民権派 | 高橋 賢 | |
| 三河における旧制中学校の設立と廃止をめぐる動向 -地域間「交流」と地域意識に着目して- | 山下廉太郎 | |
| 「日本デンマーク」と近代三河農村 | 平野 正裕 | |
| 三河の民俗の地域性 | 服部 誠 | |
| 三遠信大念仏と周辺の大念仏芸能 | 坂本 要 | |
| 旅する花太夫衆-奥三河花祭の文化交流から- | 西海 賢二 | |
| 第56回日本史関係卒業論文発表会 特別講座 | ||
| フィールドへ出よう、村を歩こう -地域史料の保存利用のために- |
佐藤 孝之 | |
| 第56回日本史関係卒業論文発表会 参加記 | 土居嗣和 長瀨光仁 松本智恵 仲泉 剛 松尾悠亮 野浪雄貴 |
|
| 動向 地域研究活動 | ||
| 「第七回四国地域史研究連絡協議会大会」参加記 | 宮田 克成 |
|
| 岡崎地方史研究会の歩み | 中根 洋 | |
| 愛知大学中部地方産業研究所の活動 | 樋口 義治 | |
| 崋山・史学研究会のあゆみ | 鈴木 利昌 | |
| 書評 地方史研究協議会大会成果論集 | ||
| 『“伝統”の礎-加賀・能登・金沢の地域史-』 | 清水 聡 | |
| 展示批評 石神井公園ふるさと文化館特別展 | ||
| 「富士山-江戸・東京と練馬の富士-」に寄せて | 今井 功一 | |
| 研究例会(埼玉大会総括例会)報告要旨 | 水品洋介 実松幸男 |
|
| 訃報 新行紀一先生と三河地域史 | 久保田昌希 | |
| 第375号(第65巻3号)(2015.06) | ||
| 1143円(税別) | ||
| 近世後期の江戸の花火と幕府政策 | 福澤 徹三 | |
| 帝国議会開設後における鉄道敷設運動と地方官 ―岩越線と福島県知事日下義雄― |
徳竹 剛 | |
| <小特集 シンポジウム「基礎的自治体の文書館の現状と課題」> | ||
| シンポジウム開催にあたって | 地方史研究協議会文書館問題検討委員会 | |
| 松本市文書館の現状と課題 | 小松 芳郎 | |
| 小布施町文書館について | 山岸 正男 | |
| シンポジウムに参加して | 大橋 昌人 | |
| シンポジウム参加記 | 高木 秀彰 | |
| 公害問題資料と資料館の可能性 ―「公害資料館連携フォーラムin富山」の開催― |
小田 康徳 | |
| 第五六回日本史関係卒業論文発表会要旨 | ||
| 動向 陵墓問題 災害史料関連 地域研究活動 | ||
| 2014年度陵墓限定公開 ニサンザイ古墳(宇度墓)参加記 | 山下真理子 | |
| シンポジウム「災害史を研究し続けること、史料を保全し続けること ―新潟地震50年・中越地震10年―」参加記 |
田中 洋史 | |
| 松平シンポジウム | 三島 一信 | |
| 刈谷市郷土文化研究会―私的な紹介― | 岡本 建国 | |
| 展示批評 都城島津邸開館5周年記念特別展 「島津と北郷の時代―鎌倉・南北朝期の南九州―」を観て |
増田 豪 | |
| 第374号(第65巻2号)(2015.04) | ||
| 1143円(税別) | ||
| 近世後期の頼母子運営と豪農 ―備中国南西部を題材に― |
東野 将伸 | |
| 神宮御師集団と師檀関係 ―寛永年間の争論をめぐって― |
谷戸 佑紀 | |
| 博物館・資料館問題 | ||
| 「基礎的自治体の地域博物館のあり方に関する指標」の作成について | ||
| 基礎的自治体の地域博物館のあり方に関する指標 | ||
| 自治体の標準的行政事務と地域博物館 | 伊藤 暢直 | |
| 動向 | ||
| 福岡大会に参加して | 小川 晶子 | |
| 「全国歴史資料保存利用機関連絡協議会全国(福岡)大会」参加記 | 菅野 直樹 | |
| シンポジウム「多摩地域の博物館・資料館・美術館における防災と地域連携」参加記 | 森 悦子 | |
| 写真保存事業からみえてくるもの ―「ガラス乾板の調査・保存・研究資源化に関する研究」集会参加記― |
川﨑 華菜 | |
| 秋田県大仙市公文書館設置シンポジウム 「そうだ、あーかいぶずへ行こう!」開催報告記 |
髙橋 一倫 | |
| 天白・元屋敷遺跡破壊の全国報道と現在遺跡が置かれている状況の報告 | 櫻井 隆司 | |
| 三河地域史研究会の歩みと現状 | 田中 康弘 | |
| 展示批評 枚方市立枚方宿鍵屋資料館・淀川資料館合同企画展 「明治一八年の淀川洪水」を見学して |
常松 隆嗣 | |
| 研究例会報告要旨 近世中期幕領の代官変更に伴う変化―武蔵国神奈川領を題材として― |
道上 和洋 | |
| 第373号(第65巻1号)(2015.02) | ||
| 1143円(税別) | ||
| 皇国農村確立運動下の村造り構想と農地解放 ―静岡県磐田郡富岡村の事例より― |
鈴木 正行 | |
| 尾張国熱田東浜御殿の創建年代 | 永井 哲夫 | |
| 2014年度(第65回)大会・総会報告 | ||
| 第65回(埼玉)大会参加記 | 須藤茂樹 小沼幸雄 村岡幹生 太田弥保 山田邦明 小田直寿 |
|
| 動向 | ||
| 日本歴史学協会報告 | 中野 達哉 | |
| 宮崎県西都市男狭穂塚古墳立会調査参加報告 | 近沢 恒典 | |
| 第七回越佐地方史談話会参加記 | 中山 清 | |
| 展示批評 館山市立博物館 特別展 | ||
| 「安房の干鰯 いわしと暮らす、いわしでつながる」を見て | 鎮目 良文 | |
| 第372号(第64巻6号)(2014.12) | ||
| 1143円(税別) | ||
| 幕末期長崎奉行所の開港場運営と「ロシア村」 -「郷方」三ヶ村浦上村渕庄屋の動向を中心に- |
吉岡 誠也 | |
| 新潟奉行川村修就の物価抑制策と窮民救助対策 | 中野 三義 | |
| 動向 | ||
| シンポ「アーキビスト認定制度をめぐる現状と公文書管理制度」参加記 | 佐藤 勝巳 | |
| シンポ「歴史災害を伝える-「災害史」展示の現状と課題」参加記 | 落合功 榎本博 |
|
| 全国歴史民俗系博物館協議会第三回年次集会参加記 | 亀尾美香 小野浩 |
|
| 展示批評 | ||
| みくに龍翔館「本多成重丸岡入城400年記念 本多成重と丸岡城」を観て | 遠藤 英弥 | |
| 土浦市立博物館「城下町土浦の祭礼-江戸の文化と土浦」を観て | 松岡 薫 | |
| 多摩市文化振興財団・宮内庁宮内公文書館共催 「みゆきのあと-明治天皇と多摩」を観て |
牛米 努 | |
| 研究例会報告要旨 | 番場夏希 吉岡拓 菊地悠介 |
|
| 地方史の窓/新刊案内 | ||
| 訃報 小高昭一氏の訃 | 出口 宏幸 | |
| 第371号(第64巻5号)(2014.10) | ||
| 1143円(税別) | ||
| <大会特集Ⅱ 北武蔵の地域形成-水と地形が織りなす歴史像-> | ||
| 問題提起 | ||
| 14 板碑と地域の仏教史 | 有元 修一 | |
| 15 北武蔵地域における板碑造立に関する一視点 | 滝澤 雅史 | |
| 16 武蔵成田氏と鎌倉府権力・享徳の乱 | 清水 亮 | |
| 17「忍城水攻め」歴史像の形成 | 鈴木紀三雄 | |
| 18 北武蔵の地域編成 -御捉飼場の視点から- | 水品 洋介 | |
| 19 近世中山道鴻巣宿周辺村落の耕地と集落 | 森 朋久 | |
| 20 北武蔵北端地域における先進性 | 井上 潤 | |
| 21 熊谷地域における戦後初期の青年運動について | 岸 清俊 | |
| 22 熊谷の麦文化 | 平井加余子 | |
| 23 歴史時代の火山噴出物を指標とした利根川河道変遷解明の可能性 | 井上 素子 | |
| 京都公家華族の負債問題 | 刑部 芳則 | |
| 動向 | ||
| アーカイブズ学会2014年度大会参加記 | 針谷 武志 | |
| 埼玉県地域史料保存活用連絡協議会40年の活動 | 工藤 宏 | |
| 埼玉県における大学サークルの史料保存活動 -立正大学古文書研究会の取り組み- |
堀野 周平 | |
| 埼玉地理学会の歩み | 山本 充 | |
| 埼玉県郷土文化会の活動について | 有元 修一 | |
| 展示批評 安城市歴史博物館特別展 「三州に一揆おこりもうす-三河一向一揆450年-」 |
福原 圭一 |
|
| 書評 地方史研究協議会編『地方史活動の再構築』 | 佐藤正三郎 | |
| 研究例会報告要旨 | 坂江渉 板垣貴志 池田英真 出口宏幸 川上真理 堀井美里 |
|
| 地方史の窓/新刊案内 | ||
| 第370号(第64巻-4号)(2014.08) | ||
| 1143円(税別) | ||
| <大会特集I 北武蔵の地域形成 ―水と地形が織りなす歴史像―> | ||
| 問題提起 | ||
| 1 利根・荒川流域における古墳群の形成 | 塚田 良道 | |
| 2 北武蔵の水害史 | 根ヶ山泰史 | |
| 3 熊谷氏と熊谷郷をめぐるいくつかの論点 | 高橋 修 | |
| 4 忍成田氏の国衆化をめぐって | 黒田 基樹 | |
| 5 「北武蔵地域」の豪農層と水利普請組合 | 榎本 博 | |
| 6 交通史の視点 ―中山道から日本鉄道への交通結節点― |
杉山 正司 | |
| 7 幕末変革期における関東豪農の役割と根岸友山 | 根岸 友憲 | |
| 8 寺子屋から学校へ ―玉松堂を例として― | 濱田 由美 | |
| 9 熊谷における製糸業の展開 | 小林 公幸 | |
| 10 熊谷の戦災についての考察 | 来間 平八 | |
| 11 年中行事と地域性 | 飯塚 好 | |
| 12 北武蔵に残る伝統と文化継承に関する一考察 | 瀬藤 貴史 | |
| 13 「荒川筋工作物構造明細図」にみる北武蔵の近代 | 増山 聖子 | |
| <小特集 東日本大震災と地方史研究> | ||
| 岩手県九戸郡洋野町の被災と震災後の状況 | 酒井 久男 | |
| 三陸文化復興プロジェクトの取り組み | 小笠原 晋 | |
| 震災から三年が過ぎたが | 佐々木 淳 |
|
| 東日本大震災の被災状況と文化財保全 ―福島県双葉町に於ける現状― |
吉野 高光 | |
| 茨城県桜川市の被災と復旧事業について | 寺崎 大貴 | |
| 第55回日本史関係卒業論文発表会 特別講座 | ||
| 地方・地域・郷土を意識して | 菊池 勇夫 | |
| 第55回日本史関係卒業論文発表会 参加記 | 富居幸斗 |
|
| 動向(博物館・資料館問題 地域研究活動 陵墓問題) | ||
| 平成二十五年度神奈川県博物館協会主催講演会参加記 | 根本佐智子 | |
| 第四回松平シンポジウム | ||
| 「三州に一揆おこりもうす―三河一向一揆の本質を問う―」参加記 | 水野 智之 | |
| 野口王墓古墳(天武・持統檜隈陵)見学会(限定公開)参加記 | 風間 洋 | |
| 第369号(第64巻3号)(2014.06) | ||
| 1143円(税別) | ||
| 戦国大名武田氏の西上野支配と箕輪城代 -内藤昌月宛「在城定書」の検討を中心に- |
丸島 和洋 | |
| <シンポジウム 基礎的自治体の博物館・資料館の使命と役割2> -地方史研究協議会版 地域博物館指標」を考える- |
||
| 開催にあたって | 地方史研究協議会博物館・資料館問題検討委員会 | |
| 地方史研究協議会版 地域博物館指標(素案) | ||
| 「地方史研究協議会版 地域博物館指標(素案)」作成について | 乾 賢太郎 | |
| 常設展示の更新と地域博物館の使命 -展示改装事業から五年を経て- |
萩谷 良太 | |
| 地方自治体と博物館 -泉佐野市の事例から- | 森 昌俊 | |
| 「地方史研究協議会版 地域博物館指標(素案)」についてのコメント | 小島 道裕 | |
| 「地方史研究協議会版 地域博物館指標(素案)」を読んで | 秋山 伸一 | |
| シンポジウム「基礎的自治体の博物館・資料館の使命と役割2」参加記 | 外山 徹 | |
| 「地方史研究協議会版 地域博物館指標」作成への期待 | 宮川 充史 | |
| 第55回日本史関係卒業論文発表会要旨 | ||
| 動向(史料保存問題 地域研究活動) | ||
| 人間文化研究機構連携研究シンポジウム | 藍原 怜 | |
| 「災害に学ぶ-歴史文化情報資源の保全と再生-」参加記 | ||
| 埼玉考古学会の歩みと活動 | 中島 洋一 | |
| 訃報 村上直先生と地方史研究 | 馬場 憲一 | |
| 第368号(64-2)(2014.04) | ||
| 1143円(税別) | ||
| 明治初年における藩の議事制度 -上総国柴山藩の会議所巷会を事例に- |
堀野 周平 | |
| 中世東国の宿の構造と検断職 -常陸国新治郡田宮宿を中心に- |
高橋 裕文 | |
| 動向 | ||
| 第39回全史料協(東京)大会参加記 | 藤 隆宏 | |
| 第39回全史料協(東京)大会に参加して | 伊藤 一晴 | |
| 第99回全国図書館大会に参加して | 野口 文 | |
| 第11回日本の地域博物館シンポジウム 「学芸員はどのような地域博物館を望んだのか」に参加して |
茂木 健緒 | |
| いわて高等教育コンソーシアム・国文学研究資料館合同講演会 「なぜアーカイブズは必要なのか-文書保存の意義と実態」に参加して |
松崎 裕子 | |
| 震災資料及び学校資料の現状と課題-シンポジウム 「震災資料・学校資料をどのように保全し活用するか」に参加して- |
吉田 律人 | |
| 三重県亀山市能褒野古墳群見学会参加記 | 荊木 美行 | |
| 三重県亀山市能褒野古墳群見学会に参加して | 厚地 淳司 | |
| 第27回越後と会津を語る会会津若松大会参加記(主催記) | 長谷川慶一郎 | |
| 「四国地域史連絡協議会香川大会」参加記 | 大谷 都湖 | |
| 香川歴史学会創立60周年を迎えて | 唐木 裕志 | |
| 埼玉民俗の会の活動と歩み | 飯塚 好 | |
| 展示批評 | ||
| 春日部市郷土資料館特別展 「最後の将軍が見た春日部-野鳥と御鷹場・御猟場-」を観て |
水品 洋介 | |
| 東日本大震災後の博物館における災害史展示を考える | 橋本 直子 | |
| 杉並区立郷土博物館特別展「甲州道中へのいざない-行き交う人・モノ-」 | 野本 禎司 | |
| 研究例会報告要旨 戦国期畿内の木沢長政の動向 | 山下真理子 |
|
| 第367(第64巻第1号)2014年2月 | ||
| 1143円(税別) | ||
| 近世後期旗本領支配と知行付百姓の「譜代意識」 | 澤村 怜薫 | |
| 南北朝期の那須氏に関する一考察 -本宗那須氏と伊王野氏の関係を中心として- |
那須 義定 | |
| 第64回(金沢)大会参加記 | 番場夏希 鎌田康平 山下真理子 佐藤愛未 蛭間健悟 網谷行洋 |
|
| 動向 | ||
| 日本歴史学協会報告 | 中野 達哉 | |
| 大阪府羽曳野市小白髪山古墳(清寧天皇陵飛地い号) 発掘調査の見学会(限定公開)参加記 |
桑原 功一 | |
| 地域-自治体史シンポジウム-「自治体史編纂事業の成果と今後」参加記- | 滝尻 侑貴 | |
| 熊谷市郷土文化会の活動 | 来間 平八 | |
| 展示批評 | ||
| 茨城県立歴史館特別展「筑波山-神と仏の御座す山-」 | 櫛田 良道 | |
| 横浜都市発展記念館特別展「関東大震災と横浜-廃墟から復興まで-」 横浜開港資料館企画展示「被災者が語る関東大震災」 |
池田 真歩 | |
| 研究例会報告要旨 | ||
| 近代水道施設の政治史 | 松本 洋幸 | |
| 地方史の窓/新刊案内 | ||
| 第366号(63巻6号)(2013.12) | ||
| 1143円(税別) | ||
| 江戸周辺鷹場と御場肝煎制 -化政期を中心に- | 山崎 久登 | |
| 埼玉県杉戸地域の小作争議 -大正デモクラシーの一様相- |
柏浦 勝良 | |
| 二宮尊徳の桜町領仕法と報徳思想の成立 -仕法着手の史料論的研究- |
阿部 昭 | |
| 動向 | ||
| 日本歴史学協会・日本学術会議史学委員会主催史料保存問題シンポジウム 「東日本大震災から二年、資料の救済・保全のこれから」に参加して |
加藤 健 佐藤麻里 |
|
| 全国歴史民俗系博物館協議会第二回年次集会参加報告 | 本間 与之 | |
| 全史料協近畿部会例会「大阪人権博物館の現状と今後の課題」に参加して | 佐藤明俊 嶋田典人 |
|
| 第三九回山形県地域史研究協議会庄内大会参加記 | 長南 伸治 | |
| 埼玉県地方史研究会の歩みと活動 | 田代 脩 | |
| 展示批評 | ||
| 栃木県立博物館開館三〇周年記念特別企画展 「足利尊氏-その生涯とゆかりの名宝-」 |
新井 敦史 | |
| 島根県立古代出雲歴史博物館企画展 「戦国大名尼子氏の興亡」を観て |
西島 太郎 | |
| 研究例会報告要旨 | ||
| 一九世紀初頭の武士の旅と経験 | 中山 学 | |
| 奥能登における真言宗寺院について | 畠山 聡 | |
| 第365号(第63巻5号)(2013.10) | ||
| 1143円(税別) | ||
| <大会特集Ⅱ“伝統”の礎 -加賀・能登・金沢の地域史-> | ||
| 問題提起 | ||
| 17 古代北加賀地域における内水面交通の様相 | 和田 龍介 | |
| 18 「倭の玉器」とコシ | 河村 好光 | |
| 19 板碑研究の現状と課題 -珠洲市野々江本江寺遺跡出土の木製板碑をめぐって- |
三浦 純夫 | |
| 20 能登国守護に関する一考察 -中世の伝統的職制の確立とその変遷- |
北村 周士 | |
| 21 加賀藩の産物方政策と諸産業 | 袖吉 正樹 | |
| 22 加賀藩十村の政治能力と蔵書文化 | 工藤 航平 | |
| 23 「伊能忠敬測量日記」の活用と歴史教育 | 河崎 倫子 | |
| 24 日記にみる幕末期の十村 | 高堀伊津子 | |
| 25 士族福祉論の系譜 -「救貧より防貧」の思潮を生んだ加賀百万石リストラ士族たちの意地- |
平野 優 | |
| 26 加賀門末の真宗信仰 | 太多 誠 | |
| 27 工芸の「伝統」 -阿部碧海の生涯にみる- | 森 仁史 | |
| 嘉永・安政期における京都紅花問屋の取引 -最上屋喜八家文書を中心として- |
森田 昌一 | |
| 動向 日本アーカイブズ学会 博物館・資料館問題 地域研究活動 | ||
| 理論と実務が交わる場 -日本アーカイブズ学会二〇一三年度大会参加記- |
中臺 綾子 | |
| 「ピースおおさかのリニューアルに市民・府民の声を! シンポジウム」参加記 | 田中はるみ | |
| 「ピースおおさかのリニューアルに府民・市民の声を! シンポジウム」と「ピースおおさか見学会」に参加して | 西村 健 | |
| 伊予史談会創立百周年を迎えて | 高須賀康生 | |
| 加能地域史研究会スプリングセミナー参加記 | 田中 丈敏 | |
| 展示批評: | ||
| 館山市立博物館平成24年度特別展 「幕末の東京湾警備」 |
神谷 大介 | |
| 大磯町郷土資料館企画展 「大磯の災害-かつてこの地で起きたこと」 |
水野 保 | |
| 書評 地方史研究協議会第62回大会成果論集 『出羽庄内の風土と歴史像』 |
齊藤 和輝 | |
| 研究例会報告要旨 富士山宝永噴火とその復興過程 | 辻林 正貴 | |
| 第364号(63-4)(2013.08) | ||
| 1143円(税別) | ||
| <大会特集号Ⅰ“伝統”の礎 -加賀・能登・金沢の地域史-> | ||
| 問題提起 | ||
| 1 能登郡与木郷にかんする一試論 | 笹川 尚紀 | |
| 2 中世加賀国倉月荘の「村」 -“伝統”が生まれる場の成り立ち- |
若林 陵一 | |
| 3 中世奥能登の宗教情勢 -奥能登の真言宗寺院- |
宮野 純光 | |
| 4 中世後期能登における七尾・府中の性格と展開 | 川名 俊 | |
| 5 金沢にとって「伝統」とは何か | 長山 直治 | |
| 6 加賀藩研究の素材について | 本多 俊彦 | |
| 7 白山麓の出作り | 山口 隆治 | |
| 8 近世奥能登における伝統産業の盛衰 | 見瀬 和雄 | |
| 9 政治情報活動に見る加賀藩地域社会 | 堀井 美里 | |
| 10 能登の視点 | 奥田 晴樹 | |
| 11 能登七尾の近代にみる「脱・百万石」と「土着の心」 | 市川 秀和 | |
| 12 「繊維王国石川」の形成と「伝統」の存在 | 新本 欣悟 | |
| 13 「軍都」金沢における陸軍記念日祝賀行事についての覚書 | 能川 泰治 | |
| 14 近世の生活文化が残存する金沢 | 小林 忠雄 | |
| 15 近代の神社政策と鵜祭 | 市田 雅宗 | |
| 16 西岸が能登の新たな聖地となるまで -のと鉄道西岸駅の『駅ノート』記帳から- |
由谷 裕哉 | |
| 日本史関係卒業論文発表会特別講座:史料との出会い | 村井 早苗 | |
| 日本史関係卒業論文発表会 参加記 | 佐藤雄一 大貫茂紀 桐生海生 阿部祐也 栗原祐斗 幸田 啓 |
|
| 被災文化財救援活動について考える会 「語ろう!文化財レスキュー」参加記 |
林 貴史 保垣 孝幸 |
|
| 人問文化研究機構災害連携研究報告会 「東日本大震災から二年、津波被害と文化遺産」参加記 |
宇野 淳子 | |
| 全史料協調査・研究委員会主催事業 「アーキビスト専門職問題セミナー」参加記 |
小林 可奈 | |
| 石川県内の諸研究団体の活動 | 道下 勝太 | |
| 展示批評: | ||
| 二つの「美濃路」展 ~豊橋市二川宿本陣資料館とタルイピアセンター~ |
宮川 充史 | |
| 研究例会報告要旨 | 栗原健一 山野井健五 加藤将 |
|
| 訃報 地方文人塚本学先生の歴史学 | 青木 歳幸 | |
| 第363号(第63巻第3号)(2013年6月) | ||
| 1143円(税別) | ||
| 15・16世紀北陸地方における通貨事情 -文献史料と考古資料の観点から- |
小早川裕悟 | |
| 伊達・蘆名領国境と桧原城 | 垣内 和孝 | |
| 第54回日本史関係卒業論文発表会要旨 | ||
| 動向 | ||
| 福島大学うつくしまふくしま未来支援センター設立2周年記念 第6回シンポジウム「ふくしま再生と歴史・文化遺産」参加記 |
渡辺 文久 | |
| シンポジウム「ふくしま再生と歴史・文化遺産」参加記 | 栗原 健一 | |
| 平成二十四年度千葉県美術館・博物館等職員研究会兼公開シンポジウム「博物館資料はなぜ救済されなければならないのか?-東日本大震災の教訓-」に参加して | 菅野 洋介 | |
| ピースおおさか展示リニューアル問題 | 小田 康徳 | |
| 2012年度陵墓立入り観察について参加報告記 -箸墓古墳・西殿塚古墳- | 斉藤 進 | |
| 石川県五学会連合研究発表会 | 河村 好光 | |
| 展示批評 葛飾区制施行八〇周年記念特別展 「東京低地災害史 地震、雷、火事?…教訓!」を観て | 渡部 恵一 | |
| 研究例会報告 | ||
| 仙台藩廻米体制における穀宿の機能 | 井上 拓巳 | |
| 天明三年浅間焼け絵図にみる構図の変化とランドマーク | 福重 旨乃 | |
| 福島県警戒区域の再興を担う博物館の復興・再生に向けて(提言) | ||
| 第362号(第63巻2号) (2013.04) | ||
| 1143円(税別) | ||
| 加賀藩上級家臣団の職掌と職名の変化について -貞享三年の職制改革後を対象として- | 林 亮太 | |
| 発智長芳と上杉氏権力 | 大貫 茂紀 | |
| 動向 | ||
| 第38回全史料協全国(広島)大会参加記 | 宮田 克成 | |
| 第38回全史料協全国(広島)大会で思ったこと -管理条例・「人」の問題・組織- | 伊藤 康 | |
| 「全国図書館大会 資料保存分科会」に参加して | 千 錫烈 | |
| 群馬県立文書館30周年記念シンポジウム参加記 | 新井 浩文 | |
| 第10回日本の地域博物館シンポジウム 「学芸員の地域的活動について」に参加して |
中岡 貴裕 | |
| 土師ニサンザイ古墳(東百舌鳥陵墓参考地)限定公開 参加記 | 家塚 智子 | |
| 第5回四国地域史研究連絡協議会愛媛大会 「山岳信仰と四国遍路」参加記 |
徳野 隆 | |
| 北陸都市史学会の活動 | 塩川 隆文 | |
| 研究例会報告要旨 | ||
| 伊豆安山岩製の中世石塔について | 本間 岳人 | |
| 明治前期における在地修験の動向 -埼玉県高麗郡の事例から- |
酒井 麻子 | |
| 訃報 西垣晴次さんと地方史研究協議会 | 有元 修一 | |
| 第361号(第63巻第1号) (2013.02) | ||
| 1143円(税別) | ||
| 「院外青年」と地域係争問題 -橋本徹馬と愛媛県新居郡における産米検査問題を事例として- |
伊東 久智 | |
| 船木氏小論 -能登を中心として- | 笹川 尚紀 | |
| 羽柴秀保と一庵法印 | 北堀 光信 | |
| 2012年度(第63回)東京大会参加記 | 小笠原孝起 栗原祐斗 堀井美里 宮川充史 和田 学 長澤慎二 |
|
| 動向 | ||
| 日本歴史学協会報告 | 佐藤 孝之 | |
| シンポジウム「東日本大震災から一年、資料の救済・保全の在り方を考える」に参加して | 渡部恵一 工藤航平 |
|
| 神奈川県地域史研究会シンポジウム「地域史と博物館」に参加して | 乾 賢太郎 | |
| 加賀藩研究ネットワークの活動 | 堀井 美里 | |
| 展示批評 | ||
| 八代市立博物館未来の森ミュージアム特別展覧会 入城四〇〇年記念「八代城主・加藤正方の遺産」を観て | 鍋本 由徳 | |
| 第360号(第62巻第6号) (2012.12) | ||
| 1143円(税別) | ||
| 中近世移行期の遠州井伊谷龍潭寺 -無縁所の役割と地域社会- |
夏目 琢史 | |
| 公家家来と百姓の壱人両名 -大島数馬と利左衛門- |
尾脇 秀和 | |
| 豊後大友氏の官途授与体系 | 風間 幸 | |
| 動向 陵墓問題 史料保存問題 地域研究活動 | ||
| 春日向山古墳・山田高塚古墳の立入り観察参加記 | 川上 真理 | |
| 歴史資料ネットワークシンポ「歴史遺産と資料を守りぬく」に参加して | 桜井 昭男 | |
| 四国中世史研究会創立30周年記念公開シンポジウム | ||
| 「四国をめぐる戦国期の諸相」に参加して | 磯川いづみ | |
| 能登文化財保護連絡協議会の活動 | 和田 学 | |
| 訃報 山本幸俊さんを偲ぶ | 浅倉 有子 | |
| 第359号(第62巻第5号) (2012.10) | ||
| 1143円(税別) | ||
| <大会特集Ⅱ 地方史、その先へ-再構築への模索-> | ||
| 問題提起 | ||
| 19 住民と区立博物館の関係から -足立区の事例- |
多田 文夫 | |
| 20 地域博物館における循環型活動をめざして -千代田区の事例から- |
滝口 正哉 | |
| 21 地域住民にむきあう -名古屋市博物館の取り組み- |
岡村 弘子 | |
| 22 江東区文化財保護推進協力員制度と活動領域の展開 | 斉藤 照徳 | |
| 23 文化財行政と地域文化の再生産 -杉並区文化財保護ボランティアの活動の試み- |
野本 禎司 | |
| 24 地方史活動と文書館の現状 -千葉県文書館の活動を通じて- |
高橋 伸拓 | |
| 25 大河ドラマと地方史研究 | 工藤 航平 | |
| 26 江戸時代地方史の研究をめぐる二つの情報ネットワーク -瀬戸内海域における異国船対応史の視点から- | 鴨頭 俊宏 | |
| 27 東京大空襲における被害の実態解明と焼失した地域の構造を復元する試み | 西村 健 | |
| 朝鮮通信史乗馬役と加賀藩前田家 -正徳・享保期の鞍置馬派遣を中心に- |
横山 恭子 | |
| シンポジウム 災害と歴史資料の保存 -何のため・誰のために遺すのか- |
||
| 基調報告:地域・ふろさと、そして歴史資料 | 小田 康徳 | |
| 震災発生後一年、被災地における資料保存の現状と課題 | 本間 宏 | |
| 歴史資料の調査と自治体の役割 | 平井 義人 | |
| シンポジウム「災害と歴史資料の保存」によせて | 澤村 怜薫 | |
| シンポジウム「災害と歴史資料の保存」について | 吉田 優 | |
| シンポジウム「災害と歴史資料の保存」に参加して | 小島 道裕 | |
| 動 向 | ||
| 東日本大震災における香取市の文化財の被災状況と復興への取り組み | 川口 康 | |
| 全国歴史民俗系博物館協議会設立集会・第一回研究集会に参加して | 実松 幸男 | |
| 「東日本大震災における津波被災文書の救助・復旧活動とその意義」参加記 | 山本あづさ | |
| 加能地域史研究会の活動 | 石田 文一 | |
| 研究例会報告要旨 | 矢内信悟 後藤禎久 稲葉和也 |
|
| 第358号(第62巻第3号) (2012.08) | ||
| 1143円(税別) | ||
| <大会特集Ⅰ 地方史、その先へ -再構築への模索-> 第63回大会を迎えるにあたって | 大塚 紀弘 | |
| 問題提起 | ||
| 1 四国の地方史・地域史を考える -四国地域史研究連絡協議会の試み- | 胡 光 | |
| 2 信濃史学会の現状と課題 | 山浦 寿 | |
| 3 歴史系施設における地域横断型ネットワークの重要性 | 松本 洋幸 | |
| 4 佐田岬半島の「地方史活動」模索 | 高嶋 賢二 | |
| 5 郷土資料館における「地方史活動」の取組みと課題 -北海道江差町の事例- | 宮原 浩 | |
| 6 生きられる歴史/モノごとの歴史 | 平井 太郎 | |
| 7 観光地の中の地域博物館 -日常と非日常の狭間で- | 保科 智治 | |
| 8 「地方史活動」の一拠点として | 米澤 英昭 | |
| 9 中世惣国復活プロジェクト -フィールドミュージアムの試み- | 海津 一朗 | |
| 10 地方史は理解されていくか? -就実大学吉備地方文化研究所の難問- | 苅米 一志 | |
| 11『新修彦根市史』(第十巻 景観編)の試み -「市民の市史」をめざして- | 小林 隆 | |
| 12「低成長時代」の自治体史編さんと地域への役割 -青森県史を事例に- | 中野渡一耕 | |
| 13 地方における埋蔵文化財の保存と活用 | 栗山 葉子 | |
| 14 東京都立高校における地域史学習の動向 -東京都設定科目「江戸から東京へ」の導入も視野に入れて- | 加藤 健 | |
| 15 博物館と学校、及び小中高学校間の連携について | 深田富佐夫 | |
| 16 一歴史系クラブのささやかな活動紹介 | 風間 洋 | |
| 17 漁業史研究からみる環境史研究への展望 | 高橋 美貴 | |
| 18 東日本大震災避難所資料の収集・保存 -新潟県長岡市の事例から- | 田中 洋史 | |
| 第53回日本史関係卒業論文発表会 特別講座 | ||
| 研究テーマの設定と地域史 | 上山 和雄 | |
| 第53回日本史関係卒業論文発表会参加記 | 山脇智佳・西村直亮・岩田愛加・秋山寛行・田中幸加・手塚雄太 | |
| 日本アーカイブズ学会2012年度大会参加記 | 太田 尚宏 | |
| 群馬県地域文化研究協議会の大会 | ||
| 「地方史研究の最前線パートⅡ -群馬の中世史-」に参加して | 浅倉 直美 | |
| 文化財石垣への関心と石垣技術史の最前線 -シンポジウム「城郭石垣の技術と組織を探る」の成果から- | 木越 隆三 | |
| 書評 地方史研究協議会成田大会成果論集『北総地域の水辺と台地』 | 酒井 右二 | |
| 研究例会報告要旨 | 藤野 敦・大嶌聖子・ 井上 崇・坂井飛鳥 |
|
| 第357号(第62巻第3号) (2012.06) | ||
| 1143円(税別) | ||
| 鎌倉極楽寺流律家の西国展開 -播磨国報恩寺を中心に- |
大塚 紀弘 | |
| 赤報隊「魁塚」と丸山久成 | 岩立 将史 | |
| 第53回日本史関係卒業論文発表会要旨 | ||
| 動向(日本歴史学協会/史料保存・利用問題/史料保存問題/陵墓問題) | ||
| 博物館法制定60周年記念シンポジウムを聞いて | 田辺 龍太 | |
| 地域博物館は誰のものか? -「博物館法制定60周年記念シンポジウム地域博物館の現状と今後の課題」に参加して- |
竹村 到 | |
| アジア歴史資料センター設立10周年記念シンポジウム参加記 | 新井 浩文 | |
| フクシマから学ぶ歴史資料の保存と地方史研究 -地域史研究講習会「災害と向き合い歴史に学ぶ」に参加して- |
白井 哲哉 | |
| 百舌鳥陵山古墳外構柵改修工事にともなう立会見学会参加記 | 播磨 良紀 | |
| 訃報 吉原健一郎氏の訃 | ||
| 第356号 (2012.04) | ||
| 1143円(税別) | ||
| 熊本県における郡役所文書の管理 | 丑木 幸男 | |
| 永享・嘉吉期の伊予西園寺氏の確執と幕府権力 | 山内 治朋 | |
| 出雲国の氏族の地域性 -『出雲国風土記』を中心に- |
中村 友一 | |
| 動向(全国図書館大会 全史料協 陵墓問題 地域研究活動) | ||
| 知を守り、伝えていくこと -第97回「全国図書館大会」に参加して- |
飯村はるか | |
| 第37回全史料協全国(群馬)大会参加記 -実践的報告を期待して- |
田渕 正和 | |
| 全史料協全国大会にみる資料救援の課題と展望 | 関口真規子 | |
| 奈良県郡山市新木山古墳(郡山参考地)発掘調査の見学(限定公開)参加記 | 小谷 利明 | |
| 大仙陵古墳(仁徳天皇陵)前百舌鳥部事務所改築地区の発掘調査立会見学会 | 長沼 秀明 | |
| 第4回四国地域史研究連絡協議会高知大会「四国の自由民権運動」参加記 | 野村 美紀 | |
| 展示批評 品川歴史館特別展「品川御台場-幕末期江戸湾防御の拠点-」 | 横山考之輔 | |
| 研究例会報告要旨 | ||
| 弘前藩江戸日記の管理と日記役 | 中野 達哉 | |
| 福岡藩の記録仕法と記録管理 | 江藤 彰彦 | |
| 第355(62-1)号 (2012.02) | ||
| 1143円(税別) | ||
| 化政期における羽州幕領廻米と酒田湊 -郡中惣代の「湊渡切」要求と実際- |
横山 昭男 | |
| 南方熊楠と和歌山城保存運動 | 雲藤 等 | |
| 2011年度(第62回)庄内大会・総会報告 | ||
| 2011年度(第62回)庄内大会参加記 | 岩井美樹 小田直寿 袖吉正樹 阿部靖子 吉岡拓 長谷川幸一 |
|
| 日本歴史学協会報告 | 佐藤 孝之 | |
| 歴史学と博物館のありかたを考える会8月例会 | ||
| 「2008年に行われた博物館法の改正を考える」参加記 | 桑原 功一 | |
| 展示批評 北区飛鳥山博物館企画展 | ||
| 「天明以来ノ大惨事-明治43年水害と岩淵」を観て | 吉田 優 | |
| 第354(61-6)号 (2011.12) | ||
| 1143円(税別) | ||
| 近世国境争論にみる佐賀藩領主と地域信仰 -脊振弁財嶽国境争論を素材として- |
田中由利子 | |
| 宮崎県における青年訓練所について | 竹村 茂紀 | |
| 東寺領山城国植松荘の伝領と相論 | 松園潤一朗 | |
| シンポジウム 歴史資料の保存と地方史研究 | ||
| 地方史研究の現状と課題 | 桜井 昭男 | |
| 全国アンケートから見えてきた地域資料の保存状況 | 福嶋 紀子 | |
| 自治体史編さん事業後の動向と自治体史の再検証 -北区立中央図書館における地域資料の保存・活用- |
保垣 孝幸 | |
| 広域ネットワークによる地域史料の保存と地方史研究 -県境を越えた結びつきから- |
松下 師一 | |
| 参加記 | 佐藤勝巳 高野弘之 菅野将史 |
|
| 「史料保存利用問題シンポジウム」に参加して -新たな史料保存運動の出発点- |
岡田 昭二 | |
| 国立歴史民俗博物館・財団法人歴史民俗博物館振興会主催 特別集会「被災地の博物館に聞く」に参加して |
立野 晃 | |
| 相馬中村城の堀跡保存にご支援を! -北日本近世城郭検討会開催される- |
岡田 清一 | |
| 展示批評 | ||
| 都営交通100周年記念特別展 「東京の交通100年博~都電・バス・地下鉄の“いま・むかし”~」を見て |
奥原 哲志 | |
| 研究例会報告要旨 | 服部浩平 松野聡子 芳賀和樹 |
|
| 第353(61-5)号 (2011.10) | ||
| 1143円(税別) | ||
| <大会特集Ⅱ 出羽庄内の風土と歴史像-その一体性と多様性-> | ||
| 問題提起 | ||
| 古代の庄内と越後 | 相沢 央 | |
| 近世から近代にかけての飛島における「生業知」 | 中村 只吾 | |
| 庄内藩の幕末史の再検討として | 今野 章 | |
| 庄内狩川通の民間育種家について | 日野 淳 | |
| 協議体としての庄内会について | 谷口 裕信 | |
| 庄内地方のモリ供養 | 大塚 幹士 | |
| 庄内地方の漁民と海の信仰 | 阿部 友紀 | |
| 出羽国における善光寺信仰 | 牛山 佳幸 | |
| 地域史・伝説と地域社会の歴史「解釈」 -肥前後藤氏の歴史的展開と為朝伝説- | 宮島 敬一 | |
| 但馬国幕領における安石代の軌跡 | 宿南 保 | |
| 動向(地域研究活動 日本アーカイブズ学会 史料保存問題 動向レポート) | ||
| 庄内民俗学会について | 本間 豊 | |
| 日本アーカイブズ学会2011年度大会をきいて -今日の記録を明日の史料とするために- |
宇野 淳子 | |
| 『広がりゆく「デジタルアーカイブ」とアーカイブズ』に参加して | 小池真理子 | |
| 「大災害における文化財の救出・保全を考える緊急集会」見学記 | 富澤 達三 | |
| 「東日本大震災 茨城の文化財・歴史資料の救済・保全のための緊急集会 -文化財・歴史資料の救済のために、いま、何ができるのか-」参加記 | 川上 真理 | |
| 「日本アーカイブズ学会登録アーキビスト(仮称)」の資格認定制度創設について | 文書館問題検討委員会 | |
| 研究例会報告要旨 | ||
| 天保期秋田藩における感恩講の活動に関する一考察 | 塩屋 朋子 | |
| 訃報 村井益男氏の訃 | 竹中 眞幸 | |
| 第352号 (2011.08) | ||
| 1143円(税別) | ||
| <大会特集Ⅰ 出羽庄内の風土と歴史像-その一体性と多様性-> | ||
| 問題提起 | ||
| 出羽国成立前後の庄内地域 | 川崎 利夫 | |
| 新史料に見る中世庄内と他地域の交流 | 秋保 良 | |
| 出羽庄内は「上杉領」なり -中世の越後と庄内をめぐる交流と地域感覚- |
長谷川 伸 | |
| 近世庄内浜の漁村 | 前田 光彦 | |
| 庄内と最上との関係 -二つの峠道のこと- | 佐久間 昇 | |
| “象潟地震”の謎 -そのとき、鳥海山は噴火したか- |
土岐田正勝 | |
| 三方領地替反対一揆における“一体制”と“多様制” | 岩淵 令治 | |
| 明治期庄内の青春群像 | 阿部 博行 | |
| 災害は歴史を変えるか -明治二七年庄内地震を巡って- |
北原 糸子 | |
| 庄内地域史の検証と再構築 -実証的研究への第一歩- |
三原 容子 | |
| ワッパ騒動の研究の進展 | 星野 正紘 | |
| 出羽三山信仰の諸課題 | 岩鼻 通明 | |
| 第52回日本史関係卒業論文発表会 特別講座 | ||
| 地域からの発信を -仲間に支えられた私の地方史研究を顧みて- |
橋詰 茂 | |
| 第52回日本史関係卒業論文発表会 参加記 | 小川 雄・望月保宏 稲松朋子・藤方博之 須田剛広・櫻庭茂大 |
|
| 庄内町郷土史研究会について | 小野寺 裕 | |
| 展示批評 | ||
| 埼玉県立歴史と民俗の博物館特別展「皇女和宮と中山道」を見て | 西 光三 | |
| 書評 地方史研究協議編『南九州の地域形成と境界性』 | 米澤 英昭 | |
| 研究例会報告要旨 | 生駒哲郎 矢嶋毅之 |
|
| 地方史の窓/新刊案内/復興への声/受贈図書論文要目 | ||
| 第351(61-3)号 (2011.06) | ||
| 1143円(税別) | ||
| 新潟奉行川村修就の海防体制の確立過程について | 中野 三義 | |
| 幕府屋敷改による百姓商売家の把握と規制 -将軍家鷹場鳥見との関係に注目して- |
宮坂 新 | |
| 第52回 日本史関係卒業論文発表会 要旨 | ||
| 文化財保護をめぐる諸問題の検証と今後の課題 | 瀧沢 典枝 | |
| シンポジウム「文化財保護法制定60年と歴史学」に参加して | 鈴木 由美 | |
| 「雄略天皇陵」外構柵整備その他工事にともなう調査見学参加記 | 鍋本 由徳 | |
| 2010年度陵墓立入り観察について -誉田御廟山古墳(現応神陵)- |
斉藤 進 | |
| 「酒田古文書同好会」について | 土岐田正勝 | |
| 研究例会報告要旨 | ||
| 第350号 (2011.04) | ||
| 1143円(税別) | ||
| <小特集 地方史研究の現在> | ||
| 自治体史編さんと地方史研究覚えがき | 横山 昭男 | |
| 沖縄県における地方史研究の現在 | 恩河 尚 | |
| 三重県における近年の自治体史編纂 | 上野 秀治 | |
| 古文書を千年後まで残すために | 平川 新 | |
| 多摩の地域史研究と資史料 | 保坂 一房 | |
| 福岡県の地方史研究の現状 | 石瀧 豊美 | |
| 首都圏の地方史-埼玉から | 太田 富康 | |
| 地方史研究の現在-北方史 | 榎森 進 | |
| 栃木県に於ける地方史研究を回顧する | 阿部 昭 | |
| 地方史研究の現在-和歌山県 | 小山 譽城 | |
| 富山県の地域史研究の現状 | 深井 甚三 | |
| 神奈川県地方史研究の現在-三つの視点から | 馬場 弘臣 | |
| 地方史研究の現在-大阪 | 尾崎 安啓 | |
| 21世紀歴史研究の構築に向けて-長野県の場合 | 武田 安弘 | |
| 地方史研究と自治体史編纂-広島県 | 中山 富広 | |
| 東京23区北部地域の地域史研究について | 秋山 伸一 | |
| 地域の歴史団体の連携と活性化-八戸市 | 三浦 忠司 | |
| 近藤義雄先生卒寿記念論集-群馬県 | 丑木 幸男 | |
| 第56回敦賀大会後の福井県における地方史研究の動向 | 多仁 照廣 | |
| 静岡県の地域史研究の現状 | 森田 香司 | |
| 四国の地方史研究 | 胡 光 | |
| 茨城県の地方史研究の現状と課題 | 久保田喜一 | |
| 研究活動のネットワークを進める戦略を-宮崎県 | 籾木 郁朗 | |
| <動向> | ||
| 新木山古墳(三吉陵墓参考地)限定公開報告 | 茂木 雅博 | |
| 新木山古墳発掘調査見学会参加記 | 谷口 榮 | |
| これからの文書館像の模索 -第36回全史料協全国大会に参加して- |
秋山 正典 | |
| 全史料協京都大会参加記 -公文書管理法施行を追い風にするために- |
島津 良子 | |
| 庄内歴史懇談会について | 阿部 博行 | |
| 第349号 第61巻1号(2011.02) | ||
| 1143円(税別) | ||
| 江戸幕府道奉行の成立と職掌 | 松本剣志郎 | |
| 明治前期の遊学に対する漢学塾の取り組み -新潟県西蒲原郡長善館を対象として- |
池田 雅則 | |
| 2010年度(第61回)大会・総会報告 | ||
| 第61回(成田)大会参加記 | 上田 浄 横山考之輔 菅原義勝 岡村龍男 今野 章 佐藤雄太 |
|
| 動向 | ||
| 歴史資料保存・活用機関としての図書館 -第96回「全国図書館大会(奈良大会)」に参加して- |
保垣 孝幸 | |
| 「地域資料をめぐる図書館とアーカイブズ」を聞いて | 山上 豊 | |
| 研究例会報告要旨 | ||
| 成田地域における地方史研究の新展開 | 白井 哲哉 | |
| 下総飯岡村大河平兵衛について | 深田富佐夫 | |
| 第348号(2010.12) | ||
| 1143円(税別) | ||
| 明治三年遠州「大池事件」と静岡藩 | 杉山 容一 | |
| 在地領主としての東国豪族的武士団 -畠山重忠を中心に- |
清水 亮 | |
| 中国山地における役牛の売買流通過程 -牛馬商の専門分化と階層構造に関する分析- |
坂垣 貴志 | |
| 動向 | ||
| 国文学研究資料館におけるアーカイブズ学関係の研究と事業 | 国文研アーカイブズ学関連教員一同 | |
| 越佐地方談話会の活動について | 本山 幸一 | |
| 第3回 四国地域史研究連絡協議会徳島大会シンポジウム | ||
| 「近代四国における戦争と地域社会」参加記 | 西村 健 | |
| 展示批評 | ||
| 杉並区立郷土博物館特別展「大田黒元雄の足跡-西洋音楽への水先案内人-」 | 竹村 誠 | |
| 研究例会報告要旨 | 中山 学 | |
| 水戸藩領における育子政策の展開 | 高村 恵美 | |
| 第347号(2010.10) | ||
| 1143円(税別) | ||
| <大会特集Ⅱ 北総地域の水辺と台地-生活空間の歴史的変容-> | ||
| 問題提起 | ||
| 印旛沼周辺地域における弥生後期土器研究の課題 | 高花 宏行 | |
| 「香取の海」を基盤とした中世の権力と文化 | 外山 信司 | |
| 近世初期の開発をめぐる争論と裁許 -成田地域周辺を中心に- |
宮原 一郎 | |
| 近世北総の地域的特質 | 出口 宏幸 | |
| 利根川流域の山岳信仰 -大山信仰をめぐって- |
西海 賢二 | |
| 三方領知替事件における川越藩 -幕藩領主と「人気」- |
上白石 実 | |
| 村落共同における医師の役割 -変死隠蔽事件を事例として- | 尾脇 秀和 | |
| 〔動向〕文化財保存問題 日本アーカイブズ学会 資料館紹介 地域研究活動 | ||
| 「十条冨士塚」の保全をめぐって | 中山 学 | |
| 「日本アーカイブズ学会二〇一〇年度大会」参加記 | 富田 健司 | |
| 大原幽学記念館について | 猪野映里子 | |
| 成田市文化財保護協会について | 小倉 博 | |
| 〔研究例会報告要旨〕 | ||
| 江戸周辺鷹場と御場肝煎制 -化政期を中心に- |
山崎 久登 | |
| 第346号(2010.08) | ||
| 1143円(税別) | ||
| <大会特集Ⅰ 北総地域の水辺と台地-生活空間の歴史的変容-> |
||
| 問題提起 | ||
| 北総地域における古式須恵器 | 佐藤 晃雅 | |
| 成田市江川流域の古墳について | 仲村 元宏 根本 岳史 |
|
| 北総荘園の変容と印西内外十六郷の成立 -房総中世村落論の一課題- |
湯浅 治久 | |
| 香取本「大江山絵詞」の伝来と北総地域 | 鈴木 哲雄 | |
| 在方町佐原からみた近世地域文化試論 | 酒井 二右 | |
| 佐倉藩政史研究の現状と課題 -下総佐倉堀田家文書を中心として- |
土佐 博文 | |
| 佐原から考える平田国学 | 小田 真裕 | |
| 門前町成田と成田鉄道 | 矢嶋 毅之 | |
| 堀田伯爵家と近代北総地域 | 宮間 純一 | |
| 取香牧から取香種畜場へ、さらに下総御料牧場へ | 鏑木 行廣 | |
| 北総台地と国策 | 中村 政弘 | |
| 社会事業と成田山新勝寺 | 中澤 恵子 | |
| 私の地方史研究とアーカイブズ | 高橋 実 | |
| 第51回日本史関係卒業論文発表会 参加記 | ||
| 印旛郡市地域史料保存利用連絡協議会について | 小池 康久 | |
| 常総地方史研究会のこと | 荒井 信司 | |
| 書評『茨城の歴史的環境と地域形成』 | 木塚 久子 | |
| 第345号(2010.06) | ||
| 1143円 | ||
| 盛岡藩における元禄十六年「新法」事件について |
蝦名 裕一 | |
| 幕府広域役の負担原則と地域社会 -琉球使節淀川通航時の綱引役を事例として- |
飯沼 雅行 | |
| 第51回日本史関係卒業論文発表会要旨 | ||
| シンポジウム 基礎的自治体の博物館・資料館の「使命と役割」 「基礎的自治体の博物館・資料館の「使命と役割」~地方史研究協議会版 評価基準作成へ向けて~」開催にあたって |
博物館・資料館問題検討委員会 | |
| 博物館評価制度の導入は改善か改悪か | 水嶋 英治 | |
| 地域における基礎的自治体立博物館・資料館の「使命と役割」 | 桑原 功一 | |
| 教育現場からみた博物館・資料館の可能性 | 藤野 敦 | |
| シンポジウム参加記 | 千枝 大志 | |
| 第29回「陵墓」限定公開 コナベ古墳見学会参加記 | 大嶌 聖子 | |
| 房総のむら(風土記の丘資料館)について | 千葉県立房総のむら | |
| 展示批評 安城市歴史博物館企画展「徳川家康の源流 安城松平一族」 | 堀江登志実 | |
| 企画例会「シリーズ地方史の現場」報告要旨 | 蛭田廣一 庄司明由 三野行徳 |
|
| 研究例会報告要旨 | 北村厚介 野本禎司 |
|
| 第344号(2010.04) | ||
| 1143円 | ||
| 戊辰戦争期における「草莽隊」の志向 -下野国利鎌隊を事例として- |
宮間 純一 | |
| 元禄期加賀前田家における諸大夫家臣の再興とその意義 | 清水 聡 | |
| 嘉永二年の年番辞退申し出にみる宿組合の問題点 | 橘 敏夫 | |
| 公文書館機能と自助の精神 -第35回全史料協全国大会(福島大会)の意味するもの- |
富永 一也 | |
| 公文書管理の現状について -第35回全史料協全国大会(福島大会)に参加して- |
藤井 康 | |
| シンポジウム「ふるさと濃飛の歴史」に参加して -一利用者の雑感- |
高橋 伸拓 | |
| 地域史研究の担い手による相互交流の重要性 -シンポジウム「地域史研究の交流と未来」参加記- |
宮坂 新 | |
| 第343号(2010.02) | ||
| 1143円 | ||
| 武田親族衆穴山信君の江尻領支配 |
柴辻 俊六 | |
| 近世後期の「離檀」をめぐる権力・寺院・民衆 | 林 宏俊 | |
| 2009年度(第60固)大会・総会報告 | ||
| 第60回(都城)大会参加記 | ||
| 立入り成果報告シンポジウム後の陵墓運動の動向 | 谷口 榮 | |
| 陵墓関係16学協会「陵墓限定公開」30周年記念事業シンポジウム | ||
| 「陵墓公開運動の30年の総括と展望」に参加して | 生駒 哲郎 | |
| 「陵墓」の公開化と多面的価値の模索について | 斉藤 進 | |
| シンポジウム「文化財と史料保存問題を考える」参加記 | 福島 幸宏 | |
| シンポジウム「地域の史料保存と人材育成-その現状と課題-」参加記 | 佐藤正三郎 | |
| 第二回四国地域史研究大会シンポジウム | ||
| 「四国の大名-大名の交流と文化-」参加記 | 清水 邦俊 | |
| 展示批評:横浜歴史博物館・開港150周年記念特別展 | ||
| 「海賊-室町・戦国時代の東京湾と横浜-」 | 風間 洋 | |
| 企画例会「シリーズ:地方史の現場」報告要旨 | ||
| 第342号(2009.12) | ||
| 1143円 | ||
| 日露戦後の町村合併問題 -石川県の事例から- |
山本 吉次 | |
| 鎌倉前期における谷の開発と畠地 -備中国新見荘を題材として- |
渡邊 太祐 | |
| 寛永巡見使国絵図の記載内容とその成立時期 -美濃国を事例として- |
永井 哲夫 | |
| 動 向 | 松本 洋幸 | |
| 「Archives Japan50 -アーカイブズ学からの照射-」参加記 |
大石三紗子 | |
| 日本歴史学協会報告 | 佐藤 孝之 | |
| 「公文書等の管理に関する法律」の成立によせて | 学術体制小委員会 | |
| 展示批評 国立公文書館展示「旗本御家人-江戸を彩った異才たち-」 | 坂本 達彦 | |
| 研究例会報告要旨 豊臣政権と相良氏 | 丸島 和洋 | |
| 訃報 田中喜男氏の訃 | 村上 直 | |
| 第341号(2009.10) | ||
| 1143円 | ||
| 大会特集Ⅱ 南九州の地域形成と境界性-都城からの歴史像- 問題提起 |
||
| 古墳時代竪穴住居内「火処」からみた都城盆地の位相 | 今塩屋毅行 | |
| 島津荘の成立をめぐる諸問題 | 桑畑 光博 | |
| 四国遍路・修験者の文化・情報・技術交流試論 -四国と南九州との関連を中心にして- |
西海 賢二 | |
| 牧民官・有吉忠一と宮崎県 | 松本 洋幸 | |
| 中世後期南九州の村と町-『庄内地理志』を中心に- | 福島 金治 | |
| 朝鮮通信使への接待と情報収集 -伊予国津和地島を中心として- |
玉井 建也 | |
| 中世後期における如法経信仰と地域的生業 -摂津国勝尾寺を事例として- |
小山 貴子 | |
| 動向 資料館問題 岐阜県歴史資料館の機能縮小について | 森田 晃一 | |
| 動向 学会活動 宮崎考古学会の活動について | 松林 豊樹 | |
| 展示批評 すみだ郷土文化資料館開館十周年記念特別展 | ||
| 「隅田川文化の誕生-梅若伝説と幻の町・隅田宿-」 | 斉藤 照徳 | |
| 研究例会報告 埼玉県比企地域における武蔵型板碑の様相 | 村山 卓 | |
| 第340号(2009.8) | ||
| 1143円 | ||
| <大会特集 南九州の地域形成と境界性-都城からの歴史像-1> 第60回大会共通論題 問題提起 |
||
| 1 南九州縄文時代早期の貝殻文円筒形土器と押型文土器の関係について | 山下 大輔 | |
| 2 東・南九州における弥生土器の様式構造からみた都城盆地の位相 | 加覧 淳一 | |
| 3 古代都城盆地の地域性と境界性 | 栗山 葉子 | |
| 4 出土文字資料からみた古代の諸県郡 | 柴田 博子 | |
| 5 対外貿易と都城 | 小山 博 | |
| 6 九州の「奥三ケ国」と「山東」 | 若山 浩章 | |
| 7 天正~慶長期における島津氏の港津支配 | 米澤 英昭 | |
| 8 豊臣政権と日向国-日向の大名配置をめぐって- | 増田 豪 | |
| 9 庄内地域の境界性と一向宗禁教 | 西 光三 | |
| 10 鹿児島藩・天保度の一向宗取締り -自訴不罰・宗旨替えを中心とした取締り- |
所崎 平 | |
| 11 日向四藩と薩摩藩における六十六部対応の相違について | 前田 博仁 | |
| 12 「都城ヲ鹿児島県ニ復セン事ヲ」-明治一八年の管轄替運動- | 武田 信也 | |
| 13 「田の神講」文書取り扱いの視座について | 森田 清美 | |
| 第50回日本史関係卒業論文発表会 特別講座 歴史研究と地域活動 | 三浦 忠司 | |
| 第50回日本史関係卒業論文発表会 参加記 | ||
| 動向 史料保存問題:「二度目の震災」から一年 -岩手・宮城内陸地震での歴史資料保全活動の成果と課題- |
佐藤 大介 | |
| 学会活動:鹿児島地域史研究会について | 栗林 文夫 | |
| 展示批評:歴史資料としての可能性をひらく -「美しき九州の旅-「大正広重」初三郎が描くモダン紀行」- |
有馬 学 | |
| 研究例会報告要旨 頭役祭祀の差定書と頭人帳-宮座における頭人の選定基準とその変化- |
渡部 圭一 | |
| 訃報 若林淳之先生を悼む | 小和田哲男 | |
| 第339号(2009.06) | ||
| 1143円 | ||
| 近世後期における高野山参詣の様相と変容 -相模国からの高室院参詣を中心に- |
佐藤 顕 | |
| 近代労働力移動の地域的展開 -明治中期における香川県の出稼ぎと移住- | 嶋田 典人 | |
| 第50回日本史関係卒業論文発表会要旨 | ||
| 動向 博物館問題 自治体史 学会活動 | ||
| 地域博物館とは? そして「日本」の学芸員とは? | 石山 秀和 | |
| 全日本博物館学会 2008年度 第3回研究会 「あらためて考える 博物館の存在価値とコレクション」 |
鎮目 良文 | |
| 横浜市史から横浜市史資料室へ | 羽田 博昭 | |
| 「開港期の相武地域史研究会」について | 馬場 弘臣 | |
| 隼人文化研究会について | 永山 修一 | |
| 展示批評 | ||
| “深化”する展示「一粒入魂!-日本の農業をささえた種子屋-」を見て | 平野 恵 | |
| 書評 | ||
| 地方史研究協議会編「歴史に見る四国-その内と外と-」 | 川岡 勉 | |
| 研究例会報告要旨 | ||
| 第338号(2009.04) | ||
| 1143円 | ||
| 近世の旅先地域と諸営業 -上野国吾妻郡草津村を事例に- |
高橋 陽一 | |
| 利根川中流域における河道変遷の再検討 -16世紀後半から17世紀前半を中心に- |
橋本 直子 | |
| 三方楽所の成立と南都楽人 | 北堀 光信 | |
| 動向 | ||
| ・文書館問題に関する会員への意見募集の結果について | 文書館問題 検討委員会 |
|
| ・宮崎県地域史研究会について | 籾木 郁朗 | |
| ・「史料は死料にあらず」と再嚥下 -全史料協第34回全国大会参加記- |
大木祥太郎 | |
| ・アーカイブズのこれまでとこれから -第34回全史料協全国大会参加記- |
烏野 茂治 | |
| ・百舌鳥御廟山古墳(百舌鳥陵墓参考地)事前調査の見学について | 学術体制 小委員会 |
|
| 研究例会報告要旨 | 水野伍貴 石井里枝 |
|
| 第337号(2009.02) | ||
| 1143円 | ||
| 工場委員会と企業城下町形成 -戦間期の釜石製鉄所真道会と地域を中心に- |
松石 泰彦 | |
| 近世後期における朝廷の意思決定過程 -尊号一件を事例として- |
長澤 慎二 | |
| 第59回(茨城)大会参加記 | ||
| 四国地域史研究連絡協議会の発足について | 武智 利博 | |
| 展示批評 萩博物館特別展「明治維新の光と影」 | 落合 弘樹 | |
| 研究例会報告要旨 | ||
| 第336号(2008.12) | ||
| 1143円 | ||
| 地租改正における地価決定と収穫高 -広島県恵蘇郡奥門田村を事例として- |
中山 富広 | |
| 武田氏の駿河侵攻と徳川氏 | 小笠原春香 | |
| 文明・明応期の但馬の争乱について -山名政豊父子と垣屋氏- |
片岡 秀樹 | |
| 練馬区郷土資料室特別展「『講』ってなあに?」によせて | 西海 賢二 | |
| 研究例会要旨/提言・緊急声明/地方史の窓/新刊案内 | ||
