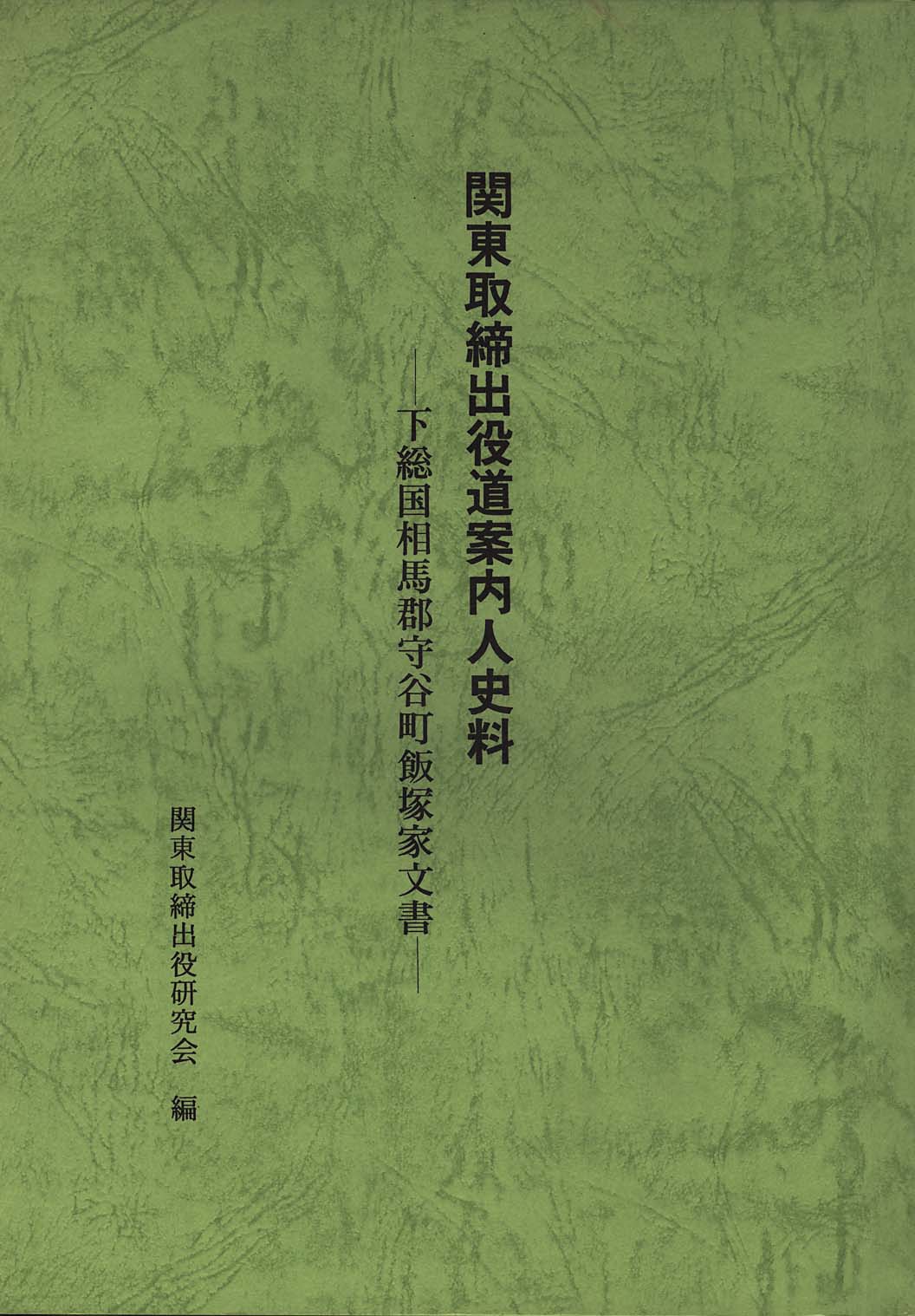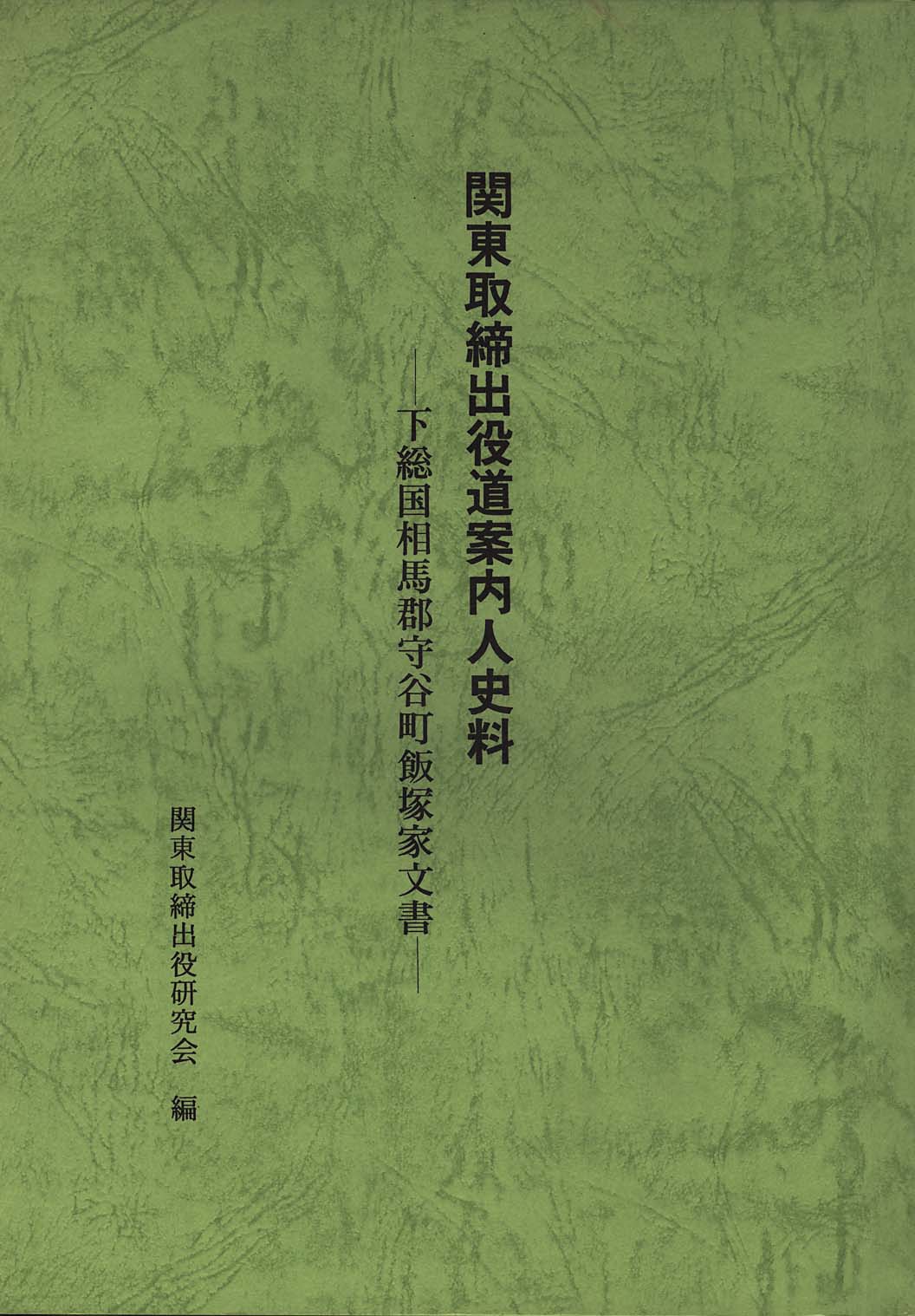飯塚源蔵家は、江戸時代には関東取締出役の「道案内」を勤め、明治に入ってからは、印旛県・千葉県・茨城県の、逮部・捕亡附属・羅卒・巡査などを勤めた家である。
「道案内」とは、一般的には、文政10年(1827)、関東一円の治安維持のために編成された改革組合村において、関東取締出役や組合村役人のもとで警察活動に従事していた者のことである。
「飯塚家文書」総点数439点の内、206点(役職関係文書)を関東取締出役研究会が購入し、233点(家政関係文書)は取手市史編纂室が購入した。本書には
役職関係文書の内、重要な30点を翻刻し、付録として、同じ守谷町の寄場組合大惣代であった斎藤家の「御用留」(文政12-明治2年)の細目を収録した。
|
| 【収録内容】 |
|
| 論 文 |
|
飯塚源蔵家文書にみる関東取締出役道案内人の実像
|
岩橋 清美 |
近代警察制度と飯塚源蔵
|
安藤 陽子 |
| 飯塚家史料 |
|
諸用留・御用留・御用書物写(嘉永4-6年、安政7-文久1年、慶応2-3年、慶応3年、明治2年)
囚人日割預控帳(安政6-文久1年、元治1-2年)
上総国寄場高村々帳(安政7年)
積金講連名帳(文久1年)
道中日記帳(慶応1年、2年、3年)
関八州寄場組合石高覚(慶応3年)
警部・巡査氏名書上(明治期)
申渡/通達/探索書/辞令/ほか
|
|
飯塚家文書目録
|
|
付:関東取締改革御用留細目(下総国相馬郡守谷町寄場組合大惣代「斎藤家文書」より)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |