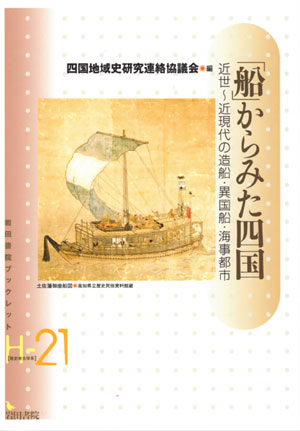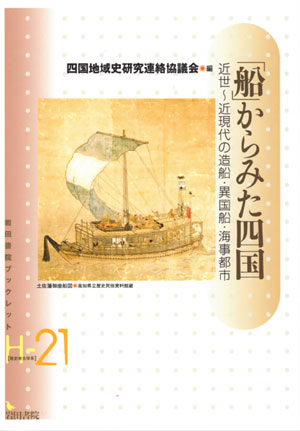2013年11月に開催された四国地域史研究連絡協議会のシンポジウム第6回「「船」からみた四国」(於:香川県立ミュージアム)の成果をもとに編集。
造船史、流通・交通史、対外交渉史、異国観・国内観の変遷など、「船」への着目は 歴史検討の方法として豊かな可能性をもつ。また、四国各県ともに、社会にとって「船」が重要な役割を果たしたという共通点がある一方で、瀬戸内海と太平洋という性質の異なる海が存在するという相違点も見出すことができる。本書では、これらの共通点や相違点を踏まえて、四国という地域のもつ特性に迫る。 |
|
| 【主要目次】 |
|
| 第1章 |
日本船舶史の流れ |
| |
(東京大学名誉教授)安達 裕之
古代から近代初期にかけての造船、特にその船体構造の特徴と歴史的な展開を述べつ、船体の地域性と材料供給の関連を指摘する。
|
| 第2章 |
瀬戸内の和船と道具の発達
−一本水押(みよし)の棚板構造船をめぐって− |
| |
(瀬戸内海歴史民俗資料館)織野 英史
この構造の特徴を東アジアとの比較から論じ、その形状・名称の分布から瀬戸内海発生説を記す。
|
| 第3章 |
高松藩船団の成立と展開 |
| |
(香川県立ミュージアム)御厨 義道
瀬戸内海という軍事上枢要な海に面している高松藩の船団成立と、江戸初期の海防問題を論じる。
|
| 第4章 |
江戸時代 阿波の民衆が見た「異国」
−異国船漂着事件などを中心に− |
| |
(徳島県立文書館)徳野 隆
江戸中期以降の漂着西洋船の事例をもとに、その対応を村や郡代の視点から紹介する。
|
| 第5章 |
日本最大の海事都市・今治の身近なルーツ
−当地方の江戸後期から昭和初期までの地域色ある船− |
| |
(NPO法人 能島の里)大成 経凡
今治藩の御座船から、桜井商人の椀舟、近代母船式蟹漁業の蟹工船まで。
|
| 参考文献 |
|
|
|
  |