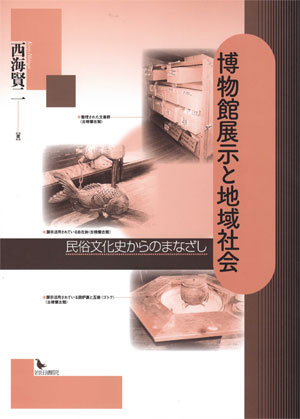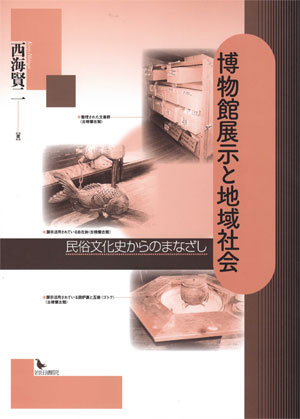歴史系(民俗系)博物館の展示批評を中心に、地域と博物館の役割を考える。
著者の地元で常民文化研究会を主宰して40年。地域に暮らす人々との座談会や、学生時代から撮りためた民俗生活写真のスライド巡回などを通して、一人ひとりの自分史を掘り起こし、それを地域の歴史、地域の文化に広げていきたいという著者の願いは、いまも熱い。
石造物展示の方法、民間信仰をどう見せるかなど、研究者と入館者の目線で記述する。 |
|
| 【主要目次】 |
|
| 1 |
郷土資料と地域 |
| 2 |
ムラが蘇るとき |
| 3 |
小田原における歴史・文化の掘り起し |
| 4 |
高島屋・渋谷区松濤美術館・郡山市美術館特別展「慈愛の造形―木喰の微笑仏」によせて |
| 5 |
福島県立博物館企画展「生の中の死」によせて |
| 6 |
茨城県立歴史館企画展「ねがい・うらない・おまじない―欲望の造形」によせて |
| 7 |
神奈川・静岡県 19博物館・資料館共同企画「東海道宿駅制度400年記念特別展」によせて |
| 8 |
相模原市立博物館収蔵品展「豊かさの研究―石器時代から見る未開と文明展」によせて |
| 9 |
文化遺産学の継承をめぐって |
| 10 |
地域の文化をどうつくるか ―常民文化研究会の活動から― |
| 11 |
大根おろし考 ―紀年銘民具再考― |
| 12 |
相模原市立博物館・高知県立歴史民俗資料館 二つの石造物展示によせて |
| 13 |
千葉県立中央博物館秋の展示「語る・観る 房総の石仏」によせて |
| 14 |
川越市立博物館企画展「民間信仰のかたち―地域と講」によせて |
| 15 |
ベルナールフランク著『「お札」にみる日本仏教』書評 |
| 16 |
「四国遍路」研究をめぐる最近の動向
―「旅の祈りの道―阿波の巡礼」展によせて― |
| 17 |
練馬区郷土資料室特別展「「講」ってなあに?」によせて |
| 18 |
森武麿著『1950年代と地域社会―神奈川県小田原地域を対象として』を民俗から読み直す |
| 19 |
常陸木食上人考 ―木食観海によせて― |
|
|
  |