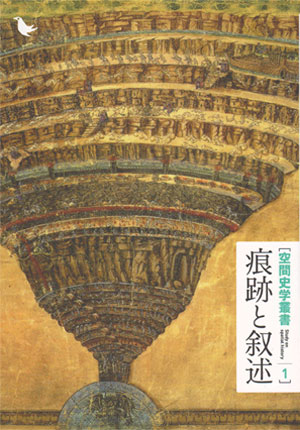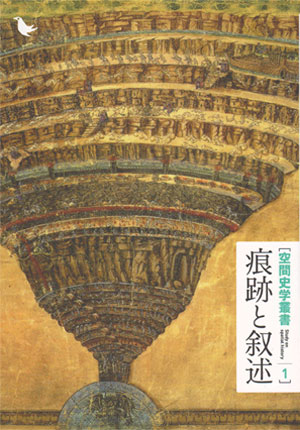「空間史学研究会」始動────────野村 俊一
隣接領域分野の研究者たちと、「空間史学研究会」という学際的研究の場を立ち上げた。テーマは「空間の歴史」。 建築史学では、建築の形態や技法にくわえ、意匠や使われ方、背景となる社会や文化までも問う。仏堂を例に取ってみても、そこに奉られた仏像や堂内で行われる儀礼はもちろん、まわりを荘厳する絵画、全体を包括する仏教理念、仏堂を経営する檀越や僧侶たちの政治や思惑など、解くべき問題は多岐にわたる。ゆえに隣接領域分野と切磋琢磨する機会も、必然的に多くなる。(中略)
モノ・言葉・絵画などさまざまな「痕跡」を頼りに、見えるものにとどまらず、いかに見えないものまでも「叙述」するか。このような予感と期待のもと、本叢書は新たな空間の地平を目指すべくして始動した、ありそうでなかった試みの一つのドキュメントである。 |
|
| 【主要目次】 |
|
| 新たな学術分野の創出へ |
佐藤 弘夫 |
| 「空間史学」への期待 |
長岡 龍作 |
| <特集:痕跡と叙述> |
|
神・彼岸・コスモロジー
−歴史学における「空間」の発見− |
佐藤 弘夫 |
| 夢見と仏堂 −その礼堂の発生に関する試論− |
藤井 恵介 |
行為と感応の場としての空間
−表象の読み方を考える− |
長岡 龍作 |
| <論文> |
|
| 江戸のつぶれ家−尾張屋版切絵図と四谷怪談− |
大川 真 |
| 山水の生成とその諸空間 −中世禅院における境致と社友の考察を通して− |
野村 俊一 |
| 仏像光背考 −〈ほとけ・像・人〉の場と空間− |
海野 啓之 |
| アルベルティの『建築論』における「スパティウム」(空間)の用法 |
飛ヶ谷潤一郎 |
『源氏物語』賀茂祭の物見空間と正妻
−桟敷の座と紫の上造形− |
岩原 真代 |
| 煉獄という空間 −15〜16世紀のダンテ受容にみるその組織化と視覚表象− |
石澤 靖典 |
| <フィールド・ノート> |
|
| トルチェッロの聖母−都市の記憶、空間の記憶− |
佐々木千佳 |
|
|
|
|
  |