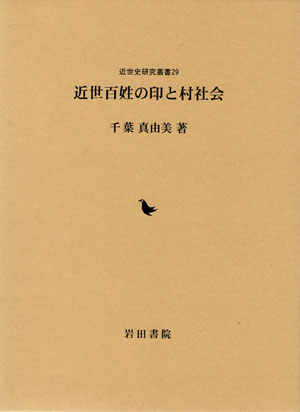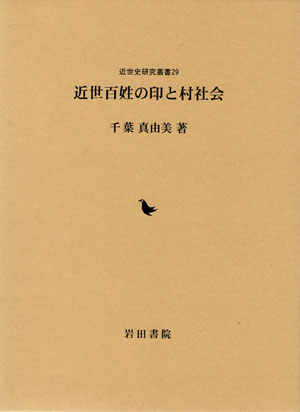一般の民衆に至るまでが印を多用する、現代の「はんこ社会」の萌芽は近世に求められよう。近世では、村の百姓に至るまでが個々に印を所持し、使用するようになった。
本書は、近世の百姓が使用する印および捺印行為の諸相を明らかにし、ここから日本近世の村社会、さらには日本近世社会の特質を導き出すことを目的とする。
印は文書における唯一の意思表示であり、意思表明として使用される印は村社会に様々な影響をもたらした、ということを念頭に置き、近世前期から幕末期までの南関東を事例として、「文書社会」といわれるその具体相を明らかにする。 |
|
| 【主要目次】 |
|
| 序 章 |
| 第Ⅰ部 |
近世前期の惣百姓印 |
| 第1章 |
近世前期関東における惣百姓印 |
| 第2章 |
近世の惣百姓印
―南関東地域の事例収集を中心として― |
| 第Ⅱ部 |
文書作成と百姓の印 |
| 第3章 |
近世百姓印の捺印と使用状況
―相模国津久井県牧野村を事例として― |
| 第4章 |
近世百姓印の機能と文書作成
―相模国津久井県牧野村を事例として― |
| 第5章 |
名主日記にみる村の文書と捺印(1)
―相模国高座郡座間宿村庄右衛門の元文四年日記から― |
| 第6章 |
名主日記にみる村の文書と捺印(2)
―武蔵国多摩郡乞田村茂兵衛の明和八年日記から― |
| 第Ⅲ部 |
文書作成と百姓の印 |
| 第7章 |
近世中後期村落における印の相続と女性当主
―武蔵国多摩郡大沼田新田を事例として― |
| 第8章 |
近世百姓印と村の公文書 |
| 第9章 |
近世後期村落における出入と捺印
―武蔵国多摩郡大沼田新田を事例として―
|
| 終章 |
近世の村社会における印と捺印 |
|
|
  |