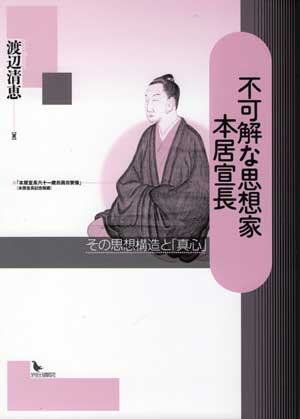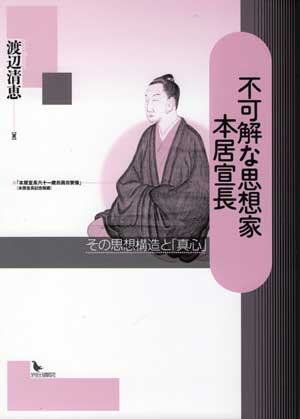「そもそも道は、もと学問をして知ることにはあらず、生まれながらの真心なるぞ、道には有ける」(『玉勝間』)
「改めて宣長学の意義について考えてみると、宣長の思想がそれまでの考え方と決定的に違うと思われる点は、儒学の「修身斉家治国平天下」に代表されるような、個人個人が身を修めることによって、国家を治めようとする方向を捨て、「真心」という言葉に表現される、人間の心情のさまざまな在り方を認めたというところにあると考えられる。そのように考えると、宣長が、文学論や言語学を駆使しながら辿り着いた「古道論」は、「真心」という人間心理の自由を認め、その上で成立可能な社会の在り方を模索した結果とみなすことができるのではないだろうか。人間の心の様々な形態を認めても、社会を成立させるための具体的な方策が、「もののあはれ」による他者や神々との交感であり、また、手本となるべきものが、皆が「真心」を持って、穏やかに「上下和合」した日本古代であり、天皇を中心とした社会であったということができるのである。」(終章より) |
|
| 【主要目次】 |
|
| 序章 |
本居宣長をめぐる諸問題 |
| 第1章 |
『古事記伝』における宣長の世界観 ―神代巻を中心に |
| |
道/神/理 |
| 第2章 |
本居宣長と市川鶴鳴 |
| |
本居宣長の儒教観/市川鶴鳴の儒教観 |
| 第3章 |
本居宣長の文学論と言語観 |
| |
文学論/言語論 |
| 第4章 |
本居宣長と「平安京」 |
| |
宣長と「平城京」/宣長と「平安京」/宣長における都市と文学 |
| 第5章 |
本居宣長の和歌論
―「ツタナクシドケナキ」人間観の形成と発展 |
| |
宣長の和歌論と人間観―『あしわけおぶね』/
和歌と「もののあはれ」 |
| 第6章 |
「まことの理は、思慮の及びがたきこと」―本居宣長の「理」に関する一考察 |
| |
宣長の『古事記』解釈/政治論への展開 |
| 終章 |
宣長学の意義とは ―「聖人」から「真心」へ |
|
|
  |