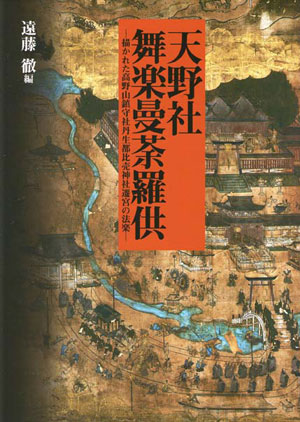 |
天野社舞楽曼荼羅供 −描かれた高野山鎮守社「丹生都比売神社」遷宮の法楽− 遠藤 徹 編 (東京学芸大学准教授/1966年生まれ) 2011年2月刊 A5判・378頁+口絵8頁・上製本・カバー装 ISBN978-4-87294--674-1 C3039 7400円 (税別) |
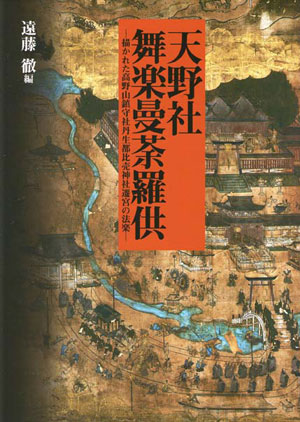 |
天野社舞楽曼荼羅供 −描かれた高野山鎮守社「丹生都比売神社」遷宮の法楽− 遠藤 徹 編 (東京学芸大学准教授/1966年生まれ) 2011年2月刊 A5判・378頁+口絵8頁・上製本・カバー装 ISBN978-4-87294--674-1 C3039 7400円 (税別) |