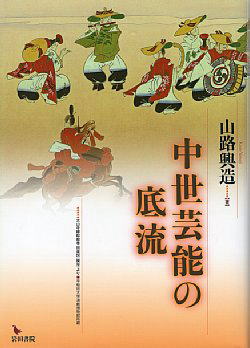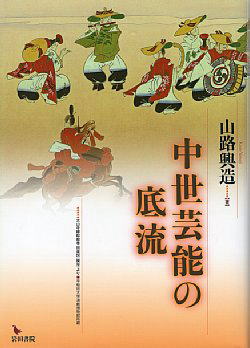「中世期の民衆が社会生活のなかで享受した芸能文化というものの実態を、その環境のなかで描きたかったのである。
もちろん、中世芸能の源流を考察した論も含まれてはいるが、これまで中世芸能の研究といえば、今日まで古典芸能として生き延びた「能・狂言」の研究が中心となりがちであったのに対して、本書では、中央のみならず、地方をも視野に入れて、中世の人々が生活のなかで享受した芸能の実態を明らかにすることを目的としている。」(「あとがき」より)
|
| 【主要目次】 |
|
| 第1部 |
古代的芸能の展開 |
| 第1章 |
伎楽・舞楽の地方伝播 |
| 第2章 |
「楽戸」の伝流
―芸能民差別の一つの源流― |
| 第3章 |
御田植祭り考
―一宮祭祀を中心に― |
| 第4章 |
「田楽」という芸能 |
| 第5章 |
「田楽躍り」の芸態 |
| 第6章 |
宇佐八幡宮放生会の傀儡戯考 |
| 第7章 |
傀儡田楽考 |
| 第8章 |
獅子舞の原型とその変容 |
|
| 第2部 |
中世社会と芸能 |
| 第1章 |
荘園鎮守社における祭祀と芸能
―若狭三方郡を中心として― |
| 第2章 |
中世山村における祭祀と芸能
―天竜川沿いと越前の小祠・小堂を中心に― |
| 第3章 |
中分された祭祀と芸能
―隠岐国島前の田楽を例に― |
| 第4章 |
中世村落と祭祀
―中世の宮座祭祀を中心に― |
| 第5章 |
中世武士団の祭祀と芸能
―下野国「今宮祭祀録」の周辺― |
| 第6章 |
中世後期の郷村と雨乞
―風流踊りの土壌― |
|
| 第3部 |
寺院と芸能 |
| 第1章 |
修正会の変容と地方伝播 |
| 第2章 |
修験の延年芸能 |
| 第3章 |
田遊び論の構想
―鎌倉武士政権の芸能政策― |
|
|
  |