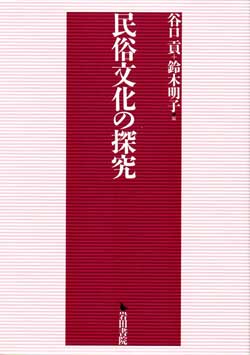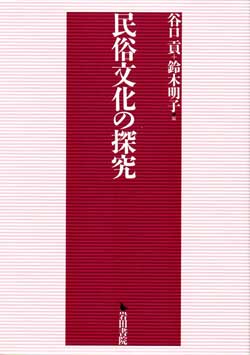| 倉石忠彦氏(國學院大学客員教授)のもとに、学内外の多彩なメンバーが参加。 |
| 【主要目次】 |
|
| Ⅰ 演者と観客―送り手と受け手の交流― |
|
交錯する関係・受けとめる身体
-空間と組織からみた阿波踊り- |
中野 紀和 |
| 「よさこい」をめぐる若者論の現在 |
内田 忠賢 |
女相撲の観客論
-明治以降の新聞・雑誌記事からみる観客反応を中心に- |
亀井 好恵 |
| |
|
| Ⅱ 祭りと信仰の構成 |
|
| 木曽御嶽講と星祭り |
牧野 眞一 |
地神信仰の形成と展開
-神奈川県二宮町の地神塔造立を中心に- |
沼﨑 麻矢 |
盆に迎える霊
-「ウラ盆」と善光寺信仰- |
谷口 貢 |
沖縄久高島の祭祀と神役の区分
-来訪神祭祀をめぐって- |
森田 真也 |
| 薬種商における同業神信仰とその祭祀集団 |
加藤 紫識 |
| |
|
| Ⅲ 民俗地図の可能性 |
|
民俗地図再検討試論
-民俗地図作成過程における妊娠中の食物禁忌- |
倉石あつ子 |
| 民俗地図リテラシー-「正月魚」を例として- |
安室 知 |
| 十日夜のワラデッポウの唱え言葉 |
三輪 京子 |
| |
|
| Ⅳ 語りの生成 |
|
| 「種の藤助」考-田の神信仰と祝言職- |
菱川 晶子 |
先祖に口説く村の歴史
-大分県臼杵市諏訪津留の叙事歌謡- |
厚 香苗 |
| 折口信夫「生き口を問ふ女」と大阪言葉 |
上野 誠 |
| |
|
| Ⅴ 民俗学の方法 |
|
都市民俗学の理論化
-倉石都市民俗学の貢献と展開- |
和崎 春日 |
縦から横へ
-身体技法で読み解くお産の伝承- |
鈴木 明子 |
| |
|
| Ⅵ 民俗の発見―移住・しつけ・歴史― |
|
| 引揚者の民俗学 |
島村 恭則 |
| 韓国における父親の娘に対するしつけの変化 |
倉石 美都 |
| 中世後期朽木氏による関支配の特質 |
山野井健五 |
| |
|
| 倉石忠彦先生 略年譜・著作目録 |
|
| |
|
|
|
|
|
  |