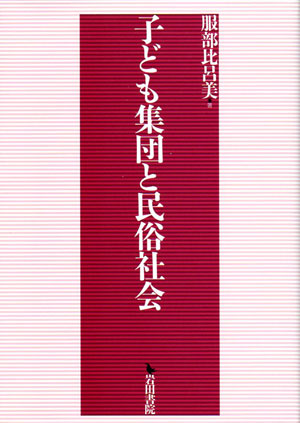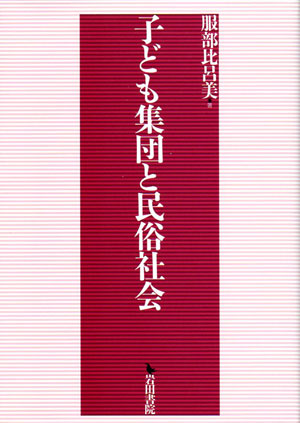「本研究の目的は、日本における子ども集団の実態を民俗事象から叙述することで、「子ども」という社会階層の存在とその役割を確認し、民俗学の立場から児童生活史研究を推し進めることである。」(序章より)
子ども集団が担う行事を地域社会の行事全体の中で捉え直すことをめざし、著者の出身地沼津市の事例を確認し、それとの比較検討のため、他地域のサイノカミ祭祀や地蔵盆などにおける「こども組」の位置づけをおこなう。また、近世の草双紙や、大正期の児童雑誌の分析をとおして
子ども観の変遷をたどり、近代以降に組織化された「少年団」「子ども会」のありかたについても考察した。 |
| 【主要目次】 |
|
| 序 章 |
|
| 第1章 |
子ども集団の実態 |
| |
静岡県沼津市岡宮・岡一色の位置と歴史/
ムラの年中行事と子ども集団の実態/
天神講とアガリ講サガリ講 |
| 第2章 |
サイノカミと子ども集団 |
| 第1節 |
静岡県東部地域のサイノカミ祭祀と子ども集団 |
| 第2節 |
山形県鶴岡市羽黒町手向のサイノカミ祭り |
| 第3節 |
サイノカミと産神問答譚 |
| 第4節 |
折口信夫のサイノカミ観 |
| 第3章 |
盆行事と子ども集団 |
| |
福井県小浜市西津の地蔵盆/
同市甲ケ崎の精霊船/
盆行事に見られる子ども集団の特質 |
| 第4章 |
出版物に見る子ども観 |
| 第1節 |
草双紙類「桃太郎話」の構成と比較 |
| 第2節 |
絵雑誌に見る民俗倫理観
−『子供之友』甲子上太郎を事例に |
| 第5章 |
少年団と子ども会 |
| |
若者組と青年団、子ども組と少年団/
岳陽少年団の成立と活動/
沼津市の子ども会 |
| 終 章 |
まとめと今後の課題 |
|
|
  |