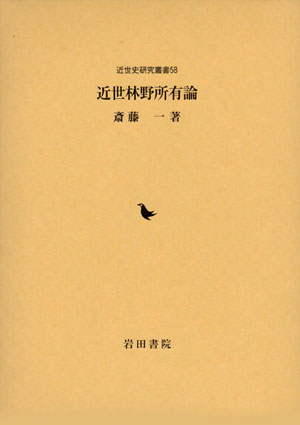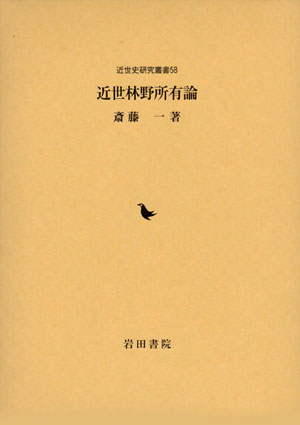「以上のような学説史を見る中で、本書では村の林野の「地盤所持」を否定した戒能通孝の立論と、それを批判し「地盤所持」を認めた西川善介の論点を検証することを基軸に、近世林野所有を考えていくものとする。(中略)
本書の独自性は、こうした議論を止揚する概念として、「領有」「所持」と並んで、村による「テリトリー」支配という規定を提起することにある。この「テリトリー」は、中世以前から村が育んできた観念として位置づけられ、そこでは「地盤所持」的に排他的所有が行われていたのでなく、「毛上の重層的所持」ともいうべき状況が一般的に存在していたことを明らかにしていきたい。(中略)
本書で基幹史料として用いた「松江藩郡奉行所文書」(島根県立図書館蔵)は近世後半に松江藩の郡奉行所で取り扱った裁判資料であり、その中でも山論の数は多く、近世の林野所有を考察するのに絶好であった。同文書の内容は当事者からの訴状類に加えて、郡奉行所内の内部文書や調査報告など多岐にわたっていて、管見の限り他に類を見ない幅広さを有している。…そして、日本全国における近世林野の状況を探る必要があると考え、一年をかけて、全国の自治体史に記された林野の内容を調査した。最終的には3600冊の自治体史にアクセスし、90の自治体史の資料を用いることになったが、それは全国の林野の状況を概観することにもなった。」(本書「序章」より) |
|
| 【主要目次】 |
|
| 序 章 |
近世林野所有論の意義と研究史 |
|
| 第一部 |
日本近世における林野所有の構造 |
| 第一章 |
鉄師と農民の争論から見る近世林野所有
‐戒能通孝学説と「毛上の重層的所持」‐ |
| 補論1 |
出雲鉄山「所有」の再考察
‐佐竹昭氏の論考と広瀬藩領入間村の事例を題材に‐ |
| 第二章 |
山札から見る入会と「領有」
‐信濃と出雲の比較を通して‐ |
| 第三章 |
「割山」再考
‐古川貞雄と西川善介の研究を出発点に‐ |
| 第四章 |
近世的「所持」の諸局面
‐栃の木、落葉掻き、蛸穴などに見る「毛上」所持− |
|
| 第二部 |
山野河海をめぐる近世社会の諸関係 |
| 第五章 |
近世木地師の存在形態と地域社会
|
| 第六章 |
山論に見る近世寺社領の特質
‐「松江藩郡奉行所文書」の諸事例から‐ |
| 第七章 |
近世村と領主林業の山
‐秋田藩における「徒伐」をてがかりに‐ |
| 第八章 |
藻草入会の近世的特質と共同体
−浜名湖の諸事例から‐ |
| 補論2 |
「属地主義的共同体」の考察
‐貰魚、落葉掻き、落穂拾いに見る生存権行使‐ |
| 終 章 |
近世林野から見えるもの |
| 付:索引 |
|
|
|
  |